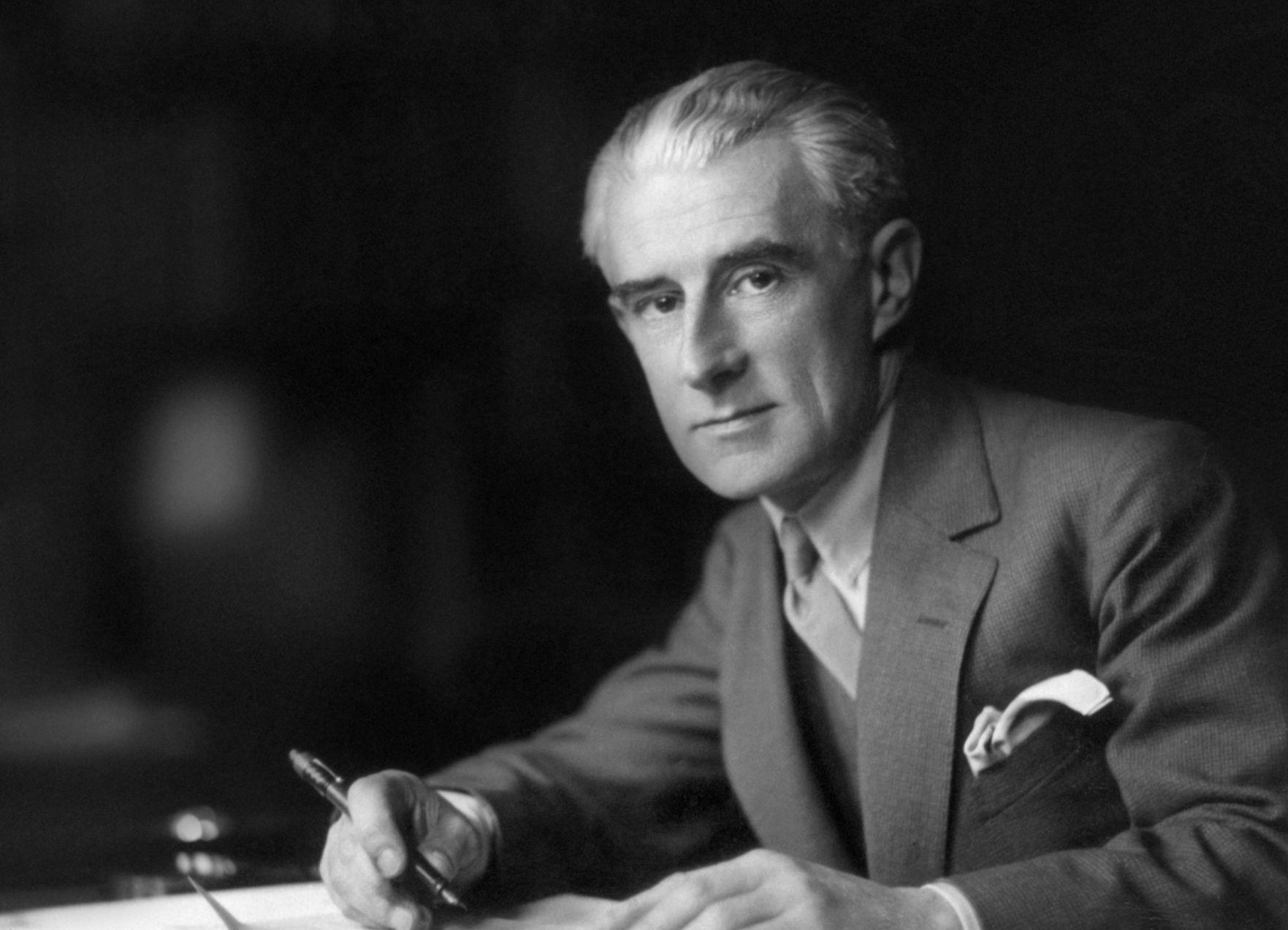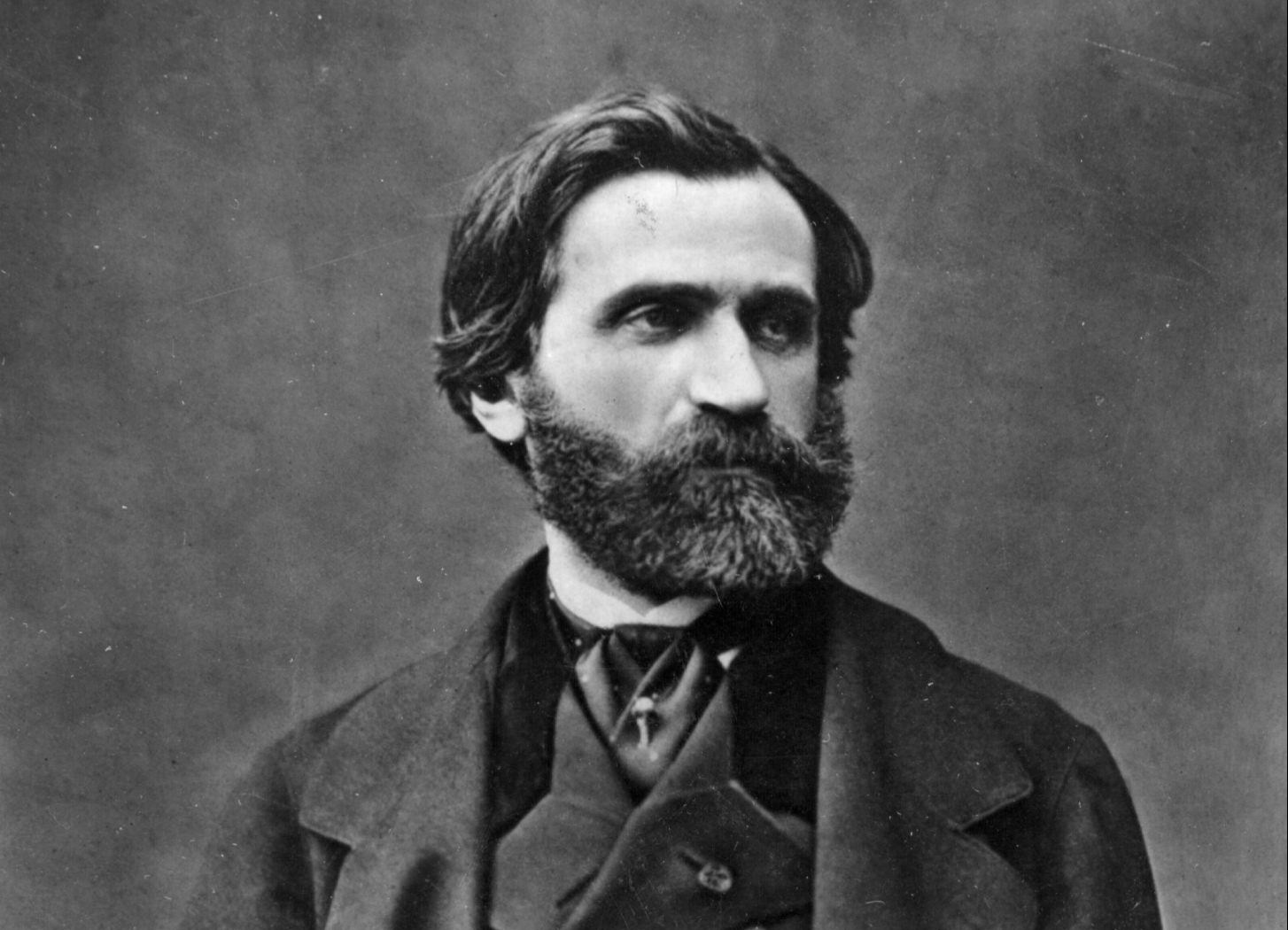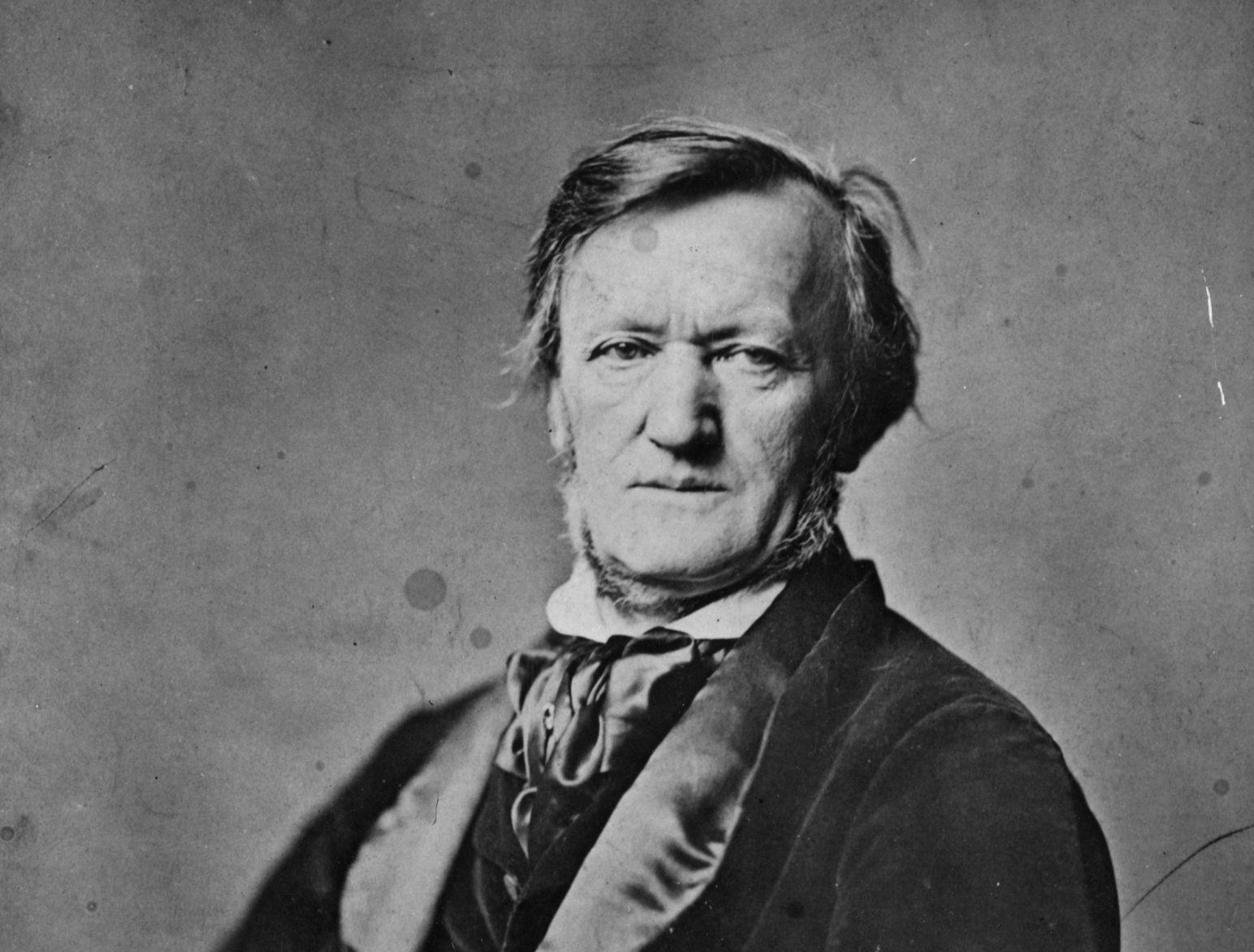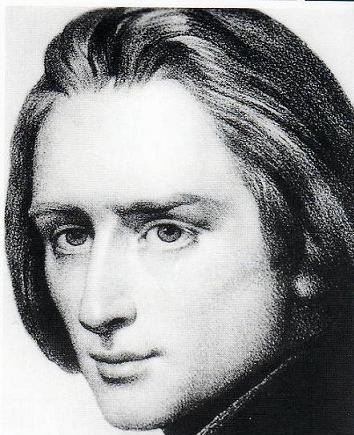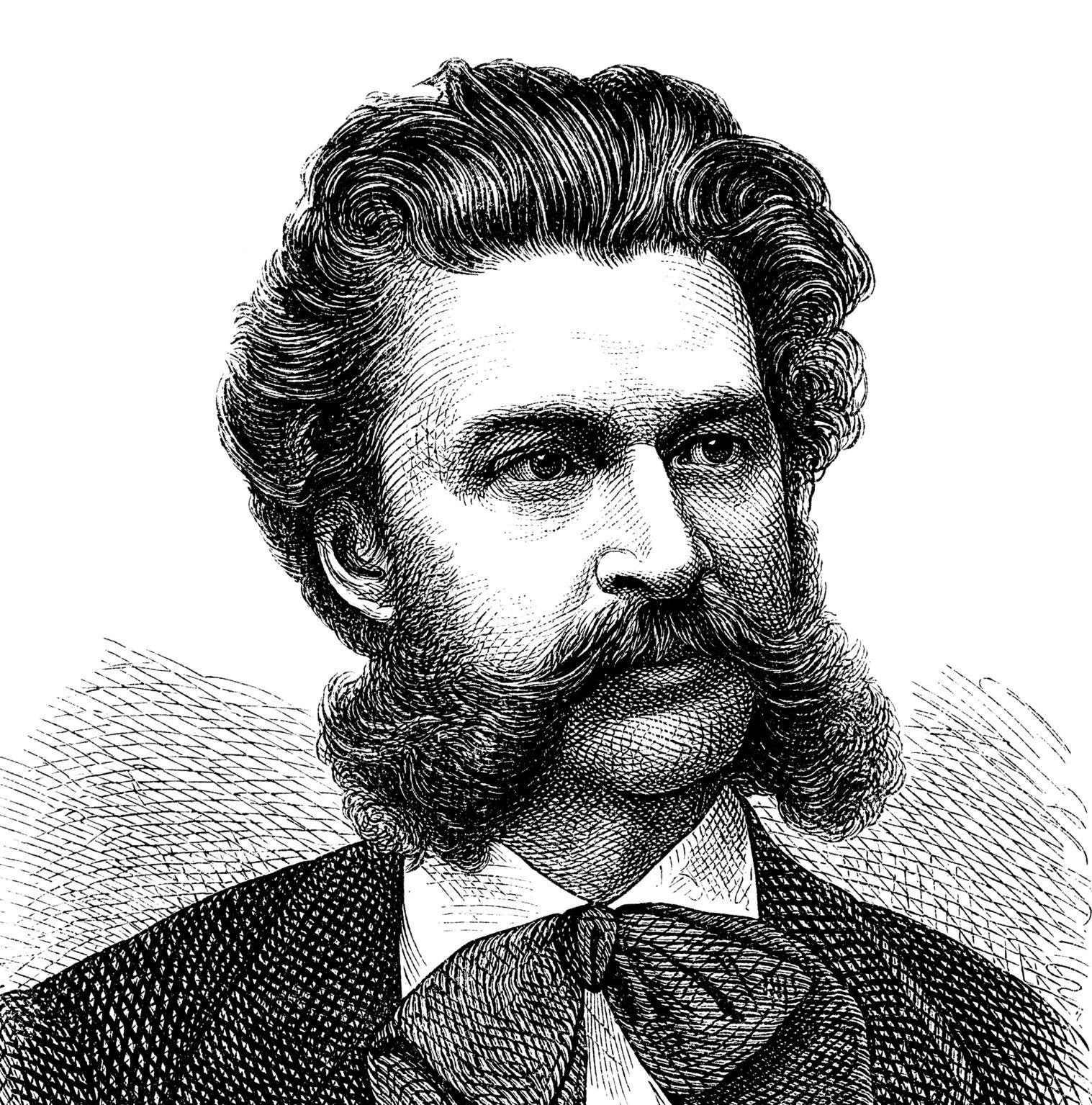序章 婚活市場におけるマーケティングの新潮流
21世紀の日本社会において、結婚はもはや単なる人生の通過儀礼ではなくなった。少子化の進行、未婚率の上昇、ライフスタイルの多様化によって、結婚は「選択されるもの」となり、同時に「選ばれるための競争の場」とも化している。この状況の中で浮上したのが「婚活マーケティング」という概念である。
婚活はかつて親や地域社会に媒介される場であったが、いまや婚活アプリや結婚相談所、街コンや地域おこし協力隊を絡めたイベントなど、マーケティングの色彩を帯びた場へと移行した。その中で、永島もえと江藤あおいという二人のマーケター/実践者が果たした役割は大きい。彼女たちは単なる広告戦略を超えて、人々の「愛されたい」「結婚したい」という欲望を「商品」として可視化し、それをブランド化していった。
第Ⅰ部 永島もえ・江藤あおいの登場と婚活マーケティングの基盤
第1章 婚活マーケティングとは何か
婚活マーケティングとは、結婚相手を探す活動そのものを「市場的な文脈」で捉え、そこに広告・ブランディング・ターゲティングを持ち込む試みである。
従来の結婚相談所が提供していた「紹介」の機能は、現代においては「マッチングプラットフォーム」と「自己演出のメディア戦略」へと変貌した。つまり、結婚相手を探すことは「恋愛」よりも「市場における自己の価値提示」に近くなっている。
この背景には、婚活市場がすでに「商品市場」のように細分化し、年収・学歴・容姿・趣味といったスペックが数値化される社会的傾向がある。その中で、マーケティング的発想が不可欠になったのだ。
第2章 永島もえの戦略的発想
永島もえの強みは、恋愛を「物語」としてパッケージ化することにあった。彼女はSNSで自身の婚活体験をドラマ仕立てで発信し、多くのフォロワーを得ることに成功した。この戦略はまさに「コンテンツマーケティング」であり、自身を「婚活の語り部」としてブランド化する手法だった。
例えば、彼女が行った「30日間婚活チャレンジ」は、自らのデート経験を連日投稿する企画で、共感と話題性を呼んだ。フォロワーは「永島もえのストーリーを追体験する」ことで、彼女のブランドを強く認知した。
第3章 江藤あおいの心理学的アプローチ
江藤あおいは一方で、心理学を婚活マーケティングに応用する試みで知られている。彼女は「選ばれる人は、相手に投影させる余白を持っている」という理論を展開し、セミナーや著作を通じて広めた。このアプローチは「恋愛を成功に導く心理学」をベースに、自己演出の方法をマーケティング化した点で特徴的である。
たとえば彼女の提唱する「愛されフレーズ集」は、LINEや初対面の会話で使う具体的な言葉を提示し、それがフォロワーの支持を得て「恋愛心理学×実践マーケティング」のモデルケースとなった。
第Ⅱ部 具体的な事例とエピソード
第4章 SNSを用いた自己ブランディング事例
1. 「婚活インフルエンサー」の登場
婚活市場においてSNSは、単なる情報発信の場ではなく、「自己を商品化する場」としての意味を持ち始めた。永島もえがInstagramやX(旧Twitter)を通じて行った活動は、まさに婚活インフルエンサーの先駆的事例である。
彼女は「デート服のコーディネート」「初対面での会話の鉄則」「既読スルーされたときの心の持ち方」といった具体的なTipsを短文+写真で発信した。ここで重要なのは、情報そのものの有益性に加え、彼女自身が「リアルに婚活をしている人物」であることが、発信の信憑性を強化した点である。フォロワーは「永島もえの物語」に共感し、自分の婚活体験をそこに重ね合わせた。
2. 「ストーリーテリング戦略」
彼女の最も成功した企画の一つに、「30日間婚活チャレンジ」がある。これは、1カ月間毎日異なる男性とデートする記録を投稿するという企画であった。
単なる自慢話ではなく、「今日はこういう期待をして臨んだ」「実際はこんなギャップがあった」「そのとき自分はどう感じたか」というプロセスを赤裸々に描いたことで、多くの女性から共感を呼び、「婚活のリアル」を届ける役割を果たした。
結果的に、この発信は彼女のSNSフォロワーを一気に数万人規模に拡大させただけでなく、婚活関連の企業やイベントからのタイアップ依頼を生み出し、「婚活そのものがマーケティングの対象となる」流れをつくった。
3. 自己ブランディングの心理学
江藤あおいは、こうした永島のSNS戦略を心理学的に分析し、「人は完成された像よりも、成長途中の物語に共感する」と指摘した。つまり、SNSで「私は完璧です」と見せるよりも、「私も迷い、失敗しながら成長している」と示したほうが、共感を呼び、ファンを獲得しやすい。
これはマーケティングでいう「未完成の美学」であり、婚活という領域においても有効であることが実証されたのだ。
第5章 地方都市における婚活イベントとマーケティング
1. 苫小牧市での「街コン」の事例
北海道苫小牧市で行われた「漁港マルシェ婚活イベント」は、永島もえと江藤あおいが関わったプロジェクトとして知られる。地元の食材をテーマにしたマルシェに、婚活の要素を掛け合わせるという試みであった。
イベントの参加者は「出会いを探す男女」と「地元食材のファン」が混在しており、自然な会話のきっかけが生まれるように設計されていた。たとえば「牡蠣を一緒に焼いて食べる」という体験型アクティビティは、緊張を和らげると同時に、共同作業を通じて「疑似的なカップル体験」を提供することにつながった。
2. マーケティング的仕掛け
このイベントの背後には、江藤あおいの心理学的アプローチがあった。彼女は「人は共同作業によって親近感を持ちやすい」という心理学的知見を応用し、単なる交流会ではなく「共同体験型イベント」にすることで、成約率を高めたのである。
結果的に、このイベントから3組のカップルが誕生し、地域新聞にも大きく取り上げられた。
3. 地方都市ならではの価値
永島もえは、この成功を「地方都市だからこそ可能なマーケティング」と評した。大都市圏の婚活イベントでは「数の論理」が優先されがちだが、地方では「地域資源との結びつき」が新しい価値を生む。
つまり、婚活マーケティングは「人と人をつなぐ」だけでなく、「人と地域をつなぐ」仕組みとしても機能し得ることを、この事例は示している。
第6章 婚活アプリと結婚相談所の比較戦略
1. 婚活アプリのマーケティング事例
婚活アプリにおいて永島もえが行った実験は興味深い。彼女は「プロフィール写真を毎週更新する」という戦略を取り、その効果を可視化した。
結果、更新直後の一週間は「いいね」数が平均の2倍以上に跳ね上がることが判明した。これはアルゴリズム上の露出効果と同時に、「新しさ」がユーザー心理に与える影響を示している。
また、プロフィール文に「最近〇〇にはまっています」と具体的な趣味を短く追加するだけで、マッチング率が顕著に上がることも明らかになった。この戦略は「プロフィールを静的な名刺ではなく、動的な日記のように使う」ことを意味する。
2. 結婚相談所のマーケティング事例
一方で江藤あおいは、結婚相談所の会員向けに「第一印象セミナー」を開催した。ここでは、心理学に基づく「表情トレーニング」や「相手に余白を感じさせる会話法」が導入された。
ある参加者の事例では、セミナー後に「これまでまったく申し込みが来なかったのに、1カ月で5件の申込みがあった」と報告されている。これは、相談所が単なるマッチングの場ではなく、「自己演出を学ぶ学校」としても機能することを示している。
3. アプリと相談所の相乗効果
永島と江藤が強調するのは、「婚活アプリと相談所は対立するものではなく、補完関係にある」という点だ。アプリは「出会いの数」を拡大し、相談所は「出会いの質」を高める。
マーケティング的にいえば、アプリは「リード獲得」、相談所は「リードナーチャリング」に相当する。両者をうまく活用することで、婚活全体の成功率は飛躍的に向上する。
第Ⅱ部まとめ
本章では、永島もえと江藤あおいの婚活マーケティングを、具体的な事例やエピソードを通じて検討した。
-
SNSでのセルフブランディングによる「婚活インフルエンサー」の登場
-
地方都市での「地域資源×婚活イベント」の成功
-
婚活アプリと結婚相談所を補完的に活用する比較戦略
これらはいずれも、従来の「出会い」を超えたマーケティング的発想であり、婚活市場の新たな方向性を示している。
第Ⅲ部 心理学と社会学の応用
第7章 「選ばれる人」の心理学
1. 婚活における「選ばれる人」とは
永島もえと江藤あおいが強調するのは、婚活において「相手を選ぶ力」よりも「相手から選ばれる力」の重要性である。
この「選ばれる力」は、外見やスペックだけでは説明できない。むしろ心理学的に分析すると「他者に投影されやすい余白」「安心感を与える雰囲気」「自己効力感と承認欲求のバランス」といった要素が鍵を握る。
たとえば、ある男性参加者(30代後半・年収600万)は、婚活パーティーで積極的に自己アピールをしたが、女性からの人気は低かった。江藤は彼に「自分を語る割合を減らし、相手の話を引き出すこと」を勧めた。すると次のイベントでは、女性から「話しやすい」「安心感がある」と好意的な反応が返ってきた。
この事例は、「選ばれる人」とは自己を誇示する人ではなく、相手に自己を投影させる「鏡」のような存在であることを示している。
2. 心理学的理論からの分析
心理学的にいえば、これは「自己呈示理論(self-presentation theory)」や「投影同一化」の概念と関わる。相手に「自分を理解してもらえた」と思わせる行為は、実際には相手自身の欲望を映し返しているにすぎないが、それが強い魅力として作用する。
江藤あおいはセミナーで、「人は『この人といると、自分の魅力が引き出される』と感じた瞬間に恋愛感情を抱く」と説明する。つまり、婚活におけるマーケティング戦略とは、自己の魅力を最大化するのではなく、「相手の魅力を引き出す装置」として振る舞うことにある。
3. 「余白」の演出
永島もえは、SNS発信においても「余白」を意識した。彼女は自分の投稿に「結論」を書かず、「どう思いますか?」と問いかけるスタイルを多用した。これにより、フォロワーは「自分の意見を反映できる場」として永島の物語に参加し、結果的に彼女自身のブランド力を高めた。
婚活の現場でも同じである。自己を完璧に見せるよりも、「ちょっと足りない部分」「伸びしろ」を見せたほうが、相手の心を動かす。
第8章 婚活におけるジェンダー・役割期待
1. 「男性は収入」「女性は若さ」という固定観念
婚活市場では、いまだにジェンダー役割期待が根強く残っている。
男性は「経済力」や「安定性」で評価され、女性は「若さ」や「外見的魅力」で測られる傾向がある。この構造は婚活アプリの検索項目や、結婚相談所のプロフィール欄にも組み込まれており、まさにマーケティングが社会的規範を再生産する場となっている。
ある婚活アプリでは「男性の年収」が細かく区切られ、女性のプロフィールでは「年齢」が最も目立つ位置に表示されている。これはシステムそのものがジェンダー役割を強化している例である。
2. 江藤あおいの批判と提案
江藤は講演で「婚活はジェンダー規範のショーケースだ」と批判した。
彼女は「女性は若くなければならない」「男性は高収入でなければならない」という規範が、婚活市場に不必要な格差と不安を生んでいると指摘する。代わりに、彼女は「価値の多様性マーケティング」を提案した。
具体的には、「共働き志向の女性に対する家庭的な男性の価値」「都市よりも地方でのライフスタイルを望む人同士の親和性」といった切り口で、相手を評価する枠組みを提示したのである。
3. 永島もえの戦略的活用
一方で永島は、このジェンダー規範を「戦略的に利用する」側面を持っていた。
彼女はセミナーで「相手が持っている役割期待を完全に無視するのではなく、むしろ一度受け入れた上で、自分の強みを再提示するべきだ」と語る。
たとえば、30代後半の女性参加者に対しては「『若さではなく、経験値と安定感』を武器にするストーリーテリング」を推奨した。これは社会的規範を打破するのではなく、マーケティング的に再利用するアプローチである。
第9章 「市場」としての婚活とブランド化
1. 婚活市場は「見えない市場」
経済学的な市場では、需要と供給が明確な数値で表れる。しかし婚活市場では、需要も供給も「人間の欲望」という曖昧な形で存在するため、非常に特殊である。
にもかかわらず、婚活は「市場」として成立している。なぜなら、人々は「結婚相手を探す」という目的のもとに集まり、条件や価値観を提示し合うからである。
2. 自己ブランド化のプロセス
この市場で成功するためには、「自己をブランド化」する必要がある。
永島もえのSNS戦略や江藤あおいの心理学的アプローチは、まさに「婚活者をブランドに仕立てる方法論」であった。
ブランド化には以下の三つのステップがある。
-
差別化:「他の婚活者にはない特徴を提示する」
-
一貫性:「プロフィール、会話、SNS発信を通じて矛盾のないイメージを保つ」
-
物語化:「自分の結婚観や人生観をストーリーとして語れる」
ある40代男性の事例では、永島のアドバイスにより「ただの会社員」から「地域の未来を担うリーダー」という物語を打ち立て、結婚相談所の成婚率が飛躍的に高まった。
3. 婚活ビジネスそのもののブランド化
さらに重要なのは、婚活を支える企業やサービスそのものがブランド化している点である。
たとえば「誠実なサポートで安心」「ハイスペック男性に特化」「地方移住婚に強い」といった特徴を打ち出すことで、結婚相談所や婚活アプリは他社との差別化を図っている。
永島と江藤はこの流れを敏感に捉え、「婚活はもはや個人の活動ではなく、企業のブランド戦略と融合する」と主張している。
第Ⅲ部まとめ
心理学と社会学の視点から、婚活マーケティングを三つの角度で分析した。
-
心理学的側面:選ばれる人は「余白」と「投影可能性」を持つ
-
社会学的側面:婚活はジェンダー規範を反映しつつ、それを戦略的に利用・批判できる
-
市場的側面:婚活は自己とサービスのブランド化がカギを握る
ここで見えてくるのは、婚活マーケティングが単なる「出会いの支援」ではなく、心理学・社会学・経済学を横断する学際的な営みであるという点だ。
第Ⅳ部 実践的アプローチ
第10章 自己演出とストーリーテリング
1. 自己演出の必然性
婚活は「ありのままの自分を見せる場」と誤解されがちである。しかし永島もえと江藤あおいは、これを強く否定する。
彼女たちの立場は明確だ――「婚活は自己演出の舞台である」。
ここでいう演出とは、虚偽ではなく「相手が理解しやすいように自分を整理して提示すること」である。
2. ストーリーテリングの力
永島は、自己演出の中でも「ストーリーテリング」を重視した。
ある30代前半女性の相談に対し、彼女はこうアドバイスした。
「自分の職業や趣味を列挙するだけでは『スペックの羅列』に過ぎません。大切なのは、それがあなたの人生観や未来の結婚像につながる物語になっているかです。」
例えば、その女性が「旅行好き」と語るとき、単に「旅行によく行きます」ではなく、
「旅を通じて世界中の文化を知り、将来のパートナーと共に人生を広げていきたい」という物語に変換すれば、同じ趣味が「結婚観」に結びつく。
これはマーケティングでいう「コンテクストの付与」に近い。
3. 「物語化」されたプロフィール
江藤はさらに心理学的に解説する。
「人は情報の羅列ではなく、物語を通して相手を理解し、共感を抱く」――これはナラティブ心理学の基本原理だ。
プロフィール文に「私は○○です」という断定を重ねるよりも、「私はこういう経験をして、今はこういう価値観を持ち、未来はこうしたい」と語ったほうが、人の心は動く。
彼女のセミナー参加者の中には、プロフィールを「職業・趣味・条件」だけで埋めていた男性が、永島の助言によって「両親が仲睦まじい姿に憧れ、将来も同じようにパートナーを大切にしたい」と書き換えた結果、申込数が3倍に増えたという事例もある。
第11章 成功・失敗エピソードの分析
1. 成功エピソード:札幌の30代女性の事例
ある30代半ばの女性は、婚活アプリで2年近く成果が出ず、自己否定に陥っていた。
彼女は永島のSNS投稿を参考に「30日間、プロフィール文を毎日少しずつ更新する」というチャレンジを実践。
「今日はパン作りに挑戦しました」
「休日に読んだ本から学んだこと」
といった日常の小さな記録を追加していった。
すると「あなたのプロフィールを読むと人柄が伝わってきます」というメッセージが急増し、ついに同じ趣味を持つ男性と出会い、半年後に成婚。
この事例は「小さな更新の積み重ねが、ストーリーを豊かにし、共感を呼ぶ」ことを証明している。
2. 失敗エピソード:高収入男性のケース
一方で失敗事例もある。
40代前半、年収1,000万円超の男性は、結婚相談所でのプロフィールに「年収」「高級車」「海外旅行」といった要素を全面に押し出していた。
しかし面談をした女性の多くが「魅力を感じない」「自分がアクセサリーのように扱われそう」と否定的な感想を抱いた。
江藤はこのケースを「自己演出の失敗例」と分析した。
心理学的には「自己愛的呈示」が強すぎると、相手は「共感」よりも「不安」を感じる。
つまり、高いスペックも「物語化」されなければ逆効果になる。
3. 中間的事例:地方移住婚の試み
苫小牧市で実施された「地方移住婚活イベント」では、数組のカップルが成立した一方で、半数以上が関係を継続できなかった。
理由は「移住」という大きなライフスタイルの変化が、十分に共有されていなかったからだ。
永島は「マーケティング的には成功だが、心理学的には期待値のコントロールに失敗した」と総括した。
この事例は「条件やコンセプトを魅力的に見せる」だけでなく、「その後のリアリティをどのように伝えるか」が重要であることを示している。
第12章 価格設定とターゲティングの妙
1. 婚活における「価格」の意味
婚活サービスの価格は単なる金額ではなく、「信頼」「真剣度」「ブランド価値」の指標である。
結婚相談所の入会金が高額であるほど「遊び目的の人が少ない」と評価され、逆に低価格のサービスは「気軽に出会えるが真剣度は低い」と解釈されやすい。
これは経済学でいう「シグナリング効果」が婚活市場でも作用している例である。
2. 永島もえの「価格の物語化」
永島は価格設定に関して、「高い=安心」「安い=気軽」という単純な二分法ではなく、「価格そのものをストーリーにする」ことを提案した。
例えば、ある結婚相談所が「入会金10万円のうち、5万円は成婚した方の記念パーティーに還元します」と掲げたところ、「お金が単なる費用ではなく、未来への投資になる」という物語を打ち出せた。
結果として、この相談所は若い層からの入会希望者が急増した。
3. 江藤あおいのターゲティング戦略
江藤は「ターゲティングの精度こそ、婚活成功率を左右する」と説く。
彼女が提案した方法は、「顧客の不安に基づいたセグメント化」である。
-
経済的不安層:「安定志向」「安心の象徴」となる男性像を求める
-
孤独不安層:「共感力」「家庭的な温かさ」を強く評価する
-
承認欲求層:「見栄え」「社会的に誇れる相手」を選びやすい
このセグメントに合わせたマーケティングを行えば、サービス提供者も利用者も「選びやすさ」を実感する。
4. アプリと相談所の価格対比
婚活アプリは月額2,000〜5,000円程度が主流で、ターゲットは「まずは気軽に試したい層」。
一方で相談所は入会金10万〜30万円、月会費1万〜2万円と高額で、ターゲットは「真剣層」。
永島と江藤は「両者の価格差は単なるビジネスモデルの違いではなく、心理的な『覚悟』の差を演出している」と指摘する。
つまり、価格は単なる数字ではなく、「自分は本気です」という心理的宣言のツールになっているのだ。
第Ⅳ部まとめ
本部では、婚活マーケティングを実践的な観点から検討した。
-
自己演出とストーリーテリング:プロフィールや会話を「物語化」することで相手の共感を得る
-
成功と失敗のエピソード:小さな更新の積み重ねは成功を生むが、自己愛的な誇示は失敗を招く
-
価格とターゲティング:価格は単なるコストではなく「真剣度と信頼」のシグナルであり、ターゲット層に合わせた戦略が不可欠
ここで明らかになったのは、「婚活マーケティングは戦略的な自己演出と市場理解の両輪で動く」ということだ。
永島もえと江藤あおいの事例は、その実践的な知恵を鮮やかに示している。
第Ⅴ部 現代社会と婚活マーケティングの未来
第13章 AI・デジタル化時代の婚活マーケティング
1. 「出会い」の定義が変わる時代
スマートフォンが恋愛の入口となった今、「出会う」とはもはや「偶然の邂逅」ではなく、「アルゴリズムによる提示」を意味するようになった。
永島もえはこれを「選ばされる時代の恋愛」と呼んだ。
AIマッチングアプリは、ユーザーの年齢、職業、趣味、会話の傾向、さらには過去のスワイプ履歴を解析して「あなたに合いそうな人」を提示する。
しかし江藤あおいは、その裏に潜む心理的リスクを指摘する。
「AIが提示する“相性の良さ”は、あくまで統計的な親和性であって、“情熱”や“偶然性”を保証するものではない」
彼女は「最適化された出会い」がもたらすのは「安心」ではなく、「退屈」であるとすら述べた。
恋愛の本質にある“予測不能性”が消えつつあるというのだ。
2. デジタル・インティマシー(digital intimacy)の誕生
それでも、AIとテクノロジーは婚活を根底から支えている。
永島は「デジタル・インティマシー(digital intimacy)」という概念を提唱した。
これは、テクノロジーを媒介に形成される新しい“親密さ”の形を意味する。
オンライン通話での「間」の取り方、絵文字の使い方、メッセージの返信スピードなど、微細なデジタル表現が「感情の文法」を作り出す。
江藤はこれを「デジタル言語としての恋愛心理」と呼び、講義で次のように語っている。
「既読スルーは拒絶ではなく、むしろ“考える時間”を与える合図の場合もある。
デジタル社会では、沈黙もまたコミュニケーションの一部になるのです。」
この視点は、婚活マーケティングが単なる「出会いの仕組み」ではなく、「感情の翻訳装置」として機能する未来を予見している。
3. AIコンシェルジュの進化
最近の婚活相談所では、AIがプロフィールを自動生成し、初回メッセージの文面まで提案する機能が登場している。
永島はこの動向を「AIが恋愛の脚本家になる」と形容した。
しかし江藤は、「AIに任せすぎると、恋愛が“模倣の連鎖”になる」と警鐘を鳴らす。
そこで彼女たちが提唱するのは、「AI × 人間の共創婚活」である。
AIが相性の分析や文章提案を行い、人間がそこに“感情の温度”を加える。
つまり、AIは出会いを設計し、人間は物語を紡ぐ。
それが「デジタル時代の婚活マーケティングの理想形」だと二人は結論づける。
第14章 コミュニティ形成と「共同体感覚」
1. アドラー心理学と婚活の再定義
江藤あおいは、アドラー心理学の「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」を婚活に応用している。
それは、「自分の幸せと他者の幸せがつながっているという感覚」のことである。
従来の婚活は、「自分が幸せになるために相手を探す」という個人主義的な発想が強かった。
しかし彼女は、「二人で社会に貢献できる関係こそが真の結婚」と説く。
これは、恋愛や結婚を「社会とのつながりの一形態」として再定義する視点である。
2. コミュニティ婚活の実践
永島もえは、実際に「地域コミュニティ婚活」をプロデュースした。
苫小牧市や釧路市などの地方自治体と連携し、婚活イベントを「地域活性の一環」として設計した。
例えば、漁業や農業など地元の仕事を体験しながら出会う「共働型婚活」。
この形式では、恋愛よりも先に「協働」が生まれる。
その過程で芽生える信頼感が、やがて恋愛感情へと発展する。
江藤はこの現象を、「愛の社会化」と呼ぶ。
恋愛が個人の私的な感情ではなく、共同体を再生させる社会的エネルギーとして機能し始めているのだ。
3. 婚活が「孤立」を癒やす場へ
現代社会の課題の一つは「孤独」である。
リモートワーク、SNS依存、都市の匿名性――これらが人々の心理的孤立を深めている。
江藤は著書で次のように記している。
「婚活とは、愛する人を探す場であると同時に、“誰かと同じ時間を生きている”という感覚を取り戻す営みです。」
婚活イベントが「つながりの場」として機能することは、社会的にも意味がある。
それは単なる恋愛市場ではなく、孤立を癒やす「社会的セラピー」の空間でもあるのだ。
第15章 愛・結婚・マーケティングの融合点
1. 「愛を売る」ことの倫理
婚活マーケティングは、ある意味で「愛を商品化する」営みである。
この点に倫理的な葛藤を覚える人も少なくない。
「愛は純粋であるべきではないか?」「感情を戦略化してよいのか?」
――こうした問いに、永島もえは率直に答える。
「愛を“売る”ことは、愛を“軽んじる”ことではない。
むしろ、愛を“届ける仕組み”を整えることがマーケティングの使命なのです。」
彼女にとって婚活マーケティングとは、愛を偽装することではなく、「愛が届きやすい環境を設計すること」なのである。
2. 「恋愛の持続」もマーケティング
江藤は、「結婚はゴールではなく、関係性のブランドマネジメントの始まり」だと説く。
恋愛初期は高揚感が支配するが、やがて現実が訪れる。
そのときに重要なのは、「関係をどうメンテナンスするか」であり、これは企業のブランド維持と同じ構造を持つ。
彼女は講義でこう語った。
「関係は“熱量の持続”によって維持される。
相手の小さな変化を観察し、感謝や承認を日常的に発信することは、
まるでファンとブランドの関係に似ています。」
婚活マーケティングの本質は、「出会わせること」ではなく、「関係を継続させる仕組み」に移行しつつある。
3. 「個人ブランド」と「関係ブランド」
永島は、「婚活を成功させた人が幸せになるとは限らない」と警告する。
重要なのは「個人ブランド」ではなく、「関係ブランド」を築けるかどうか。
SNS時代には、個人が自己演出を強化しすぎるあまり、「二人の関係性」そのものが空洞化しやすい。
そこで彼女が提案するのは、「二人の物語を共有するSNS発信」である。
たとえば、結婚後も「夫婦の学び」「二人の挑戦」「小さな感謝」を発信することで、
フォロワーがその関係性を“支持”する――つまり、「夫婦がブランドになる」現象だ。
これは単なる情報発信ではなく、「愛の持続を社会的に支える構造」として注目されている。
第Ⅴ部まとめ ──婚活マーケティングが描く新しい「愛の地図」
AIが恋愛の設計図を描き、人間がその中で物語を紡ぐ時代。
地方のコミュニティが再び人々の心を結び、
愛とマーケティングが対立ではなく「共創」へと進む未来。
永島もえと江藤あおいの婚活マーケティングは、もはや単なるビジネスモデルではない。
それは「人が人を求める営みを、社会の希望として再設計する哲学」である。
彼女たちの試みが示すのは、
「愛を戦略的に扱うことで、愛の本質に近づく」
という逆説的な真理だ。
婚活は、孤独を癒し、共同体を再生させ、
そして人間の「つながりたい」という根源的衝動を社会の中心に据え直す。
その未来を描くことこそが、永島もえと江藤あおいが体現する「婚活マーケティング」の到達点である。
終章 「“結婚”を売ることの是非と可能性」
Ⅰ. 「愛」は売られるのか、売られてよいのか
「結婚を“売る”」という言葉は、多くの人に違和感を与える。
なぜなら「愛」や「結婚」は、人間の最も私的で、神聖ですらある領域に属するものだからだ。
その純粋な感情を、価格・広告・販売促進というマーケティングの言語に置き換えるとき、そこには倫理的な軋みが生じる。
永島もえは、こうした批判に対し、冷静に応じている。
「愛を売っているのではありません。
愛が届かない人に、愛が届くように“橋”を架けているのです。」
つまり、彼女にとってマーケティングとは、「人と人を結び直す手段」であり、「感情を媒介する技術」であった。
それは“愛の代理販売”ではなく、“愛の流通設計”なのである。
江藤あおいもまた、心理学的観点から次のように語る。
「愛は、条件を整えなければ芽生えないことがある。
その条件を整える行為――それこそがマーケティングの本質なのです。」
つまり、「結婚を売る」とは、感情を商品に変えることではなく、「出会いの条件」を社会的に整えること。
その行為が誠実であるかどうかは、動機と姿勢にかかっている。
Ⅱ. 結婚相談所という「愛の市場」の現実
結婚相談所は、現代社会の“恋愛市場”の中で、最も人間的で、最も経済的な場所である。
そこではプロフィールが数値化され、条件がリスト化され、出会いがスケジュール管理される。
一見すると冷たい世界だが、その背後には「愛されたい」「理解されたい」という普遍的な欲望がある。
永島もえは、マーケティングの現場で何度もこう語っている。
「数字の背後には、物語がある。
年収や年齢というデータの裏には、その人がどう生きてきたかという人生の時間が流れている。」
この言葉に象徴されるように、婚活マーケティングの目的は「数値で人を選別すること」ではない。
むしろ、データを通して「人間の物語」を読み取る力を社会に取り戻すことなのだ。
そして江藤あおいは、その「物語」を心理学的に補完する。
彼女のセミナーでは、数値化できない「相性」「安心感」「沈黙の呼吸」など、非言語的要素を分析し、
「見えない価値の言語化」を支援している。
婚活マーケティングは、ここでひとつのパラドックスに突き当たる。
——“商品化された出会い”の中で、“非商品的な愛”をどう守るか。
この矛盾を解く鍵こそ、永島と江藤が共に提唱する「愛の構築的理解」である。
愛は天から降ってくるものではなく、互いの努力と工夫で「育てられるもの」だ。
それゆえ、愛の成就に「戦略」や「マーケティング」が介入するのは、必ずしも不純ではない。
むしろそれは、人間の理性が感情を支える、成熟した形の“愛の社会化”と言える。
Ⅲ. 「恋愛の自由」と「結婚の制度」のはざまで
現代人は、自由を愛しすぎた。
恋愛は「自由な選択」とされ、結婚は「個人の幸福追求」とされる。
しかし、その自由は往々にして孤立を生み、選択の多さは迷いを増幅させた。
永島もえは言う。
「現代の婚活市場で苦しんでいる人たちは、“選べる自由”を持っているが、“決める力”を失っている。」
ここにこそ、婚活マーケティングの新たな使命がある。
それは「出会いを増やすこと」ではなく、「決断を導くこと」だ。
江藤あおいは、心理学的にこの現象を「選択過剰による意思の麻痺(choice overload)」と呼び、
婚活の現場では「条件の削除」こそが幸せへの近道だと説く。
彼女はセミナーで参加者にこう問いかける。
「あなたは“どんな人と結婚したいか”ではなく、“誰となら一緒に生きていけるか”を考えていますか?」
この質問は、マーケティングから哲学への転換を促すものだ。
恋愛を「消費」ではなく「共存」に変える視点こそ、婚活マーケティングが次に進むべき方向なのである。
Ⅳ. 「売る」ことの倫理――自己演出と誠実さの間で
婚活の現場では、しばしば「自分をどう見せるか」が重要視される。
だがその“演出”が“偽装”に転じる瞬間、マーケティングは欺瞞に変わる。
永島もえは言う。
「婚活における“誠実な演出”とは、自分を偽らずに魅せること。
嘘ではなく、“より良い自分の可能性”を見せることです。」
たとえば、緊張しやすい人が「明るく振る舞う」のは嘘ではない。
それは「自分の中の社交的な側面を選択的に引き出す行為」であり、
マーケティングの言葉でいえば「ポジショニング戦略」である。
江藤は心理学的観点からこれを「適応的自己呈示」と呼ぶ。
つまり、“本当の自分”とは、固定的な一つの像ではなく、関係性の中で柔軟に変化する存在なのだ。
この理解に立つと、婚活マーケティングにおける「自己演出」は、むしろ人間の社会的成熟の表れとすら言える。
Ⅴ. 「幸福の共有」としてのマーケティング
永島と江藤が目指したのは、「愛を売る」のではなく、「幸福を共有する仕組み」を作ることだった。
婚活の現場では、成功したカップルがイベントに登壇し、体験談を語ることがある。
それは単なるPRではない。
それは「幸福の伝播」そのものである。
人々はそれを見て、「自分にもできるかもしれない」という希望を抱く。
この心理的な伝播効果は、マーケティングでいう「ソーシャル・プルーフ(社会的証明)」だが、
永島と江藤の文脈では、それは「希望の継承」に近い。
つまり、婚活とは“幸福を再生産する文化”になりつつある。
彼女たちのマーケティングは、愛を商品に変えるのではなく、愛を「語り合う社会的物語」へと変換する。
それは広告ではなく、文化の再構築であり、愛を社会の言語に戻す営みなのである。
Ⅵ. 「愛と資本主義」――美しくも危うい結婚の未来
私たちが生きるこの時代、恋愛も結婚も、資本主義の網の中にある。
SNSで映えるデート、フォロワーを増やすカップルアカウント、
ウェディング写真のブランド化――すべてが「愛の消費」を加速させる。
永島はそれを「愛のブランド化」と呼び、こう述べている。
「消費される愛の中に、“永続する関係”をどう築くか。
その矛盾の中でこそ、私たちは本当の愛を学ぶのです。」
江藤も同調する。
「資本主義の中で愛を語ることは、危険であると同時に希望でもある。
愛が“売られる”ならば、それだけ多くの人が“愛を求めている”証拠なのです。」
この二人の視点は、マーケティングの倫理を超えて「愛の経済学」へと踏み込んでいる。
彼女たちは決して愛を消費に委ねようとしたのではない。
むしろ、「愛という価値を市場の言語で語ること」によって、
人間が再び“愛を考える機会”を取り戻すことを目指したのだ。
Ⅶ. 結びにかえて――「結婚」という物語を売るということ
「結婚を売る」――その言葉に潜む挑発的な響きは、永島もえと江藤あおいの時代を象徴している。
だが、彼女たちが売っているのは“制度としての結婚”ではなく、“物語としての結婚”である。
彼女たちは、人々にこう語りかける。
「あなたが誰かと生きるという選択は、社会に新しい物語を加えること。
その物語こそが、未来の誰かの希望になるのです。」
愛とは、交換ではなく継承である。
マーケティングとは、売ることではなく伝えること。
そして、結婚とは、二人の間に生まれた“物語”を社会へ贈り返す行為である。
その意味で、永島もえと江藤あおいの「婚活マーケティング」とは、
“愛の資本主義化”ではなく、“愛の文化再生”の試みだった。
彼女たちの手によって、「結婚」という言葉は再び輝きを取り戻す。
それは、かつてのように形式的なゴールではなく、
現代社会における“希望のプロジェクト”として再構築されつつあるのだ。
■ 終章まとめ
-
「結婚を売る」とは、愛を商品化することではなく、愛を“届ける仕組み”を作ることである。
-
婚活マーケティングの目的は、「出会いの拡張」から「関係の継続」へと進化している。
-
マーケティングは倫理と結びつくとき、単なる商業活動を超えて“文化的装置”となる。
-
永島もえと江藤あおいの思想は、「愛と市場」「感情と戦略」という二項対立を超えた場所で、新しい愛の哲学を提示した。
🌸 結びの一節
愛は贈与であり、結婚は社会への贈り物である。
もし“結婚”を売ることが許されるなら、それは「誰かを幸せにしたい」という願いを
もう一人の誰かに手渡す行為である。
そしてその連鎖の中で、愛は――決して枯れない市場となる。