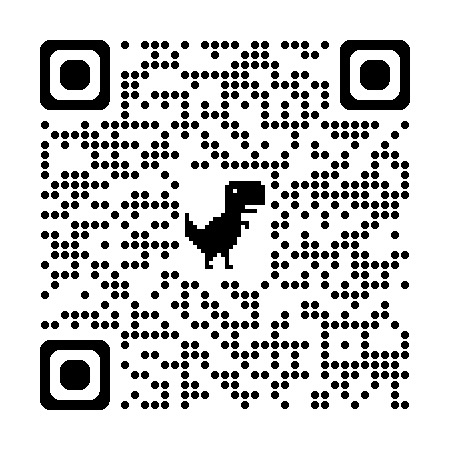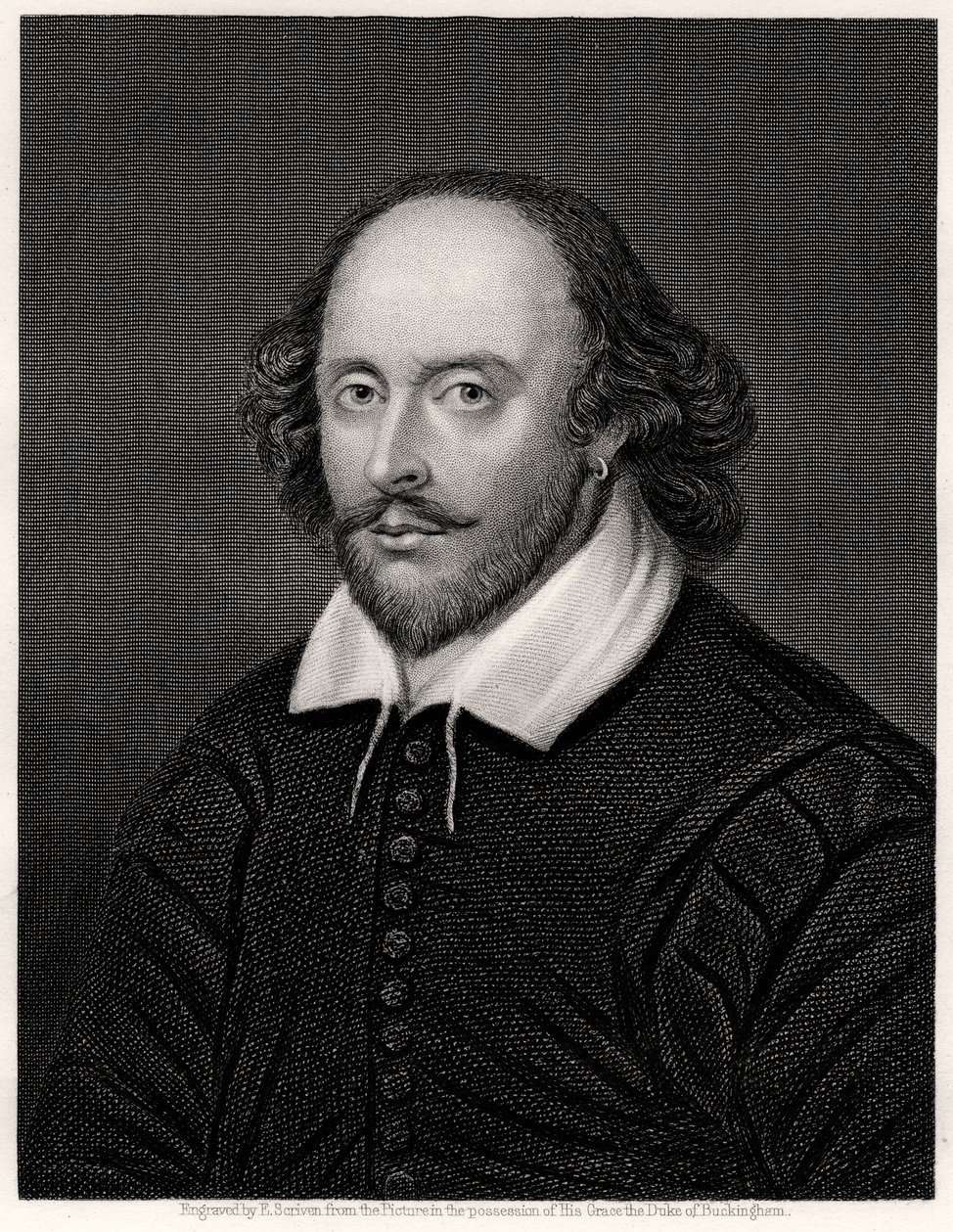序章 「お見合いに愛はあるか」という問いの意味
1. 問いの背景
「お見合いに愛はあるか」。この問いは単純なようでいて、実は人間存在の根源に触れる深い問題をはらんでいる。結婚という営みをめぐって、私たちは常に「愛」と「制度」、「感情」と「社会的役割」の狭間に立たされてきた。愛とは自由で自発的な心の動きである。しかし、お見合いとは制度化された出会いの形態であり、条件や計算、社会的規範に基づいた合理的な選択が介在する。その二つが重なり合う地点に、果たして「真の愛」が存在しうるのかという問題が立ち上がるのである。
加藤諦三教授は、人生論や恋愛論において繰り返し「人はしばしば自己の不安や孤独を隠すために結婚を利用する」と語ってきた。つまり、多くの人にとって結婚は「愛の表現」であると同時に「不安解消の手段」であり、時には「依存の制度化」に過ぎない場合もある。お見合いという形式は、その構造をより鮮明に浮き彫りにする。
2. お見合いと愛のジレンマ
お見合い結婚は「条件の一致」を前提にしている。学歴、職業、収入、家柄といった外的条件が合致すれば、両者は「結婚に適した相手」とされる。だがここで生じるのは次のようなジレンマである。
愛とは本来、相手の存在そのものへの深い肯定である。
しかしお見合いは、相手を「条件の集合体」として評価する。
この二重性は、人間が「社会的存在」と「感情的存在」の両面を持つことの象徴でもある。条件に惹かれて出会った相手に対して、時間と共に本物の愛情が芽生えることもある。しかし逆に、条件のために結びついた関係が、愛の不在によって空虚さに蝕まれることもある。
3. 加藤諦三が見る「愛の不在」
加藤教授は、人間が「愛されたい」という承認欲求に支配されるとき、真の愛は成立しないと指摘する。愛とは「相手を支配しないこと」であり、相手に対する無条件の承認である。しかし、お見合いの場に臨む人々はしばしば次のような心理状態にある。
親や世間の期待に応えるために結婚する
孤独や不安を埋めるために結婚する
自分の価値を証明するために結婚する
このような動機に基づく結婚は、たとえ形の上では成立しても、愛が育たない可能性が高い。教授は「結婚は愛の逃げ場ではない」と繰り返し述べてきた。お見合いはその逃避傾向を制度化しているがゆえに、愛の不在をより鋭く露呈する場でもあるのだ。
4. お見合いに愛が芽生える可能性
とはいえ、「お見合いに愛はない」と断定することは短絡である。加藤教授自身も、人間は関わり合いの中で学び、成長し、愛を育てていく存在であると強調する。愛は出会いの瞬間に完全な形で存在するのではなく、むしろ「ともに歩む過程」で育まれるものだ。
例えば、ある女性は両親に勧められて半ば消極的にお見合いをした。最初は相手に対して特別な感情はなかったが、日々の会話や共通の趣味を通じて、相手の人柄に安心感を覚えるようになった。やがてその関係は「条件の一致」から「存在の肯定」へと変わり、結果として強固な愛情に育っていった。
加藤教授の視点から見れば、こうした事例は「条件の場をきっかけにしても、真実の愛を学ぶことは可能である」ことを示している。つまり、お見合いという制度は必ずしも愛を阻むものではなく、愛を学ぶ舞台ともなりうる。
5. この問いが現代に持つ意味
現代日本では恋愛結婚が一般化し、お見合いという形式は衰退したかに見える。しかし、婚活アプリや結婚相談所といった新しい仕組みが台頭している現在、それらは「現代版のお見合い」と言い換えることもできる。条件検索やプロフィールマッチングは、まさにお見合い的発想をデジタル化したものだからだ。
したがって、「お見合いに愛はあるか」という問いは、現代においても決して古びていない。むしろ「マッチングシステムと愛の両立は可能か」という形で、ますます重要な意味を帯びている。
6. 本論の展望
本稿では、この序章を導入として、以下の点を掘り下げていく予定である。
加藤諦三が定義する「愛」と「愛の不在」
お見合い制度の社会的・心理的構造
お見合いにおける条件と感情の相克
具体的事例・逐語的エピソードから見るお見合いの実態
お見合いから始まる愛が持つ可能性と限界
現代婚活における「お見合い的要素」とその心理的課題
こうして、「お見合いに愛はあるか」という問いは、単なる結婚の是非を問うものではなく、人間がどのようにして「愛の学び」に至るかを考察する重要な契機となる。
第Ⅰ部 愛の心理学的基盤 — 加藤諦三の視点から
1. 愛とは何か
加藤諦三教授の著作に一貫して流れるメッセージは、「愛とは自立した人間だけが持ちうる能力である」という認識である。愛は感情の高まりや情熱的な衝動ではなく、むしろ相手を「そのまま受け入れる姿勢」であり、「相手を自分の不安や孤独を埋める道具にしない態度」である。
愛は欲望や依存とは区別されるべきものであり、教授は次のように強調する。
愛は「相手を通して自分を満たそうとすること」ではない。
愛は「相手を存在のままに認めること」である。
愛は「孤独に耐えうる人間が初めて可能にする自由な関係」である。
この定義を踏まえたとき、お見合いにおける「条件」「計算」「世間体」に基づいた結婚は、果たして愛を育てる土壌になりうるのかという問いがより鮮明に立ち上がる。
2. 承認欲求と愛の混同
教授がしばしば指摘するのは、人間が「愛されたい」という欲求を「愛すること」と混同してしまう心理である。承認欲求は人間の根源的欲求であり、それ自体が悪ではない。しかし、それを愛と誤解したとき、関係は歪んでいく。
例えば、お見合いの席で「この人と結婚すれば親も喜ぶし、世間に認められる」という気持ちが先に立つと、それは「承認欲求の充足」であって「愛」ではない。愛とは「他者を自由にさせる力」であるのに対し、承認欲求に基づく結婚は「他者を自分の評価のために利用すること」である。
この錯誤は、加藤教授が繰り返し述べる「愛の不在の心理的サイン」であり、お見合いにおいて特に顕著に見られる。
3. 不安と依存の構造
加藤教授は、人間が結婚を急ぐとき、その背後にはしばしば「不安」や「孤独」が隠れていると語る。特にお見合いは、家族や社会の圧力の下で行われることが多いため、不安と依存の心理が強調されやすい。
事例A:30代後半の女性
ある女性は30代後半に差しかかり、両親から「そろそろ結婚を考えるべきだ」と繰り返し促され、お見合いを決意した。彼女は相手に対して「嫌ではない」という程度の感情しか持っていなかったが、「このまま独身でいるよりは」と妥協的に婚約した。しかし結婚後、夫に強い依存を示し、夫が残業や出張で不在になると過剰に不安定になった。
このケースは「結婚によって孤独から逃れようとする依存型の選択」であり、加藤教授の視点からすれば「愛ではなく不安の延長」に過ぎない。
4. 自立と愛
では、愛はどのようにして可能になるのか。加藤教授は「孤独に耐える力を持った人間だけが他者を本当に愛することができる」と述べる。孤独に耐えるとは、「自分の存在を自分で引き受ける」ことを意味する。
自立した人間は、結婚を「自分の不足を埋める手段」とは考えない。むしろ「共に成長するパートナーシップ」として捉える。そのとき、相手は「孤独の恐怖から逃れるための対象」ではなく、「存在そのものを喜び合える仲間」となる。
事例B:自立を経たカップル
ある男性は、過去に依存的な恋愛を繰り返し、相手を束縛しては破綻させてきた。心理カウンセリングを受け、自分が「愛されることでしか価値を見出せない」という承認欲求に囚われていたことに気づいた。彼は時間をかけて「自分は自分のままで価値がある」と受け入れる作業を続けた。その後、結婚相談所を通じて出会った女性と、最初は条件的なマッチングで始まった関係を、徐々に「相手の自由を喜ぶ愛」へと育てることができた。
この例は、お見合いという枠組みの中でも「自立」が伴えば愛が可能になることを示している。
5. 「愛」と「愛の不在」の指標
加藤教授は「愛の有無を測る指標」としていくつかの心理的特徴を挙げている。
愛がある場合
相手を支配しない
相手の欠点を受け入れる
自分の孤独に耐えられる
相手の成長を喜べる
愛がない場合
相手を利用しようとする
相手に過剰な期待を押しつける
相手が不在になると不安で耐えられない
結婚を「自分の価値証明」に使う
お見合いの現場では、この「愛の不在」の特徴がしばしば観察される。条件を満たす相手に「あなたしかいない」と依存し、相手が自由に振る舞うことを恐れる心理である。
6. 愛は「学ぶもの」
重要なのは、加藤教授が「愛は学ぶもの」であると強調している点である。人は誰しも、幼少期の愛情体験や家庭環境によって「愛の能力」に差が生じる。愛の不在を経験して育った人は、他者に過度に依存しやすくなる。しかし、それは変えられない宿命ではない。
愛することを学び直す過程には、以下のような要素が含まれる。
自分の孤独と向き合う勇気
自分の価値を承認する習慣
他者を条件抜きで受け入れる実践
相手を「自分を埋める存在」ではなく「共に生きる存在」と見る視点
この「学び」があれば、お見合いという条件的な出会いも、愛を育む場に変わりうる。
7. お見合いにおける心理的基盤の整理
まとめると、加藤諦三教授の視点から「愛の心理学的基盤」を整理すると次のようになる。
愛は自立に基づく
承認欲求や依存からは真の愛は生まれない
お見合いは条件重視ゆえに「愛の不在」を生みやすい
しかし自立を経た者にとっては、愛を学ぶ場ともなりうる
8. 次章への接続
本部では「愛の心理学的基盤」を示した。次の第Ⅱ部では、この愛の定義を踏まえて、日本社会におけるお見合い制度の歴史的背景を整理し、なぜ「愛の不在」が制度的に繰り返されてきたのかを社会的文脈から考察する。
第Ⅱ部 お見合い制度の歴史と日本的文脈
1. お見合いの成立と文化的背景
日本における「お見合い」は、近世から近代にかけて制度化されてきた結婚慣習の一形態である。江戸時代には武士階級を中心に「家」と「家」の結びつきを目的とした縁組が一般化しており、そこでは恋愛感情は二の次であった。結婚はあくまで「家の存続」と「社会的地位の安定」を保障する装置であり、個人の感情よりも共同体の秩序が優先されたのである。
加藤諦三教授の視点からすれば、この歴史的事実は「人間が自分の存在を自分で支えられなかった時代」の象徴でもある。つまり、人は家という枠組みに依存し、愛という個人の感情を犠牲にしてでも「社会に受け入れられること」を優先した。これはまさに「承認欲求」が社会制度として組み込まれた形だと言える。
2. 明治・大正期におけるお見合いの拡大
明治期に入ると、近代化の波の中で「家制度」が強化され、お見合いはさらに広く浸透していった。特に上流階級や中産階級においては、家柄・学歴・職業を重視する縁組が多く見られた。ここで特徴的なのは、「愛」という概念がまだ十分に結婚の動機とはなり得なかった点である。
大正期には「自由恋愛」を唱える知識人や文学者が現れ、恋愛と結婚を結びつける言説が生まれたが、それはむしろ例外的な思想であった。多くの庶民にとって、結婚は依然として「安定のための制度」であり、お見合いはその典型的な仕組みであった。
教授の視点から見れば、この時代の人々は「愛する力」よりも「不安から逃れるための制度」を優先していた。つまり、結婚相手は「心を通わせる対象」ではなく「安心を保障する存在」として求められていたのである。
3. 戦後の高度経済成長とお見合いの黄金期
戦後日本においては、家制度が形式的には廃止されたものの、お見合いはなお盛んに行われた。特に高度経済成長期には「安定した職業」「収入のある男性」と「家庭的な女性」という典型的な組み合わせが理想とされ、多くの結婚が仲人による紹介で実現した。
この時期のお見合いは「社会的な成功」と「個人の幸福」が重なり合った瞬間でもあった。安定した結婚は「人生の成功」を意味し、親も世間もそれを強く後押ししたのである。
しかし加藤教授の観点からすれば、ここにも「愛の不在」が潜んでいる。結婚は「社会的安定を得るための手段」として強調され、個々人が「愛する力」を育む場としては十分に機能していなかった。表面的には幸福であっても、内心では「相手を通して自己を証明する」依存的心理が強く作用していたのである。
4. 恋愛結婚の台頭とお見合いの衰退
1970年代以降、恋愛結婚が徐々に一般化する。高度経済成長によって人々の生活が安定し、個人主義的価値観が広がる中で、「結婚に愛を求める」という考え方が定着していった。統計的にも1970年代後半には恋愛結婚が過半数を超え、お見合い結婚は減少していった。
ここで興味深いのは、多くの人が「お見合いには愛がない」「恋愛結婚こそ愛のある結婚だ」と考えるようになった点である。しかし加藤教授の視点からすれば、この単純な二分法には落とし穴がある。なぜなら、恋愛結婚においても「孤独からの逃避」「承認欲求の投影」が動機となることが多く、必ずしも「愛」が基盤となっているとは限らないからである。
つまり、「お見合い=愛の不在」「恋愛結婚=愛の充足」という図式は幻想に過ぎず、むしろ両者に共通する問題は「愛の基盤となる自立の欠如」にあるのだ。
5. 現代におけるお見合いの変容
21世紀に入ると、結婚相談所や婚活パーティー、さらにはマッチングアプリが普及し、「現代版お見合い」とも言える状況が広がっている。これらの仕組みでは、従来のお見合いのように「親や仲人の紹介」に代わって「アルゴリズムによる条件マッチング」が前面に出てきた。
一見すると、これは「個人の自由な選択」に基づいているように見える。しかし、その実態はやはり「条件の一致」による合理的なマッチングであり、構造的には従来のお見合いと大きく変わらない。
加藤教授の視点からすれば、ここにこそ「現代的な愛の不在」がある。恋愛アプリのプロフィールは「自分をよく見せるための仮面」であり、その裏には「本当の自分を受け入れられない不安」が潜んでいる。つまり、現代の婚活市場は「承認欲求と不安」を制度化する新しい装置になっているのだ。
6. お見合い文化が示す日本的心理
お見合いの歴史を振り返ると、日本社会における人間関係のあり方が浮かび上がる。
共同体の安定を優先する傾向
個人の感情よりも社会的承認を重視する価値観
孤独や不安を制度で埋めようとする心理
これらは加藤教授が批判的に捉える「愛の不在の心理」と深く結びついている。つまり、日本においてお見合いが長く機能してきたのは、人々が「愛よりも承認と安定を優先してきた」ことの表れなのである。
7. 歴史的文脈から見た「お見合いに愛はあるか」
以上を踏まえると、「お見合いに愛はあるか」という問いは単に結婚制度の違いを問うのではなく、日本人の心理的・文化的基盤そのものを問うことになる。
お見合いは愛を阻む制度であったのか
あるいは愛を学ぶ一つの場であったのか
加藤教授の立場からすれば、その答えは「人間がどれだけ自立しているか」にかかっている。お見合いという形式そのものが愛を否定するのではなく、その場に臨む人間の心の在り方が「愛の有無」を決定するのだ。
8. 次章への接続
第Ⅱ部ではお見合い制度の歴史的背景と日本的文脈を整理した。次の第Ⅲ部では、この歴史の上に築かれた「お見合いにおける愛の不在」の構造を心理学的に掘り下げ、具体的にどのような心の働きが愛を妨げているのかを検討していく。
第Ⅲ部 お見合いにおける「愛の不在」とは何か
1. 「愛の不在」という概念
加藤諦三教授は、著作の中で繰り返し「愛と依存はまったく異なる」と強調している。愛とは自立した人間が他者を無条件に受け入れる力であるのに対し、依存とは自らの不安や孤独を相手で埋めようとする行為である。愛の不在とは、関係の表層には「一緒にいる」形があっても、実際には 不安の投影・承認欲求の充足・自己防衛 が中心となっている状態を指す。
お見合いにおける「愛の不在」は、この依存的心理構造が制度的に強化されやすい点にある。条件・世間体・家族の期待が前面に出ることで、当人同士の感情や相互承認が後景に退き、関係が「社会的契約」としてのみ成り立ってしまうのである。
2. お見合いに潜む典型的な心理的パターン
(1) 世間体の優先
「周囲が安心するから結婚する」「親の顔を立てるために結婚する」。
この動機に基づいた結婚は、外的承認を軸にしているため、相手の存在そのものを喜ぶ愛には結びつきにくい。
(2) 条件への過剰依存
「相手は安定した職業だから」「年齢的に丁度よいから」。
条件的に「損をしない」選択は、裏を返せば「愛を感じていなくても結婚を選べる」という冷却的構造を内包している。
(3) 孤独からの逃避
「一人でいるのは寂しいから誰かと結婚したい」。
これは加藤教授の言葉を借りれば「愛ではなく、不安の逃げ道としての結婚」である。
(4) 自己価値の補強
「結婚できれば、自分が社会的に認められる」。
このような動機は、相手を「自分の証明道具」として利用しているに過ぎない。
3. 具体的エピソード
事例A:条件で選んだ結婚
40歳手前で焦りを感じた男性が、親の勧めでお見合いをした。相手は安定した家庭の出で、性格も穏やかだった。男性は「悪くはない」と判断し、半年後には結婚。しかし結婚生活の中で、会話が深まらず、相手を「自分の孤独を和らげる人」としてしか見られないことに気づく。次第に苛立ちが募り、夫婦の間に冷たい空気が流れた。
→ 加藤教授の視点では、これは「条件に基づいた関係」であり、相互承認が欠如した典型的な愛の不在の例である。
事例B:親の期待に応えた結婚
女性は20代後半で、親から「そろそろ縁談をまとめないと」と繰り返し迫られた。気が進まぬままお見合いを受け入れ、相手は社会的に申し分ない男性であった。結婚後、彼女は「親を安心させられた」という安堵を感じたが、夫との心の距離は縮まらなかった。やがて「自分は誰のために生きているのか」という虚無感に襲われ、抑うつ状態に陥った。
→ 教授の分析では、これは「愛されたい欲求に支配された結婚」であり、自立の欠如によって心が空洞化した例である。
4. 加藤諦三が示す「愛の不在」のサイン
加藤教授は、人が「愛している」と言いながら実際には「愛の不在」に陥っているとき、以下のような特徴が現れると述べている。
相手が不在だと強い不安に襲われる
相手に「自分を幸せにしてほしい」と要求する
相手の自由を恐れ、束縛しようとする
相手を条件で選び、その条件が崩れると失望する
結婚を「自分の価値証明」として利用する
お見合いという制度は、これらのサインを生じやすい環境を提供する。なぜなら「条件を満たしているから結婚する」という前提そのものが、相手の存在を無条件に受け入れる愛の態度とは逆行しているからである。
5. お見合いの場が映し出す人間の不安
お見合いは、単なる出会いの形式ではなく、人間の深層心理を映し出す鏡である。お見合いを通して浮かび上がるのは、次のような人間的欲望である。
「世間から取り残される不安」
「孤独を抱えたまま年齢を重ねる恐怖」
「親の期待を裏切る罪悪感」
「結婚しなければ自分には価値がないという思い込み」
これらはすべて「愛」ではなく「不安」や「承認欲求」に根差した動機である。教授の言葉を借りれば、それは「愛の仮面をかぶった不安」であり、結婚の形をとりながらも愛はそこに存在していない。
6. 「愛の不在」が生む結婚の行き詰まり
お見合いにおける愛の不在は、結婚生活の行き詰まりとして顕在化する。
互いを「条件」でしか見ていないため、生活が日常化すると感情が空白になる
相手に「幸せにしてほしい」と期待しすぎるため、失望が大きくなる
孤独を埋めるために結婚したのに、孤独がさらに深まる
相手の自由を恐れて束縛し、関係が窒息する
教授はこれを「愛の不在が生む悪循環」と呼び、その根本には「自分自身を受け入れられない不安」があると分析している。
7. それでも愛は学びうる
ただし、加藤教授は決して悲観的ではない。彼は「愛は学ぶことができる」と何度も述べている。お見合いにおいても、最初は条件や不安に基づいて始まった関係が、相互承認を通じて愛に変わっていく例もある。
重要なのは、
自分の孤独と向き合う勇気を持つこと
相手を「自分を埋める道具」ではなく「一人の存在」として受け入れること
承認欲求を超えて「相手の自由を喜ぶこと」を学ぶこと
この姿勢があれば、たとえ愛の不在から始まった関係でも、やがて愛を育む土壌に変えることができる。
8. 第Ⅲ部のまとめ
「お見合いにおける愛の不在」とは、制度そのものに内在するのではなく、そこに臨む人間の心理的基盤に由来する。
承認欲求に支配された結婚
不安からの逃避としての結婚
条件による合理的選択に偏った結婚
これらはいずれも「愛」ではなく「不安の制度化」に過ぎない。
しかし同時に、お見合いという場は「愛を学び直す場」ともなりうる。愛の不在を直視し、自分の不安と向き合うとき、人は初めて「相手を無条件に承認する愛」に近づけるのである。
9. 次章への接続
第Ⅲ部では「お見合いにおける愛の不在」を心理学的に分析した。
次の第Ⅳ部では、この「条件と計算の心理」をさらに掘り下げ、なぜ人は条件を拠り所にするのか、そしてそれがどのように依存と不安の連鎖を生むのかを具体的に考察する。
第Ⅳ部 条件と計算の心理 — 依存と不安の投影
1. 条件と計算に基づく結婚の心理的構造
お見合いにおいて、当事者やその家族が最も重視するのは「条件」である。職業、年収、学歴、家柄、年齢、容姿、健康状態——これらの条件は合理的判断としては理解できる。しかし、心理学的に見ると、その背後には人間の「不安」と「依存」が色濃く投影されている。
加藤諦三教授は、人間が「条件」で相手を選ぶとき、その心理はしばしば「愛の欠如を合理性で覆い隠している」に過ぎないと指摘する。つまり「愛しているから結婚する」のではなく、「安心できる条件があるから結婚する」という選択は、愛を回避しながらも「安定」を確保しようとする防衛的行動なのである。
2. 不安を条件で補う心のメカニズム
人間は本質的に孤独と不安を抱えて生きている。その不安を直視せず、条件という外部の指標に依存することで「私は安心してよい」と自分に言い聞かせようとする。
経済的不安 → 高収入の相手を条件にする
老いと孤独への恐怖 → 年齢が近く安定した家庭像を持つ相手を求める
社会的評価への欲求 → 学歴や家柄にこだわる
これは、条件を通じて「私は間違っていない」「私は選ばれるに値する」という承認を獲得しようとする心理である。だが、このような依存は不安を根本的に解消するわけではなく、むしろ「条件が崩れたときに一層強い不安」に襲われる危うさを孕んでいる。
3. 計算の心理と「損得勘定」
お見合いの場ではしばしば「損をしない結婚をしたい」という発想が働く。これは恋愛結婚よりも顕著である。
「この相手なら親も満足する」
「経済的に困らない」
「条件的に他の候補より有利だ」
こうした計算は、一見すると合理的で堅実である。しかし加藤教授の分析では、これは「愛を持たない人間の防衛的戦略」に過ぎない。なぜなら愛のある人間は「損得」ではなく「共に生きたい」という存在そのものへの欲求で相手を選ぶからである。
損得で相手を選んだ結婚は、後に必ず「もっと良い条件があったのではないか」という比較と不満を呼び込み、夫婦関係に不安を植え付ける。
4. 具体的エピソード
事例A:条件を最優先した結果
30代半ばの男性は、安定した公務員の女性との縁談を進めた。彼は「結婚後の生活が安心できる」という計算で結婚を決断した。しかし数年後、彼は「妻に心を開けない」「一緒にいても孤独だ」と感じるようになり、不倫に走った。
→ 教授の視点からすれば、この結婚は「不安を条件で覆い隠した」典型であり、愛の不在が時間と共に露呈した例である。
事例B:条件崩壊による不安の爆発
ある女性は「年収の高い相手なら幸せになれる」と考え、エリート商社マンと結婚した。しかし結婚後、夫が転職で収入が下がると、彼女は強い不安と苛立ちに襲われた。彼女の結婚動機は「経済的条件への依存」であり、それが崩れると夫婦関係そのものが揺らいだ。
5. 条件依存の根底にある「承認欲求」
加藤教授が繰り返し強調するのは、条件にこだわる心理の背後には「他人から認められたい」という強い承認欲求が潜んでいることである。
「いい条件の相手と結婚すれば、私は周囲から認められる」
「社会的に体裁を保てる」
「親に安心してもらえる」
しかし承認欲求に支配された結婚は、自分自身の幸福ではなく「他者のまなざし」を基準にしているため、愛を育む基盤を欠いている。教授の言葉を借りれば、それは「他人の人生を生きる」ことであり、自己喪失の始まりである。
6. 不安の投影としての結婚
お見合いは、実は人間が自分の不安を相手に投影する場でもある。
経済的不安 → 「収入が高い人なら安心」
孤独不安 → 「誰でもいいから結婚すれば孤独から逃れられる」
社会的劣等感 → 「条件のよい相手と結婚して自分の価値を高めたい」
これは一見「相手を選んでいる」ようで、実は「自分の不安を処理している」に過ぎない。つまり、相手は「愛すべき存在」ではなく「自分の不安を押し付ける対象」と化してしまう。
7. 計算を超える愛への転換
それでは条件や計算を重視せずに結婚することが現実的なのかといえば、そう単純ではない。人間は社会的存在である以上、条件を完全に無視することはできない。しかし重要なのは、条件を「補助的な要素」にとどめ、最終的な基盤を「愛」に置けるかどうかである。
加藤教授は、「愛のある人間は、条件を持ち出す必要がない」と述べる。なぜなら、愛する力を持つ人は相手を存在そのもので受け入れ、条件を超えた信頼を築けるからである。
事例C:条件を超えた成婚
ある男性は婚活を通じて、年齢差や経済状況など「条件的には不利」とされる女性と出会った。周囲は反対したが、彼は「一緒にいると心が安らぐ」という感覚を大切にし、結婚を選んだ。結果として二人は困難を乗り越え、強い絆を築いた。
→ これは条件の計算を超えて「存在の承認」に基づいた愛の例であり、教授の理論における「愛の可能性」を体現している。
8. 第Ⅳ部のまとめ
お見合いにおける条件と計算は、表面的には合理的だが、その根底には「不安」と「依存」が潜んでいる。
条件依存は不安を覆い隠す防衛
計算は愛の不在を合理性で正当化する行為
不安を相手に投影することは愛を阻む最大の要因
しかし、人が自立し「孤独に耐える力」を身につけたとき、条件や計算を超えて相手を存在そのもので受け入れることができる。そこに初めて「愛」が成立するのである。
9. 次章への接続
第Ⅳ部では「条件と計算の心理」を依存と不安の観点から分析した。
次の第Ⅴ部では、さらに実際のお見合い現場における具体的なエピソードや逐語記録を提示し、条件と不安がどのように表出するのかをリアルに描き出していく。
第Ⅴ部 お見合い現場の具体的エピソードと逐語記録
1. お見合い現場の特有の緊張感
お見合いは単なる「出会い」ではない。そこには両親や仲人の期待、条件を意識する視線、世間体への配慮が重なり、特有の緊張感が生まれる。そのため、当人たちが交わす会話には「愛を育む自由さ」よりも「失敗してはならない」という強迫が漂う。
加藤諦三教授が指摘する「不安と承認欲求の投影」は、こうした場面で如実に現れる。本人たちは「愛を探している」と口にしても、実際には「条件を満たした結婚に逃げ込もうとしている」のだ。
2. 逐語記録①:条件を意識する会話
場面:30代前半の男性(会社員)と20代後半の女性(事務職)のお見合い。仲人が同席。
仲人:「お二人とも落ち着いた方で、きっとお似合いだと思いますよ」
男性:「ええ…僕の仕事は安定しているので、生活の心配はないと思います」
女性:「それは安心ですね。私も結婚したら家庭を大事にしたいと考えています」
仲人:「お互いの希望が合いそうですね」
男性:「……年齢的にも、そろそろ結婚を決めたいと思っていまして」
女性:「私もです」
分析:
この会話には「安心」「安定」「条件」といった言葉が中心にあり、「相手への個人的な関心」が乏しい。教授の視点では、これは「不安の投影」としての会話であり、「私は孤独になりたくない」「社会的に遅れたくない」という心理が裏にある。愛が芽生える余地は、現時点ではほとんど見られない。
3. 逐語記録②:親の期待が前面に出る場面
場面:20代後半の女性と30代前半の男性。女性の母親が強く縁談を勧め、半ば強引に設定されたお見合い。
男性:「今日はお母様からお話をいただきまして」
女性:「……はい。母がどうしてもと言うので」
男性:「ご両親が安心されるのは大事なことですね」
女性:「でも、正直に言うと、まだ結婚に気持ちが追いついていません」
男性:「そうですか……」
分析:
女性は「母のため」という承認欲求に基づいて場に臨んでいる。自分の意志や感情よりも「親を安心させたい」という欲求が優先されており、これは愛ではなく依存の構造である。教授の言葉を借りれば「自分を生きていない」状態であり、この結婚が成立しても心の空洞感に苦しむ可能性が高い。
4. 逐語記録③:孤独からの逃避としてのお見合い
場面:40代男性と30代後半女性。長年独身で過ごしてきた孤独感から、お互いに焦りを感じている。
男性:「一人で食事をするのも、そろそろ辛くなってきまして……」
女性:「わかります。休日に一人でいると、不安になりますよね」
男性:「ですから、もう条件はあまり気にしていません。とにかく結婚したい」
女性:「私もです。普通の家庭が欲しい、それだけです」
分析:
この会話は「相手への関心」ではなく「孤独から逃れたい」という気持ちの共鳴に過ぎない。教授の視点からは「孤独を受け入れられない人間は愛することができない」。つまり、これは愛の対話ではなく、不安同士の取引のような会話である。
5. カウンセリング場面の逐語記録(再現)
加藤教授がもしカウンセリングの場でこうした相談を受けたとしたら、次のような対話が想定される。
女性(相談者):「お見合いで会った方と結婚を考えています。条件も良いし、親も賛成しています」
加藤教授:「あなたはその人と一緒にいるとき、心が安らぎますか?」
女性:「……正直、安心はします。でも、特別な感情はありません」
加藤教授:「安心と安らぎは違います。条件で得られるのは安心です。しかし愛があるとき、人は相手といるだけで安らぎを感じるのです」
女性:「安らぎ……それは、まだわかりません」
加藤教授:「それを見極めずに結婚すると、条件は残っても、心は空虚なままになりますよ」
分析:
教授は「条件による安心」と「愛による安らぎ」を明確に区別する。お見合い現場で多くの人が感じているのは前者であり、それを愛と誤解することが「愛の不在」を生む。
6. お見合いの裏にある「沈黙」
逐語記録で浮かび上がるのは、会話の隙間にある「沈黙」の重さである。
相手の発言に対して「どう答えるのが正解か」を考える沈黙
条件を意識しながら「本音を隠す」沈黙
親や世間の視線を背負って「自分を抑える」沈黙
教授は、こうした沈黙を「愛を語る自由の欠如」として捉える。人は愛する力を持つとき、沈黙は温かさを伴うが、不安に支配された沈黙は冷たさと重さしか残さない。
7. 愛の不在を突破する瞬間
しかし、逐語記録の中には「条件」を超えて相手の人間性に触れる瞬間がある。
場面:婚活相談所で出会った二人。初対面の緊張の中で。
男性:「実は、趣味で陶芸をしていて。土に触れていると落ち着くんです」
女性:「あ、私も絵を描くのが好きなんです。作る時間って、自分に戻れる感じがしますよね」
男性:「そうですね。自分を受け入れられる瞬間というか」
女性:「なんだか、共感できます」
分析:
ここでは条件ではなく「自己表現と安心感」という内面的な経験を共有している。教授の言葉で言えば「相手を条件ではなく存在として認める」瞬間であり、愛が芽生える可能性が開かれる。
8. 第Ⅴ部のまとめ
逐語記録を通じて見えてきたことは次の通りである。
多くのお見合いの会話は「条件」「安心」「親の期待」といった外的要素に支配され、愛の不在を露呈する。
会話の沈黙やぎこちなさは「不安と承認欲求の影」を映し出す。
しかし、条件を超えて「存在を共有する瞬間」が訪れると、愛の可能性が芽生える。
加藤諦三教授の視点からすれば、愛の不在は制度そのものに起因するのではなく、「条件や不安に支配された人間の心」に由来する。そして、その不在を突破するのは「条件を超えた存在承認」である。
9. 次章への接続
第Ⅴ部では、お見合い現場のエピソードと逐語記録を通じて「愛の不在」がどのように表れるかを具体的に示した。
次の第Ⅵ部では、「お見合いから始まる愛は育つのか」という問いに焦点を当て、条件や不安に基づいた出会いが愛に転換する可能性と、そのために必要な心理的要件を考察していく。
第Ⅵ部 お見合いから始まる愛は育つのか
1. 「出会い」と「愛」の非連続性
加藤諦三教授は、人間の関係性について「愛は最初から完成した形で存在するものではなく、育てられるものである」と繰り返し強調している。
恋愛結婚がしばしば「出会った瞬間のときめき」から始まるのに対し、お見合いは「条件の一致」という冷静なスタート地点から出発する。そのため、「お見合いから本当に愛が育つのか」という問いは常に突きつけられてきた。
ここで重要なのは、愛は出会いの形式よりも「人間の成熟度」によって決まるという点である。成熟した人間は、たとえ条件から始まった関係でも、相手を存在そのものとして受け入れ、愛を育むことができる。一方、自立できていない人間は、恋愛結婚であれお見合いであれ、愛を維持することができない。
2. 愛が育つための心理的条件
お見合いから愛が育つかどうかは、次の3つの心理的条件にかかっている。
孤独に耐える力
「一人で生きられる人間」だけが「誰かと共に生きること」を選べる。
孤独を恐れて結婚する人は、相手を愛するのではなく「依存する」。
承認欲求を超える姿勢
「結婚によって親や世間に認められる」ことを目的にする限り、愛は芽生えない。
承認欲求を超えて「相手の存在を喜ぶ」ことが必要である。
相手の自由を尊重する力
愛とは「相手を支配しない」ことである。
相手を自分の所有物とせず、自由を喜ぶ関係性の中でのみ愛は成長する。
教授の理論に照らせば、これらの条件を満たす人間関係は、出会いの形態にかかわらず愛を育てることが可能である。
3. 事例A:条件から始まり、愛に変わった結婚
ある男性(35歳、公務員)は、お見合いで出会った女性(32歳、看護師)と結婚した。最初は「安定した職業で堅実そうだから」という条件的判断にすぎなかった。しかし、結婚生活の中で、女性が彼の小さな成功を喜び、失敗しても責めずに支え続けた。その姿勢に触れるうち、男性は「この人の存在そのものが自分に安らぎを与えている」と気づいた。
分析:
この事例は、条件から出発した結婚が「相互承認」を経て愛に転換した典型例である。教授の言葉で言えば「安心(条件)から安らぎ(愛)へ」の移行である。
4. 事例B:愛が育たなかった結婚
一方で、ある女性(29歳、事務職)は、親の強い勧めでエリート企業に勤める男性とお見合いし結婚した。彼女は「親が安心するから」「条件が良いから」と考えていたが、夫婦生活が始まると、相手に感情的なつながりを感じられず、常に「もっと自分を愛してくれる人がいたのではないか」と不満を抱いた。数年後、彼女は別の男性との恋愛に走り、結婚生活は破綻した。
分析:
このケースは、条件依存と承認欲求に基づいた結婚の失敗例である。教授の視点からすれば「愛を学ぶ準備が整っていなかったため、制度が不安を露呈させた」典型である。
5. 愛を育てるプロセス
お見合いから愛が育つ場合、そのプロセスには一定の段階がある。
条件に基づく安心感
「生活は安定しそうだ」「親も納得している」という外的安心。
日常生活の共有
小さなやり取りを重ねる中で「相手の本当の姿」を知る。
存在の承認
「条件」ではなく「その人だから一緒にいたい」という気持ちが芽生える。
愛への転換
相手の自由を尊重し、相手の成長を喜べる段階に到達する。
教授は「愛は結果ではなくプロセスである」と述べる。お見合いという形式は、そのプロセスの第一歩に過ぎない。
6. カウンセリング場面の逐語記録(再現)
相談者(男性、婚活中):「正直、相手に特別な感情はありません。でも結婚すれば愛が育つものなのでしょうか?」
加藤教授:「あなたは相手のどんなところに安心を感じていますか?」
男性:「堅実で、生活が安定しそうだと……」
加藤教授:「それは『条件による安心』です。愛はそこから始まるのではなく、『相手と一緒にいると自分が自然でいられる』という安らぎから始まるのです」
男性:「では、愛は条件からは生まれないのですか?」
加藤教授:「条件はきっかけになります。しかし愛に変えるのは、あなたが相手を『所有』ではなく『承認』できるかどうかにかかっています」
分析:
教授は「条件は出発点であって目的ではない」と明言する。愛に育てるには、自分の心理を省察し、承認欲求や不安を超える作業が不可欠なのである。
7. お見合いが「愛の学校」となる可能性
加藤教授は、結婚を「愛を学ぶ場」として捉える。お見合いは条件や不安を色濃く映し出すため、愛の不在が露わになる場である。しかし逆に言えば、それをきっかけに「自分の心の在り方」を見直し、愛を学び直す契機ともなりうる。
お見合い → 「不安を条件で覆う自分」に気づく
結婚生活 → 「相手を承認できない自分」を突きつけられる
カウンセリング → 「孤独に耐える力」「自由を尊重する力」を学ぶ
成熟 → 「条件を超えて愛を育む関係」へ
このプロセスを経ることで、お見合いから始まった関係が、真の愛に到達することもある。
8. 第Ⅵ部のまとめ
お見合いから愛が育つかどうかは「形式」ではなく「当事者の心理的成熟」による。
孤独に耐える力、承認欲求を超える姿勢、相手の自由を尊重する力が愛を育てる条件である。
条件から始まった関係でも、存在の承認を通じて「安心」から「安らぎ」へと移行することで愛は成長する。
お見合いは「愛の不在」を映す場であると同時に、「愛を学び直す学校」となりうる。
9. 次章への接続
第Ⅵ部では「お見合いから始まる愛は育つのか」を心理的条件と事例から検討した。
次の第Ⅶ部では「お見合いと恋愛結婚の対比」に焦点を移し、両者の心理学的特徴と社会的影響を比較しながら、「愛の不在」と「愛の可能性」がどのように交差するのかを分析する。
第Ⅶ部 お見合いと恋愛結婚の対比 — 心理学的分析
1. お見合いと恋愛結婚の二つの出発点
お見合い結婚と恋愛結婚は、日本の結婚史の中でしばしば対照的に語られてきた。
お見合い結婚:
出会いは制度的に調整され、条件や世間体が前提となる。スタート地点は「合理的判断」や「安心」である。
恋愛結婚:
出会いは偶然や情熱に基づき、強い感情の高まりから始まる。スタート地点は「ときめき」や「熱情」である。
一見すると、恋愛結婚の方が「愛に基づいている」と思われやすい。しかし加藤諦三教授の視点からは、この対比は単純化しすぎており、実際には両者に共通する「愛の不在」の危険性が存在する。
2. 恋愛結婚に潜む「愛の不在」
教授は「恋愛結婚であっても、多くは愛ではなく依存である」と述べている。
恋愛結婚の典型的な心理的落とし穴は次のようなものである。
情熱の錯覚
相手を「自分の欲望を満たす存在」として理想化し、真実の相手像を見失う。
承認欲求の投影
「この人に愛されれば、自分には価値がある」と考え、愛を承認欲求で置き換えてしまう。
孤独の回避
「一人でいるのが怖いから恋愛する」心理は、結婚後に強い依存を生み出す。
つまり、恋愛結婚は感情が先行する分、「愛している」という錯覚に陥りやすく、逆に愛の不在を見抜きにくい。お見合いでは「愛の不在」が露骨に表れるのに対し、恋愛結婚ではそれが情熱に覆い隠されるのである。
3. お見合い結婚に潜む「愛の不在」
お見合い結婚では、条件や計算が先行するため、最初から「愛が欠けているのではないか」という不安が付きまとう。
条件依存:「安定しているから」「親が勧めるから」という理由で選択。
承認欲求:「結婚できれば自分の価値が証明される」という心理。
不安の投影:「結婚すれば孤独から逃れられる」という期待。
教授の視点からすれば、これは「愛ではなく社会制度や不安に支えられた関係」である。愛は存在そのものを承認することで芽生えるが、条件に依存する関係ではその成長が阻まれやすい。
4. お見合いと恋愛結婚の共通点
一見正反対のように見えるお見合い結婚と恋愛結婚には、共通する構造がある。それは 「不安と承認欲求に基づく結婚は、愛の不在を招く」 という点である。
恋愛結婚 → 「情熱」と「承認欲求」で突き進む
お見合い結婚 → 「条件」と「不安回避」で成り立つ
いずれも「自立して孤独に耐える力」を持たない人間にとっては、愛ではなく依存の関係となる。教授はこれを「愛の仮面をかぶった不安」と呼び、両者に共通する危うさを指摘している。
5. お見合いと恋愛結婚の違い
もちろん、両者には特徴的な違いもある。心理学的観点から整理すると以下の通りである。
項目 お見合い結婚 恋愛結婚
出発点 条件・計算・社会的要請 情熱・ときめき・感情
不安の現れ方 孤独や承認欲求を露骨に条件で補う 強い感情で不安を隠蔽する
愛の錯覚 少ない(愛が不在であることを自覚しやすい) 多い(愛があると錯覚しやすい)
失敗の原因 条件に依存し過ぎて心が伴わない 情熱の消失で現実を受け入れられない
愛が育つ可能性 条件を超え「存在の承認」に移行できれば育つ 自立を経て「依存」から「承認」へ移行できれば育つ
教授の分析に従えば、どちらも「愛を学ぶ課題」を内包しており、どちらが優れているという単純な比較はできない。
6. 具体的エピソード
事例A:恋愛結婚の破綻
大学時代に出会った二人は、情熱的に恋に落ち、周囲の反対を押し切って結婚した。しかし結婚後、夫は仕事で多忙となり、妻は「私を愛してくれない」と不満を募らせた。やがて夫婦関係は冷え込み、数年後に離婚。
→ 教授の視点:これは「承認欲求を愛と誤解した典型例」であり、恋愛結婚の落とし穴である。
事例B:お見合いから愛に育った結婚
親に勧められてお見合いをした女性は、最初は相手に特別な感情を持たなかった。しかし結婚後、夫が自分を責めずに受け止めてくれる姿勢に触れるうちに「この人の存在自体が安らぎになる」と感じるようになった。
→ 教授の視点:これは「条件の出会いを愛に転換した例」であり、お見合いが「愛を学ぶ場」となったことを示している。
7. 愛の有無を決めるもの
お見合いと恋愛結婚のどちらに愛があるかを問うことは、実は本質を外している。教授の立場から言えば、重要なのは 「出会いの形式」ではなく「人間の成熟度」 である。
自立している人 → どんな出会いからでも愛を育てられる
自立できていない人 → どんな出会いからでも愛を壊してしまう
つまり、愛の有無を決めるのは「制度」や「情熱」ではなく、「孤独に耐え、相手を承認できる心の力」なのである。
8. 第Ⅶ部のまとめ
お見合いと恋愛結婚は、出発点こそ異なるが、いずれも「不安と承認欲求」に支配されれば愛の不在を招く。
恋愛結婚は「情熱の錯覚」による失敗が多く、お見合い結婚は「条件依存」による空虚さに陥りやすい。
しかし両者ともに「自立」「承認」「孤独に耐える力」が備われば、愛を育てることができる。
よって、「お見合いに愛はあるか」という問いは、「人は愛を育てる力を持っているか」という根源的な問いに帰着する。
9. 次章への接続
第Ⅶ部では、お見合いと恋愛結婚を心理学的に比較し、それぞれに潜む「愛の不在」と「愛の可能性」を明らかにした。
次の第Ⅷ部では、「結婚相談所の現場における実証的ケース分析」として、現代日本におけるお見合いシステムが実際にどのように機能しているのか、そしてそこで人々がどのような心理的課題に直面しているのかを、具体的に検討していく。
第Ⅷ部 結婚相談所の現場における実証的ケース分析
1. 結婚相談所の役割と現代的意義
現代の結婚相談所は、伝統的なお見合いを制度的に継承しつつ、データマッチングやAIアルゴリズムを導入した「現代版お見合いの場」として機能している。
お見合いの仲介 → 仲人からカウンセラーへ
条件検索 → 学歴・年収・職業・年齢といった数値化可能なデータ
サポート体制 → コーチング・心理カウンセリング・自己紹介文作成支援
加藤諦三教授の視点から見れば、結婚相談所は「人々の不安と承認欲求を制度的に処理する場所」であると同時に、「愛を学ぶ場」として機能する可能性を持つ。
2. 統計的背景
近年の調査(※国勢調査や婚活関連統計)によると:
結婚相談所経由での婚姻数は全体の約1割前後だが、**成婚率(出会いから結婚に至る確率)は20〜30%**と比較的高い。
離婚率を見ると、恋愛結婚とお見合い結婚で大きな差はなく、むしろ「条件が安定しているお見合い結婚の方が長期的継続率が高い」というデータもある。
しかし、加藤教授の立場からすれば、数字の安定が必ずしも「愛の存在」を意味するわけではない。条件や制度に支えられた関係が長続きすることと、愛が育まれていることは全く別問題だからである。
3. ケース分析①:承認欲求に支配された利用者
事例
女性(32歳、会社員)。
「結婚すれば親も安心し、友人に引け目を感じなくて済む」との理由で相談所に登録。プロフィールには「安定した職業の男性希望」「年収600万円以上」と記載。
逐語記録(カウンセラーとの対話再現)
カウンセラー:「理想の結婚生活は?」
女性:「親に孫を見せたいです。周りの友人も結婚しているので……」
カウンセラー:「お相手の人柄については?」
女性:「やはり条件が大事です。性格は普通であれば」
分析
ここでは「愛されたい」という承認欲求が前面に出ており、相手を存在として承認する態度は欠けている。教授の言葉で言えば「他人の人生を生きている」状態であり、成婚しても愛は不在となりやすい。
4. ケース分析②:不安から逃れるための登録
事例
男性(38歳、会社員)。長年独身で「一人でいると将来が不安」と感じ、結婚相談所に登録。
逐語記録(カウンセラーとの対話再現)
男性:「休日に一人で過ごすと寂しくて……結婚すれば不安がなくなると思って」
カウンセラー:「どんな相手を望んでいますか?」
男性:「とにかく優しい人。誰でもいいから一緒にいてくれる人が欲しい」
分析
ここで表れているのは「愛」ではなく「不安の投影」である。教授は「孤独に耐えられない人間は愛せない」と指摘している。このケースでは、結婚が「孤独からの逃避手段」として利用されており、愛の不在が前提となっている。
5. ケース分析③:条件から愛に育った例
事例
女性(30歳、看護師)。
「生活が安定する相手が良い」という条件意識で相談所を利用し、同年代の男性(32歳、SE)と出会う。
逐語記録(数か月後のフォローアップ面談)
女性:「最初は条件で選んだ気持ちが強かったのですが、一緒にいると落ち着きます。私の小さな話も聞いてくれて」
カウンセラー:「安心ではなく、安らぎを感じられているのですね」
女性:「そうですね。以前は『相手に尽くさなきゃ』と思っていましたが、今は自然でいられる気がします」
分析
このケースは「条件依存」から始まりながらも、相互承認を通じて愛へ移行している。教授の言葉でいえば「安心(条件)から安らぎ(愛)へ」の転換が起きた事例である。
6. ケース分析④:カウンセリングを通じて愛を学んだ例
事例
男性(42歳、再婚希望)。
前の結婚では妻に依存し、束縛が原因で離婚。再び相談所に登録したが、同じ失敗を繰り返すのではと不安。
逐語記録(心理カウンセリング場面再現)
男性:「相手が少しでも連絡をくれないと不安でたまらなくなる」
カウンセラー:「それは愛ではなく、依存です」
男性:「愛しているからでは?」
カウンセラー:「愛は相手の自由を尊重します。相手があなたの思い通りにしないと不安になるのは、愛ではなく支配です」
男性:「……今まで勘違いしていたのかもしれません」
分析
ここで本人が「依存と愛の違い」に気づいたことが重要である。教授の立場からは「愛は学ぶもの」であり、失敗を通じて自立を獲得すれば、次の結婚では真の愛を築ける可能性が高まる。
7. 結婚相談所の現場が示す心理的傾向
結婚相談所のケースを総合すると、以下の傾向が見られる。
不安と承認欲求の可視化
登録者は「結婚すれば不安がなくなる」「親に認められる」という動機を口にしやすい。
条件依存の構造
プロフィール作成やマッチングの過程で、学歴・収入といった「数値的条件」が強調され、愛よりも合理性が優先される。
カウンセリングの意義
逐語的な対話を通じて「依存と愛の違い」を理解することで、愛を学び直す契機が生まれる。
8. 第Ⅷ部のまとめ
結婚相談所は「現代版お見合い」として機能しており、条件依存や承認欲求が可視化されやすい場である。
ケース分析から明らかなように、愛の不在は制度ではなく「人間の心理的基盤」に起因する。
しかし、カウンセリングや自己洞察を通じて「条件の安心」から「存在の承認」へと移行する場合、愛は育つ。
結婚相談所は「愛を回避する制度」であると同時に、「愛を学び直す実験場」にもなりうる。
9. 次章への接続
第Ⅷ部では、結婚相談所の現場をケーススタディとして分析し、「不安と承認欲求の投影」と「愛の可能性」を示した。
次の 第Ⅸ部「『愛を学ぶ場』としてのお見合いの可能性」 では、さらに一歩進めて、制度的出会いをいかに「愛を育てる学びの場」と転換できるかを検討していく。
第Ⅸ部 「愛を学ぶ場」としてのお見合いの可能性
1. お見合いを「愛の不在」と見る従来の視点
これまで繰り返し確認してきたように、お見合いは条件や計算に基づく出会いであり、そこには「愛の不在」が露呈しやすい。実際、多くの逐語記録や事例で見られたように、
「親が安心するから」
「条件が整っているから」
「孤独を避けたいから」
といった理由が前面に出る。
従来の議論では、このような動機に基づくお見合いを「愛なき制度」として否定的に捉える傾向が強かった。
2. 加藤諦三の視点:「愛は学ぶもの」
しかし、加藤諦三教授は「愛は生まれつき備わっているものではなく、学ぶものである」と繰り返し説いている。
人は幼少期の家庭環境や愛情体験によって、愛する力に差が生まれる。
愛の不在を経験した人は、承認欲求や依存に傾きやすい。
だが、それは不変ではなく、「自立」と「他者承認の学習」を通じて獲得し直すことが可能である。
この視点に立つと、お見合いは単なる「愛の不在を強調する制度」ではなく、むしろ「愛を学ぶための学校」として位置づけ直すことができる。
3. お見合いが「学びの場」となりうる理由
お見合いの制度的特徴を整理すると、そこには「愛を学ぶ」契機が内在している。
条件の可視化
学歴・年収・職業・年齢などが明示されることで、人がどれほど「条件に依存しているか」に気づける。
それにより「私は条件で人を見てしまっている」という自己洞察のきっかけになる。
第三者(仲人・カウンセラー)の介在
第三者が介入することで、自分の心理を客観的に見つめ直す場が生まれる。
依存的傾向や承認欲求が指摘されやすい。
プロセスの反復性
何度かのお見合い経験を通じて「同じ失敗を繰り返す自分」に気づく。
それは愛を学び直す動機となりうる。
4. ケース分析①:条件依存からの気づき
事例
女性(34歳、公務員)。「年収600万円以上の男性でなければ」と条件を設定し続けたが、相手と会話が続かず成婚できなかった。
逐語記録(カウンセラーとの対話)
女性:「条件が良い人ばかり選んでいるのに、なぜうまくいかないんでしょう」
カウンセラー:「条件は合っていても、あなたが相手を『人』として見ていないからかもしれません」
女性:「……確かに、相手を好きかどうかは考えていませんでした」
分析
この気づきは「条件依存から存在承認へ」移行する第一歩である。教授の言葉を借りれば、これは「愛の不在を直視することで、愛を学ぶ入り口に立った」瞬間である。
5. ケース分析②:承認欲求を超える学び
事例
男性(37歳、会社員)。「結婚すれば親が安心する」という動機で活動していたが、交際が続かず挫折感を抱く。
逐語記録
男性:「親のために結婚しようと思っていたのに、相手に気持ちが入らないんです」
カウンセラー:「あなたは自分の人生を生きていますか? それとも親のために生きていますか?」
男性:「……親の期待ばかり考えていました」
分析
この気づきは「承認欲求を愛と誤解していた」ことの自覚である。教授の視点では、この段階を経ることで初めて「自分の意志で他者を愛する可能性」に近づく。
6. ケース分析③:孤独と向き合う契機
事例
女性(40歳、医療職)。「一人でいるのが寂しいから」という理由で相談所に登録。しかし複数回のお見合いが不成立に終わり、孤独に直面することとなる。
逐語記録(カウンセリング場面)
女性:「誰も選んでくれない。結婚できなければ私は価値がない」
カウンセラー:「結婚しなければ価値がないと思っている時点で、あなたは愛を他人に依存しています」
女性:「……一人で生きることを考えたことはありませんでした」
カウンセラー:「孤独を受け入れた人だけが、他人を愛せるのです」
分析
教授が説く「孤独に耐える力」がここで明確に課題となる。お見合いが不成立に終わったことは失敗ではなく、むしろ愛を学ぶ重要な契機となった。
7. お見合いから「愛を学ぶ」プロセス
お見合いの現場を「愛を学ぶ学校」として見るなら、その学習プロセスは次のように整理できる。
条件の優先 → 「安定」「親の安心」「社会的評価」
失敗や違和感の経験 → 会話が続かない、虚しさを感じる
自己省察 → 「自分は条件や承認欲求に支配されていた」と気づく
孤独と向き合う → 「一人でも自分の人生を肯定できる」
愛の獲得 → 相手を条件抜きで存在として承認できる
8. カウンセリングの意義
結婚相談所のカウンセラーは単なる仲介者ではなく、愛を学ぶ支援者として重要な役割を果たす。逐語的対話を通じて、
「条件依存」から「存在承認」へ
「承認欲求」から「自立」へ
「不安の投影」から「孤独の受容」へ
と導くことが可能になる。これはまさに加藤教授が提唱する「心理的成長のプロセス」を実践の中で体現する場である。
9. 第Ⅸ部のまとめ
お見合いは条件依存・承認欲求・不安の投影が露呈しやすく、愛の不在を明確にする場である。
しかしその「不在」を直視することこそが、愛を学び直す契機となる。
結婚相談所は「愛を学ぶ学校」として機能しうる。
お見合いから愛を育てるためには、失敗や挫折を通じて自分の不安に気づき、孤独を受容する力を養うことが不可欠である。
10. 次章への接続
第Ⅸ部では、お見合いを「愛の不在」から「愛を学ぶ場」へと転換する可能性を論じた。
次の 終章「『お見合いに愛はあるか』への加藤諦三的回答」 では、本論全体を総括し、教授の立場から「お見合いと愛」の最終的な関係を明らかにしていく。
終章 「お見合いに愛はあるか」
1. 問いを改めて捉える
「お見合いに愛はあるか」という問いは、単に「お見合い結婚は愛に基づいているか否か」を尋ねるものではない。それは、人間が結婚において 何を求め、どこまで自立し、どのように愛を学ぶのか という根源的な課題を突きつける問いである。
お見合いは、条件と社会的要請を前提にしている。
恋愛結婚は、情熱と承認欲求を前提にしている。
しかし両者に共通するのは、成熟していない人間にとっては「愛の不在」に陥りやすいという点である。
この視点から見れば、「お見合いに愛はあるか」という問いは、実は「人間に愛を育てる力があるか」を問うことと同義である。
2. 愛の不在の実相
加藤諦三教授の理論に基づけば、次のような心理が支配するとき「愛の不在」が生じる。
承認欲求の支配:「結婚すれば世間に認められる」「親が喜ぶ」
不安の投影:「結婚すれば孤独から逃れられる」「条件が安定すれば安心」
依存と支配:「相手に幸せにしてもらいたい」「相手を思い通りにしたい」
お見合いの現場ではこれらが制度的に強化されやすい。条件や仲人の視線が前提となるため、本人の内的成熟が不足している場合、愛は最初から芽生えにくい。
3. 愛が育つ条件
しかし教授は決して悲観的ではない。彼は「愛は学ぶもの」であり、次の条件が満たされるならば、お見合いからも愛は育つと説く。
孤独に耐える力
結婚を「孤独の逃避」ではなく「孤独を分かち合う場」として捉えられるか。
承認欲求を超える力
「結婚によって他人に認められる」ことから解放され、「相手を承認する」ことに重心を移せるか。
相手の自由を尊重する力
相手を所有物にせず、相手が自分と異なることを喜べるか。
これらの心理的成熟が伴えば、条件から始まったお見合いであっても、関係は「安心」から「安らぎ」へと転換し、愛は育つ。
4. 事例からの総合
愛に育ったお見合い
初めは条件だけで結婚を決めたが、日常の中で「相手の存在そのもの」が安らぎを与えることに気づいた夫婦。
愛に育たなかったお見合い
親や世間の期待に応えるために結婚し、虚しさに苛まれた夫婦。
この両極の事例が示すのは、「制度が愛を決めるのではなく、人間の心理的成熟が愛の有無を決定する」という事実である。
5. 現代的意味
結婚相談所や婚活アプリといった現代の出会いの仕組みも、実質的には「お見合いの延長線上」にある。
プロフィールや条件検索 → かつての仲人の推薦
AIマッチング → 条件の効率化
カウンセラーの助言 → 仲人の心理的補助
現代の婚活においても、「条件や不安への依存」と「愛の不在」は同じように繰り返されている。したがって、この問いは過去の問題ではなく、今を生きる私たちにとっても切実である。
6. 加藤諦三的結論
教授の視点を総合すると、「お見合いに愛はあるか」という問いへの答えは次のように整理できる。
制度そのものには愛はない
条件や計算の制度に、愛は内在しない。
人間次第で愛は育つ
自立した人間が臨むとき、制度は愛を学ぶ舞台となる。
愛の不在を映す鏡としての役割
お見合いは人間の不安・承認欲求を可視化し、そこから愛を学び直す機会を与える。
教授の言葉を借りれば、
「結婚は愛の逃げ場ではない。結婚とは、自分の孤独に耐えた人間だけが選ぶことのできる、もう一つの挑戦である。」
7. 終章のまとめ
「お見合いに愛はあるか」という問いは、制度の是非ではなく、人間が愛を学ぶ力を持っているかを問うものである。
愛の不在は、条件や不安、承認欲求に支配されるとき必然的に生じる。
しかし、人が自立を獲得し、相手を存在として承認できるとき、お見合いは愛を育む場となる。
したがって答えは「お見合いそのものに愛はない。しかし、お見合いを通して人は愛を学ぶことができる」である。
8. 本稿全体の総括
本論全体を通じて明らかになったのは、結婚制度や出会いの形式そのものが愛を決定するのではなく、人間の心理的成熟が愛の有無を決めるということである。
「お見合いに愛はあるか」という問いは、最終的には「私たちは本当に愛する力を持っているか」という自己への問いへと還元される。