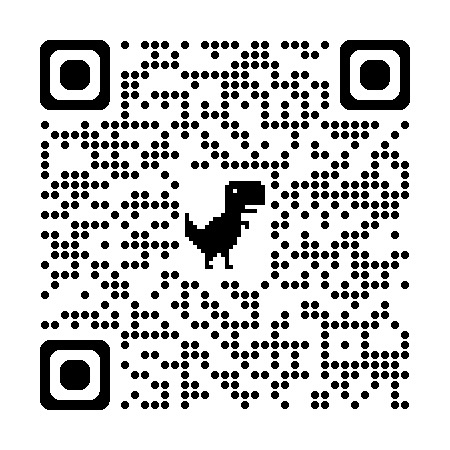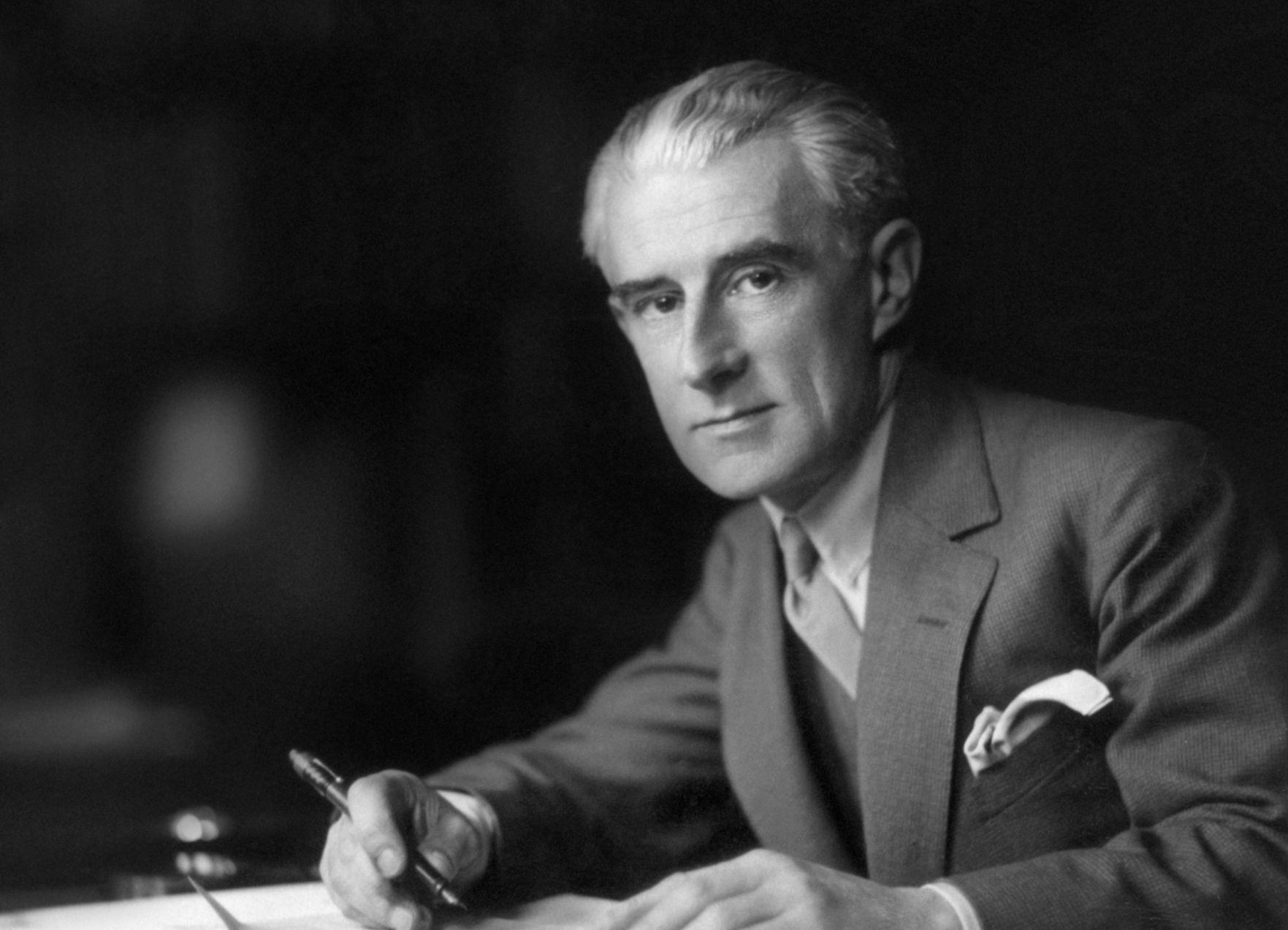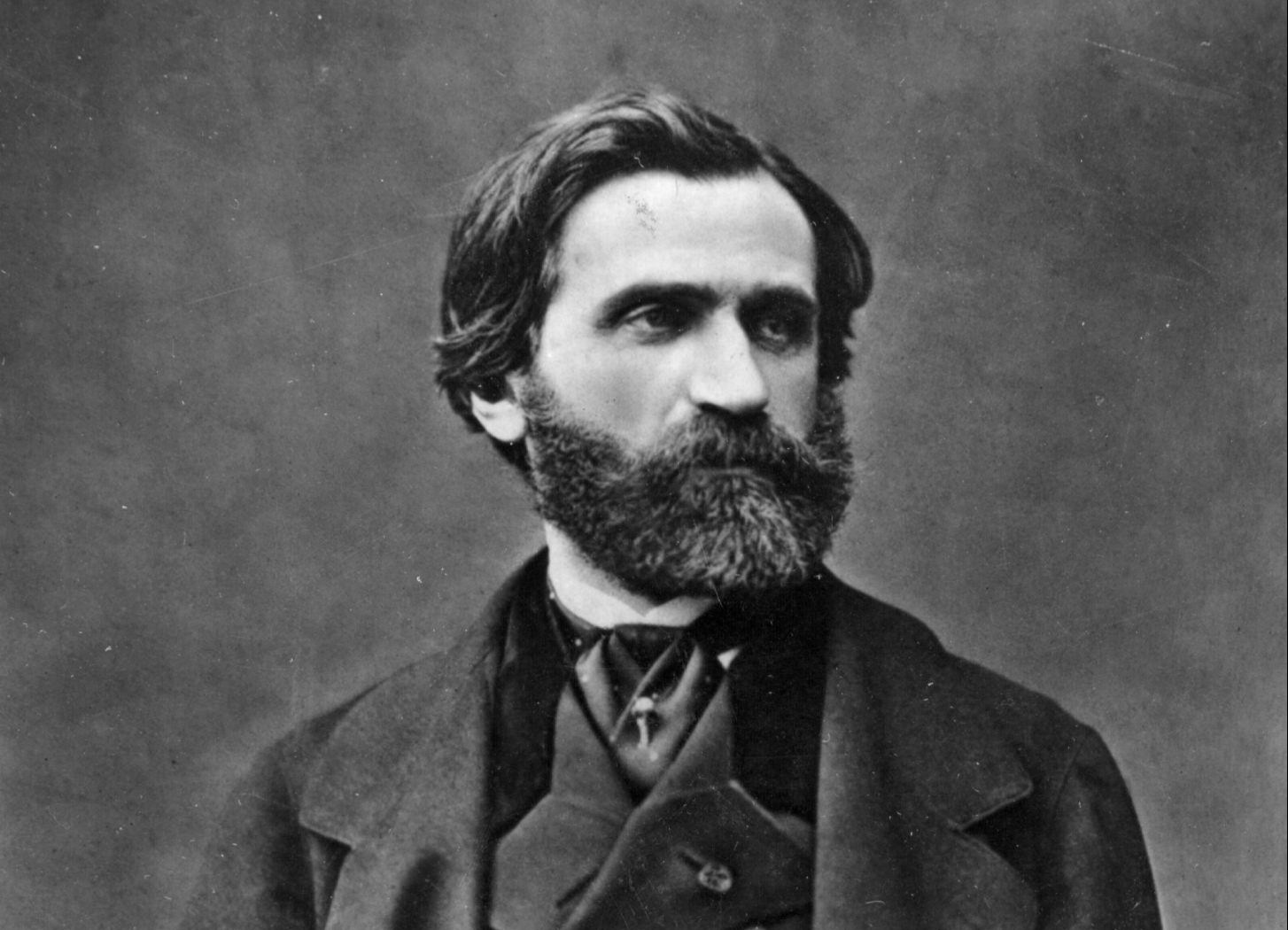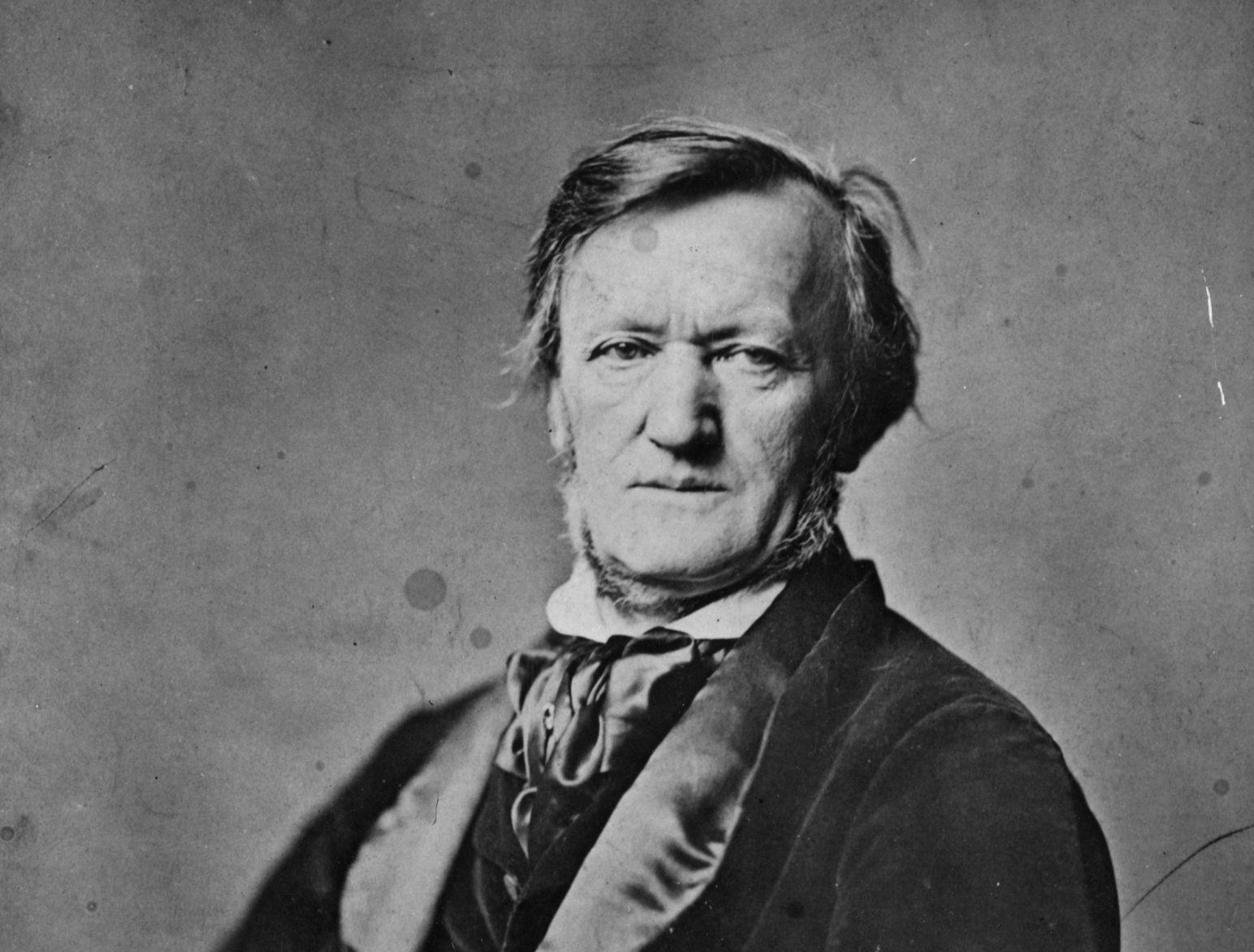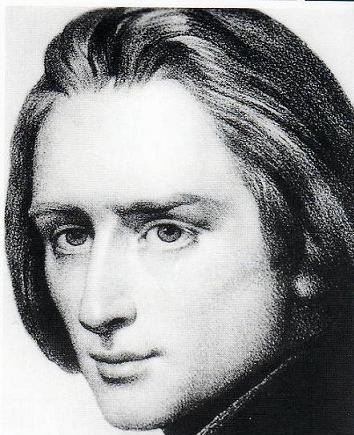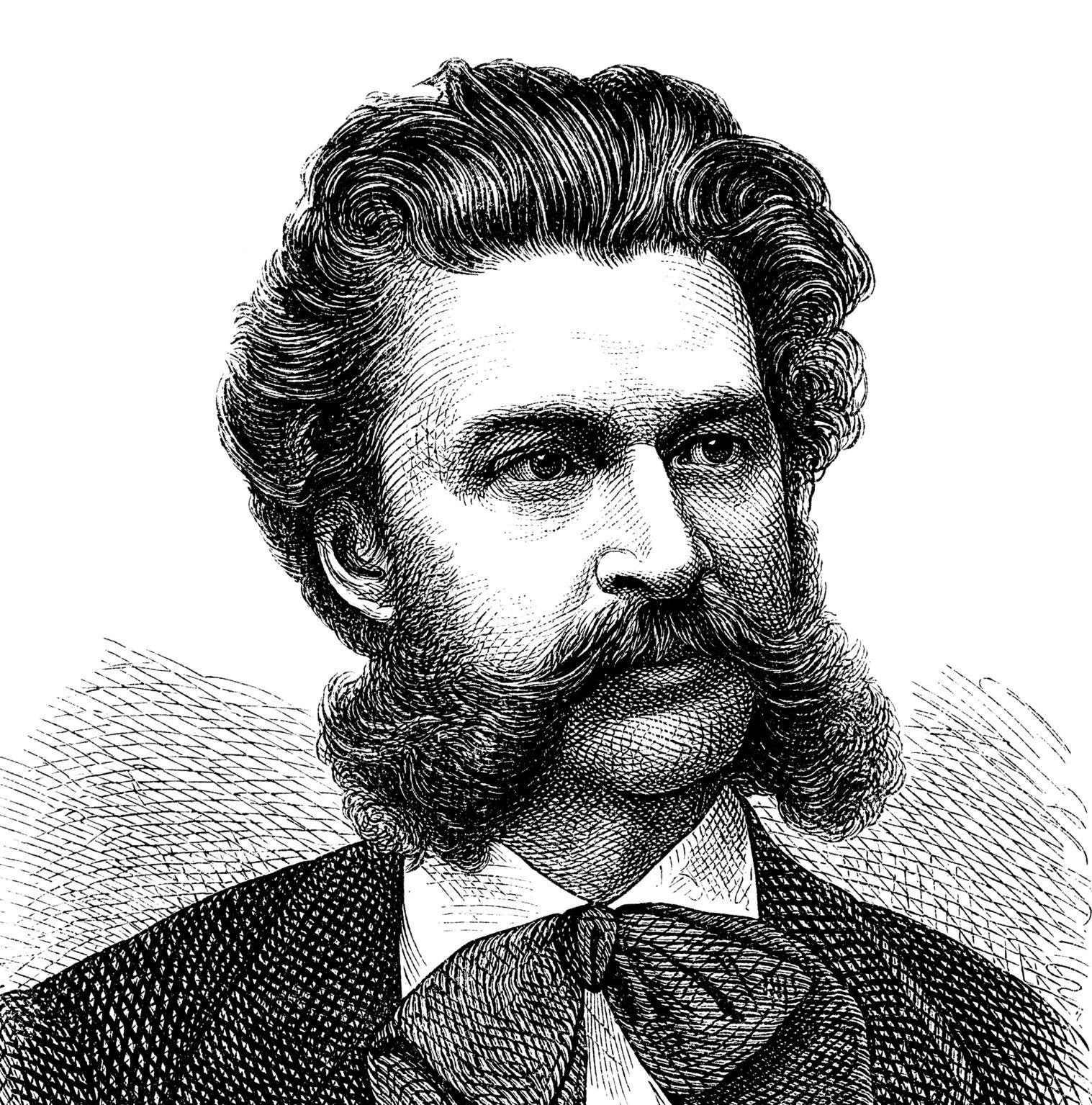ショパン・マリアージュ
(恋愛心理学に基づいたサポートをする釧路市の結婚相談所)
お気軽にご連絡下さい!
TEL.0154-64-7018
FAX.0154-64-7018
Mail:mi3tu2hi1ro6@gmail.com
URL https://www.cherry-piano.com
全体構成
序章 なぜ三巨頭を比較するのか
恋愛観・結婚観の心理学的研究史における位置づけ
精神分析学派(フロイト)、分析心理学(ユング)、個人心理学(アドラー)の理論的前提
現代の恋愛・結婚市場への示唆
第1章 フロイトの恋愛観・結婚観
1.1 リビドー理論と性的欲望の位置づけ
1.2 エディプス・コンプレックスと異性選択
1.3 結婚を「文化的制度」として見る視点
1.4 事例分析:フロイト時代のウィーン社交界と結婚観
1.5 臨床ケース:抑圧された欲望が婚姻関係に与える影響
第2章 ユングの恋愛観・結婚観
2.1 アニマとアニムスの理論
2.2 投影としての恋愛
2.3 結婚の「個性化」プロセスへの貢献
2.4 象徴と無意識の結合としての結婚
2.5 事例分析:長期婚姻における象徴的交流の変化
第3章 アドラーの恋愛観・結婚観
3.1 共同体感覚と愛
3.2 愛は「課題」のひとつ
3.3 パートナーシップと対等性
3.4 結婚における勇気と責任
3.5 事例分析:課題分離と夫婦関係改善のプロセス
第4章 三者比較:理論的対立点と接点
4.1 欲望中心(フロイト)vs 無意識の統合(ユング)vs 社会的責任(アドラー)
4.2 恋愛の動機づけ構造の違い
4.3 結婚を通じた人格成長の可能性と限界
第5章 現代日本における適用
5.1 婚活市場での活用事例
5.2 AIマッチング時代における三理論の意味
5.3 恋愛と結婚の心理教育への応用
終章 愛と結婚の心理学の未来像
三者の統合的アプローチ
「愛する」という行為の心理的成熟