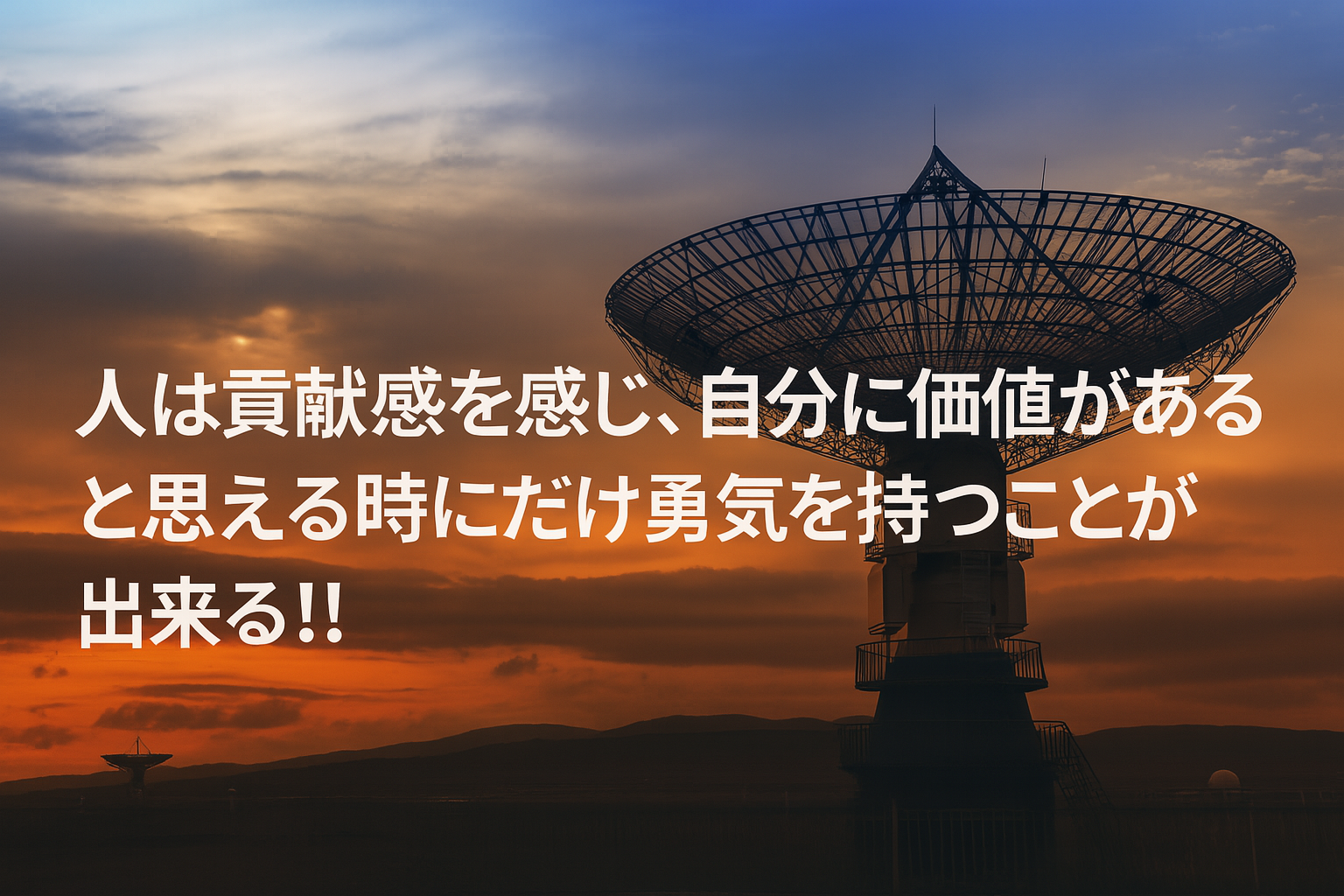第2章:理論的基盤──アドラー心理学とは
1. アドラー心理学の成立と特徴
アルフレッド・アドラー(Alfred Adler, 1870–1937)は、ウィーンの精神科医・心理学者であり、ジークムント・フロイトの初期の弟子でしたが、精神分析の無意識中心の立場に異を唱え、より社会的・目的論的な人間観を打ち出したことで独自の「個人心理学(Individual Psychology)」を築きました。
アドラーの心理学の基本的な特徴は次の3点に集約できます:
目的論的アプローチ
人間の行動は過去によって規定されるのではなく、未来に向かう「目的」によって意味づけられる。過去のトラウマよりも、「今、どこへ向かおうとしているか」が大切。
全体論的アプローチ
人は心と体、感情と行動、社会との関係などが不可分な「全体」として働く。部分的な症状分析ではなく、個人の全体像とライフスタイルを見て理解する。
社会的アプローチ
人は本質的に社会的存在であり、他者とのつながり(=共同体感覚)を持つことで心理的健康が保たれる。
このように、アドラー心理学は「人間とは目的を持った社会的存在であり、その生き方(ライフスタイル)は他者との関係を通じて形作られる」という立場に立っています。
2. 「勇気」とは何か
アドラー心理学において、もっとも重視される資質の一つが「勇気(Mut)」です。しかし、この勇気は一般的に言う“危険に飛び込む力”とは異なります。アドラーが語る勇気とは、「失敗を恐れずに行動する力」「自己の不完全さを受け入れながら、他者とのつながりを模索する力」です。
勇気を持てるか否かは、「他者から自分は必要とされている」「自分が社会に貢献できている」という感覚──つまり「貢献感」が得られるかどうかに大きく左右されます。貢献感が高いほど、人は自己を肯定的に捉えることができ、困難に直面しても立ち向かう力を持ちやすくなるのです。
3. 「共同体感覚」と「貢献感」
アドラーの核心的概念に「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」があります。これは「他者への関心(social interest)」とも訳され、人が精神的健康を保ち、社会に貢献し、幸福に生きるための鍵とされます。
共同体感覚には次の三要素があります:
所属感:「自分はこの場所にいていい」と思える感覚
他者貢献:「自分は誰かの役に立っている」という実感
共感的理解:他者の立場や気持ちを理解しようとする姿勢
このうち、「他者貢献」によって得られるのが「貢献感」であり、それが自尊心や自己効力感を育み、「勇気」の源となります。逆に、貢献感を得られない人は、劣等感に苛まれ、「どうせ自分なんて」と無力感を抱きやすくなります。
4. 劣等感と勇気の関係
アドラー心理学のもう一つの要である「劣等感(Inferiority Feeling)」も、勇気との関係で考えることができます。人間は生まれながらにして無力で不完全であり、常に何らかの劣等感を抱えています。これは決して否定すべきものではなく、アドラーはこれを「成長への原動力」と捉えます。
しかし、その劣等感を克服する勇気がなければ、以下のような形で心理的問題へとつながります:
劣等コンプレックス:劣等感に囚われ、行動ができなくなる
優越コンプレックス:自らの劣等を否定し、他者を見下して自信を保とうとする
いずれにせよ、根底にあるのは「自分には価値がないのでは」という恐れであり、それを乗り越えるには「誰かの役に立てている」という確かな貢献感が必要です。
5. ライフスタイルと勇気の育成
アドラーは、人は「ライフスタイル(人生の在り方)」を4~6歳頃までに形成し、それに基づいて思考・感情・行動のパターンを構築していくと考えました。ライフスタイルには、自分にどんな価値があるか、世界がどんな場所か、他人をどう見るかなどが含まれます。
このライフスタイルが他者とつながることを目的としていれば、貢献感を得やすく、勇気ある行動が生まれます。逆に、他者を敵視し、自己中心的なライフスタイルを持っていると、貢献感を得ることは困難で、勇気を持つことも難しくなります。
まとめ:理論としての整理
勇気は「貢献感」の上に成立する。貢献感は「共同体感覚」の中核である。
勇気を持てない人は、しばしば貢献感や所属感の欠如に悩んでいる。
ライフスタイルや劣等感の捉え方によって、勇気の発揮には大きな差が出る。
アドラー心理学は「個人」と「社会」を架橋する実践的心理学であり、勇気を育てるためには「他者とつながり、貢献できる」場の提供が鍵となる。
第3章:貢献感が生まれるメカニズム
1. なぜ人は貢献したいと願うのか?
アドラー心理学では、人間の根源的欲求として「共同体への所属」と「貢献したいという意志」があるとされます。この欲求は、「人は本来、社会的存在である」という前提から導き出されるものです。
アドラーは、孤立を最も深刻な心理的苦痛とみなし、「人は誰かに必要とされるときにこそ、自らの存在価値を見出す」と述べました。この視点に立てば、「自分は誰かの役に立っている」「貢献できている」と感じたときに初めて、安心と自信、さらには“勇気”が湧き上がってくるのです。
この貢献感は、単なる自己満足とは異なり、社会的つながりの中で意味づけられるものであるため、他者との関係が重要になります。つまり、「他者の存在」なくして人は貢献感を得ることができません。
2. 貢献感を生む3つの心理的ステップ
貢献感が人の中でどのように生まれるかを段階的に見ると、以下のようなプロセスが浮かび上がります:
ステップ①:自分が受け入れられているという感覚(所属感)
まず、人は「自分がここにいてよい」「ここにいても拒絶されない」という感覚を持つことが重要です。アドラーの言う「所属感」は、この安心感が基盤となっています。
たとえば、学校や職場、家庭といった集団の中で、「存在を否定されない」「発言してもよい」と感じられるとき、人は初めてその場で「何かをしてみよう」と思えます。貢献感は、その土台の上に築かれるものです。
ステップ②:役割と責任の付与
次に、人が「役に立てるかもしれない」と思うためには、具体的な役割や責任が必要です。これは、たとえ小さなものであっても構いません。たとえば、学校で「黒板を消す」「掃除を分担する」といった活動、職場での「備品の管理」「新人のサポート」など、誰かに必要とされるポジションを担う経験です。
ここでは、「自分が任されている」「信頼されている」という感覚が育ちます。これにより、「自分は価値ある存在である」という認識が芽生えます。
ステップ③:感謝や反応によるフィードバック
最後に、行った行為が他者にどのように影響を与えたかの「フィードバック」が重要です。「ありがとう」と言われることや、行為によって誰かが喜ぶ姿を見ることは、自らの行為の“意味”を実感する貴重な経験になります。
このような肯定的フィードバックによって、「自分の存在が誰かの役に立っている」と体感し、それが貢献感として内面化されていきます。
3. 勇気を育てる貢献感の連鎖
上記3ステップを経て得られた貢献感は、自己評価や自己肯定感を高め、次なる挑戦への「勇気」となっていきます。これは、次のような心理的連鎖として整理できます:
所属感の獲得 → 自分を否定されない安心感
役割の遂行 → 価値の実感
他者の感謝や反応 → 他者への信頼
貢献感の内面化 → 自己肯定感の向上
困難に対峙する勇気 → 新たなチャレンジへ
ここで重要なのは、勇気とは単なる“性格”や“気質”の問題ではなく、「他者との関係性の中で育まれるもの」だという点です。つまり、勇気を持てるかどうかは個人の意志力ではなく、周囲との心理的なやりとりの中で形成されていくのです。
4. 子どもと貢献感──早期体験の重要性
アドラーは、子どもの教育においても「貢献感」が育つことが重要であると考えました。幼少期に「あなたがいるから助かっている」と言われた経験、「ありがとう」と言われた経験は、人格の基盤となるライフスタイルの形成に強い影響を与えます。
逆に、子どもが何かをしても反応されず、常に「まだまだ足りない」「それくらいできて当たり前」と否定され続ける環境では、貢献感は育たず、「どうせ何をしても無駄だ」といった無力感に支配されやすくなります。
5. 大人にとっての貢献感
成人においても、貢献感の有無は人生の満足度を大きく左右します。特に、次のような場面で「役立っている」という実感は、心理的充足につながります:
仕事:同僚や部下にとっての支えとなる
家庭:家族のために何かをする
地域活動:近所やボランティアで誰かを助ける
趣味の場:仲間との共創や学びの貢献
定年退職後のうつやアイデンティティの喪失が問題になるのも、「貢献感の喪失」が一因です。つまり、貢献感は生涯を通じて必要な心理的要素なのです。
結論:貢献感が勇気を呼び起こす心理的ループ
アドラー心理学において、「貢献感」は単なる感情ではなく、行動と関係性の中で育まれる“能動的な感覚”です。そしてその貢献感が、「勇気」という人間の行動エネルギーの根本を支えるという点において、極めて重要な心理的メカニズムといえます。
この視点に立てば、勇気を持てない人を責めるのではなく、「その人が貢献できる機会を持っていないのではないか」「他者からのフィードバックが不足しているのではないか」という“関係性”に目を向ける必要があるとわかります。
第4章:具体的な事例・エピソード
アドラー心理学における「貢献感が勇気を育む」という理論は、実際の人間関係や生活の中でどのように体現されているのでしょうか。本章では、さまざまな背景を持つ人々のエピソードを通じて、貢献感がどのようにして勇気を生み出し、人生を転換させていったのかを描いていきます。
1. 職場復帰に踏み出せた中年男性:再就職支援センターでの役割
佐藤健一さん(仮名、55歳)は、大手メーカーの早期退職制度を利用して職場を離れた後、長期間の無職状態にありました。自身のキャリアが「もう誰にも必要とされない」と思い込み、再就職活動も消極的になっていました。
そんな佐藤さんは、あるNPO法人の再就職支援ボランティアに参加する機会を得ます。はじめは消極的でしたが、職業相談を受けに来た若者に、自分の業界経験や履歴書の書き方のコツを伝えたことで、「話を聞けてよかったです」という感謝の言葉をもらいます。
その経験から、「自分の知識もまだ価値があるのかもしれない」と感じ始め、最終的には、若者支援に関わる再就職先に自ら応募し、見事に採用。今では後進のキャリア支援をライフワークとしています。
➡ このエピソードは、**「役割の付与」→「肯定的なフィードバック」→「貢献感の内面化」→「勇気をもって新たな行動へ」**という典型的な心理変化の過程を示しています。
2. 家庭内で自信を取り戻した主婦:家事から見える貢献の価値
主婦の山田由美さん(仮名、42歳)は、専業主婦として10年以上家庭を支えてきましたが、「家族のために尽くすのは当たり前」とされ、感謝の言葉もなく、自尊心を喪失していました。
ある日、地域の料理教室で自身の得意なレシピを紹介することになり、参加者から「丁寧な説明で分かりやすい」「家でも作ってみたい」と反響があったことで、初めて自分の「家事スキル」が他人の役に立っていることを実感します。
その後、彼女は地域の高齢者向け料理支援のプロジェクトに加わり、食事を通じた交流活動に発展。家庭内でも子どもや夫との会話が増え、心理的にも安定した生活を取り戻していきました。
➡ この例は、「家庭で評価されない貢献が、他者の場で承認されることにより、自己価値の回復と社会参加への勇気につながる」ことを示しています。
3. 不登校からの再起:生徒会活動への参加がもたらした変化
中学2年生の鈴木拓海くん(仮名)は、学校の人間関係のトラブルで長期不登校となっていました。最初は家庭教師やカウンセラーとの個別対応が中心でしたが、彼の関心が「動画編集」にあることを教師が知り、生徒会の広報係として文化祭の映像制作を依頼することになります。
自宅で編集した動画が学校内で好評を得たことにより、彼は「自分の存在が学校に必要とされている」という実感を抱くようになります。その後、段階的に登校回数が増え、最終的には文化祭の舞台発表にも登壇しました。
➡ この事例は、「能力の認知」→「他者からの依頼」→「感謝と評価」→「所属感と勇気の回復」へとつながる回復モデルの実例です。
4. 介護の場で得た貢献感:高齢男性の再生
石川信一さん(仮名、70歳)は退職後、社会とのつながりを断ち、孤独な日々を送っていました。家族との関係も希薄で、何をしても張り合いがなく、「生きる意味」を見失っていたといいます。
そんな中、近隣のデイケアセンターで週1回の囲碁教室のボランティアを依頼されます。はじめは気乗りしなかったものの、自分が囲碁を教えることで、参加者が笑顔を見せたり、会話が弾むのを目にし、自らも生き生きとした表情を取り戻していきました。
今では週3回、囲碁だけでなく人生相談にも応じる“人生の先輩”として地域に愛される存在となっています。
➡ 高齢期においても「誰かの役に立てている」という実感は、健康や自己肯定感の維持に直結するという心理的真実を体現しています。
5. 企業リーダーにおける貢献と勇気:若手の成長を支える喜び
佐々木麻衣さん(仮名、39歳)は、中堅企業のマネージャーとしてチームをまとめる立場にあります。過去には業務量に追われる中で部下と衝突し、「管理職に向いていない」と思い悩むこともありました。
しかし、新入社員のメンターとして「質問しやすい雰囲気づくり」「小さな成功体験を褒める」という関わりを意識的に実践したことで、若手のパフォーマンスが大きく改善。「先輩のおかげです」という言葉に胸を打たれ、自分の存在が“未来を育てている”と実感します。
この体験が、彼女に再びマネジメントへの情熱と責任感を呼び起こし、以後は社内の育成プロジェクトにも積極的に関与するようになりました。
➡ 「支えることで勇気を得る」という逆説的な成長モデルを示す好例です。部下や後輩への貢献が、自己の役割意識を再定義させ、勇気を与えたことが分かります。
総括:事例が語る「人は関係の中で育つ」
ここに示した5つの事例は、いずれも異なる年代・背景を持つ人々ですが、共通して言えることは、「貢献感」が得られることで人生の転機を迎えている点です。
関係性が希薄だった状態から、
他者とのつながりが生まれ、
何らかの役割を通じて自信を得て、
勇気を持って次の一歩を踏み出している。
このように、「貢献感」は決して一方的に与えられるものではなく、「関係性の中で相互に育まれるもの」であり、そこから得られる“勇気”は人を変えるだけでなく、社会や組織をも活性化させる力を持っています。
第5章:貢献感を育む心理支援・教育の実際
「人は貢献感を感じ、自分に価値があると思える時にだけ勇気を持つことが出来る」というアドラーの命題は、教育・カウンセリング・人材育成など多様な現場で極めて実践的な指針となります。本章では、こうした場面で貢献感を育てるための具体的な方法とその意義を論じます。
1. 心理支援における貢献感の育成
(1)ライフスタイル分析の活用
アドラー心理学では、個人が持つ「ライフスタイル(人生に対する一貫した態度や行動様式)」を理解することが、支援の出発点とされます。これは4~6歳頃に形成され、現在の課題への取り組み方や他者との関わり方に強い影響を与えます。
カウンセリングにおいては以下のようなステップでライフスタイルの理解と再構築が行われます:
クライエントの「初期記憶」を聞き出す(記憶はその人の世界観を映す)
「家族構成」「兄弟順位」「役割」など社会的背景を理解する
「信念」「人間観」「世界観」にどのような歪みや偏りがあるかを検討
支援者との共同作業を通じて、新たなライフスタイルを構築
この過程において、「あなたにも貢献できる場所がある」という再認識が貢献感を育み、クライエントが勇気を持って生活課題に向き合う礎となります。
(2)勇気づけ(Encouragement)の実践
アドラー心理学の実践において最も重要な技法の一つが「勇気づけ」です。これは単なる称賛ではなく、「その人が自分で自分を信じられるようにする支援」です。
評価でなく事実を伝える:「あなたはよくやった」より「今日もあいさつをしていたね」
結果より努力や過程に注目する:「勝ったね」より「毎日練習してたもんね」
相手の自己決定を尊重する:「これをやりなさい」ではなく「君はどうしたい?」
勇気づけは、クライエント自身が「行動の主体者」であるという感覚を呼び覚まし、「貢献できる人間である」という確信につながります。
2. 教育現場における実践
(1)学級経営における役割分担
学校教育では、学級という小さな共同体で「貢献感」を育む仕掛けが極めて重要です。たとえば、日直や係活動といった役割は、一見些細なものに見えても、「自分に任された責任がある」という感覚を子どもに与えます。
掃除当番、給食係など「必要とされる実務」への参加
クラス目標の決定やルールづくりへの「参画型運営」
1対1の関係ではなく、集団の中での「役割と居場所」の確保
こうした体験を通じて、児童・生徒は「自分がクラスに必要とされている」という実感を持ち、勇気を持って発言や行動ができるようになります。
(2)プロジェクト型学習(PBL)と貢献感
近年注目されている「プロジェクト型学習(PBL)」は、児童・生徒がチームで協働しながら課題を解決する学習形式であり、「社会への貢献」を直接的に体験できる仕組みです。
例:
地域のお年寄りへのインタビュー活動
学校周辺のゴミ拾い+ポスター制作で啓発運動
地元産業の紹介動画を制作して発信
これらは、他者や社会のニーズに対して自ら働きかける機会であり、「自分にもできることがある」という肯定的な経験が、子どもたちの“勇気の発達”に直結します。
3. 子育てにおける貢献感の育て方
(1)家庭内の役割を“任せる”
子どもに家庭内で貢献の機会を与えることは、早期から「自己価値感」を育むための最良の方法です。年齢に応じた小さな役割で構いません:
幼児期:おもちゃの片付け、食器並べ
小学生:お風呂掃除、ペットの世話
中学生以上:料理、家計の相談など
重要なのは、親が「自分でやったほうが早い」と手を出さないこと。そして、結果に関係なく「任せたこと」に敬意を払い、「やってくれて助かった」と感謝を示すことです。
(2)承認より“感謝”の文化
アドラー心理学では、「褒める」よりも「感謝する」ことが重要とされます。褒める行為はしばしば上位者が下位者を評価する構図を含むため、自己決定感や貢献感にはつながりにくいことがあります。
「えらいね」→「ありがとう。おかげで助かった」
「すごいね」→「君の工夫でうまくいったね」
このように「行為そのもの」に注目し、感謝を伝えることで、子どもは自らの行為の“社会的意味”を実感し、貢献感が育ちます。
4. 組織・企業内での人材育成
(1)貢献の可視化とフィードバック文化の構築
ビジネスの現場においても、従業員が「貢献感」を感じられるかどうかが、組織の活力や定着率に直結します。上司やチームメンバーが以下の点を意識することで、心理的安全性と自律性が育まれます:
日々の業務が「誰にどのような価値を与えているか」を明示
成果に対する具体的なフィードバック
自分の仕事の社会的意義を定期的に語り合う場の提供
こうした「見えない貢献の可視化」は、社員のモチベーションやエンゲージメントを高め、変化への挑戦=“勇気”を促します。
(2)1on1ミーティングの活用
上司と部下が定期的に行う「1on1ミーティング」は、貢献感と勇気を育てる場として有効です。ただし、その運用には工夫が必要です:
話す時間の主導権は部下に
成果だけでなく、過程や学びに注目
部下の“他者への貢献”を上司が意識して言語化
たとえば、「あのフォローがチームの進行に大きく影響していたよ」と具体的な貢献に触れることで、自分の役割と存在意義を実感でき、自己肯定感と行動の自発性が高まります。
結論:社会をつなぐ「貢献感」の循環構造
貢献感は、支援者が与えるものではなく、「その人自身が役立っていると実感する経験」からしか生まれません。教育・支援・育成の現場では、以下の循環を意図的に設計することが重要です:
他者との関係構築
小さな役割の付与
努力と結果の可視化
フィードバックによる承認
勇気ある行動の発生
このプロセスは一人の自己成長にとどまらず、周囲に勇気を連鎖させる「共同体感覚」の再生へとつながっていきます。
第6章:反証・限界・他理論との対話
アドラー心理学は、個人の内的成長と社会的関係性を統合的に捉えた独自の視座を提供する一方で、他の理論との比較においてその立ち位置や限界を浮き彫りにすることができます。本章では、「人は貢献感を感じ、自分に価値があると思える時にだけ勇気を持つことが出来る」という命題を軸に、ロジャーズ、バンデューラ、マズローなどの主要理論と対話しながら、アドラー心理学の射程と限界を検討します。
1. ロジャーズの来談者中心療法との比較
カール・ロジャーズは、「無条件の肯定的関心(unconditional positive regard)」を中心とする人間中心アプローチを提唱しました。ロジャーズによれば、人間には本来的に「自己実現傾向」が備わっており、それが健全に発揮されるためには、他者からの「受容」「共感」「一致(真正性)」が不可欠だとされます。
共通点:
アドラーと同様、ロジャーズも「人間は他者との関係の中で成長する」という関係志向性を重視している。
共感的理解によりクライエントが自己価値感を取り戻し、成長へと向かう点で、「勇気づけ」と類似の効果がある。
相違点:
アドラーは「共同体への貢献」を個人の目標として外在化するが、ロジャーズは「自己一致」を内在的な目標とする。
貢献感の獲得を他者への関与を通じて生み出すアドラーに対し、ロジャーズは他者からの「受容」を自己成長の契機と見る。
➡ よって、**アドラーは「貢献することで自己価値を見出す」**のに対し、**ロジャーズは「価値ある存在として認められることで自己の成長が促される」**といえる。
2. バンデューラの自己効力感理論との対話
アルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感(self-efficacy)」は、個人が「自分はこの課題をうまく遂行できる」という信念を持てるかどうかが、行動や挑戦に大きく関与するという理論です。
関連点:
貢献感があるとき、自己効力感は高まりやすくなる。たとえば、「過去に役立った経験」→「次も自分ならできる」という連想が生じる。
「成功体験」「代理経験」「言語的説得」「生理的状態」など、バンデューラの提案する要素と、アドラーの「勇気づけ」の構成要素が部分的に重なる。
補完点:
アドラーは社会的文脈の中での勇気や貢献感を重視するが、バンデューラは「課題遂行における自己信頼」を基軸に据えており、よりタスク中心。
➡ アドラーの理論にバンデューラの視点を加えることで、「対人関係の中での貢献感」+「課題達成に対する自己効力感」という、より立体的な“勇気の生成モデル”を構築できる可能性がある。
3. マズローの欲求階層説との照合
アブラハム・マズローの「欲求階層説」は、以下のような五段階の欲求構造を提示します:
生理的欲求
安全の欲求
所属と愛の欲求
承認の欲求
自己実現の欲求
照合と評価:
アドラーの「貢献感」は、マズローの「承認の欲求」「所属の欲求」を包含しつつ、「自己実現」の初動的条件ともいえる。
ただし、アドラーは“人間は貢献したいという目的を持って行動する”とする目的論に基づいており、階層的発達を前提とするマズローの考えとは哲学的に異なる。
➡ マズローの理論は「成長に必要な順序性」を示すが、アドラーは「目的が人を導く」という未来志向の理論であるため、“成長の基盤”より“行動の方向性”に着目する傾向が強い。
4. フロイトとの決定的対立:過去原因論 vs. 未来目的論
アドラーが元来フロイト派に属していたことを考えると、両者の対立は心理学史的に重要です。
決定的な違い:
フロイト:人間の行動は過去のトラウマや無意識的衝動によって規定される(原因論)。
アドラー:人間の行動は、未来の目標や理想によって方向づけられる(目的論)。
勇気と貢献感における相違:
フロイト的立場では、貢献行動は無意識的な“罪悪感の償い”や“超自我の働き”として説明される可能性がある。
アドラーでは、貢献は「人間が持つ根源的な社会的欲求」であり、自由意思と主体的な選択によってなされる行為とみなす。
➡ よって、アドラーの理論は「自己変革が可能である」という人間観に立ち、実践的な教育や支援への応用可能性を広げていると言える。
5. アドラー理論の限界と課題
(1)文化的バイアスの問題
アドラーの理論は「個人の意思と関係性の再構築」に力点を置いていますが、これは個人主義的文化(欧米圏)と親和性が高く、集団主義文化(アジア圏)ではやや適用に慎重さが求められます。たとえば、「貢献」=「自己犠牲」と捉えられる文化では、貢献感がストレス源になりかねません。
(2)過度な目的論による自己責任化のリスク
「すべての行動には目的がある」とするアドラーの立場は、支援に主体性を与える一方で、「失敗も自分の選択である」という見方に結びつきやすく、心理的負担を高める場合もあります。
(3)実証研究の限界
アドラー心理学は臨床現場での経験則に基づく部分が大きく、自己効力感理論や認知行動療法のような実証的データの蓄積がやや乏しいと指摘されています。そのため、教育・福祉分野での体系的な効果測定においては、他理論と統合的に活用されることが望まれます。
結論:理論の対話が開く「勇気」の可能性
アドラー心理学が示す「貢献感が勇気を育む」という命題は、他の心理理論と重なる部分を持ちつつ、独自の価値を放っています。特に「未来志向の目的論」「社会的関係性の重視」「主体性と自由意思の強調」は、現代の多様化社会における心理支援や教育において非常に有効な視座です。
他理論との比較・対話を通じて見えてきたのは、アドラー心理学の実践的強さと、文化的適応・実証性における課題でした。今後は、アドラーの知見を補完しつつ拡張するために、他理論との「協働」が必要であると言えるでしょう。