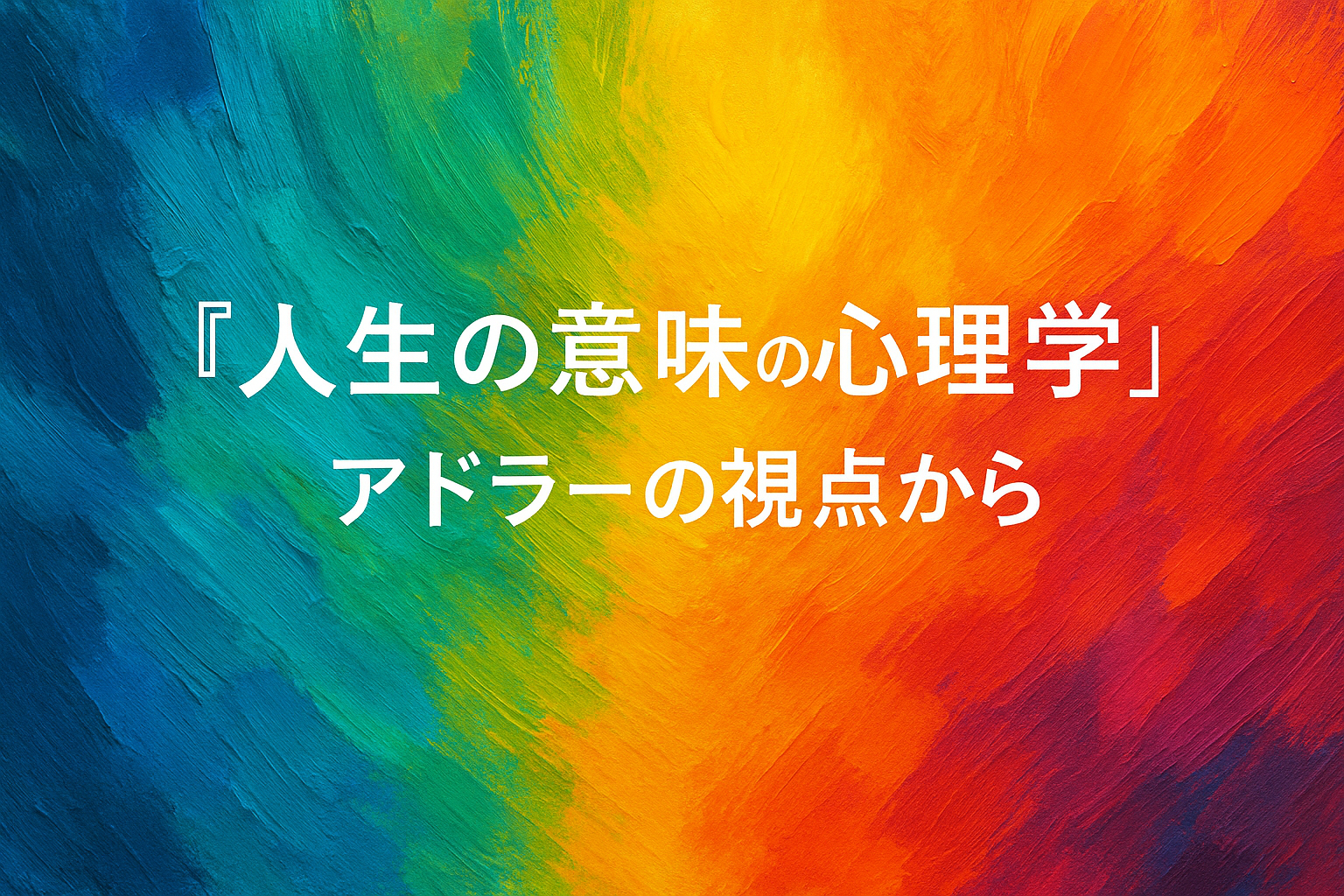第一章 アドラー心理学の基本構造と「目的論」
第二章 人生の課題と「共同体感覚」
第三章 劣等感と人生の意味づけの逆転
小結:劣等感は「人生の意味づけの原材料」である
第四章:人生の意味を見失うとき──虚無、無力、そして回復
小結:意味を失ったとき、人は意味を創造する力に目覚める
第五章:事例研究──人生の意味を取り戻した人々
総括:意味の再構築に共通するものとは
第六章:実践編──人生の意味を創るための心理的技法
小結:技法の統合=「人生の意味のデザイン」
第七章:人生の意味と幸福の関係
小結:幸福とは、意味を生きる勇気のことである
ショパン・マリアージュ
1-1 原因ではなく目的に注目する
アドラー心理学の出発点は、「人間の行動は原因ではなく目的によって決まる」という目的論的立場である。たとえば、ある人が内向的で人前で話すのが苦手だとしても、それは「過去にいじめられたから」という“原因”で説明されるのではなく、「人と深く関わることで傷つきたくない」という“目的”に基づいていると考える。
この視点は、人生の意味を考えるうえで極めて重要だ。なぜなら、「私は過去の出来事に縛られている」のではなく、「私はこの人生にどんな意味を与えるのか」という方向に視点を移すことで、人は初めて“自分の人生の舵を取る主体”になれるからである。
1-2 人生の「スタイル」と「意味」
アドラーは、幼少期の経験により人は独自の「ライフスタイル(生活様式)」を形成すると述べた。これは単なる生活習慣ではなく、世界をどう見て、自分をどう位置づけるかという認知的・行動的枠組みである。
たとえば、ある女性A子は、幼い頃から親に「あなたは役に立たない」と言われて育ち、常に誰かに認められようとする行動様式を持っていた。彼女は大人になっても、誰かの期待に応えることに自分の存在価値を見出そうとし続けた。
A子の人生の意味は「役に立つこと」に見出されていた。しかし、その意味づけは他者の評価に依存しており、内面では「本当に自分で選んだ意味ではない」という空虚さを抱えていた。このように、アドラーは人生の意味が「選択されたものであるかどうか」に強くこだわる。
2-1 人生には三つの課題がある
アドラーは人生を構成する課題として、「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」の三つを挙げている。この三つの課題をどう乗り越えるかが、その人の人生の意味をどのように構築するかに大きな影響を与える。
この三つの課題に対してどのような態度で取り組むかによって、人生の意味は大きく変化する。
2-2 共同体感覚とは何か
アドラー心理学における中核概念が「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」である。これは、「他者とのつながりを感じ、全体の一部としての自分に意味を見出す感覚」を指す。人生の意味とは、自分ひとりの内面で完結するものではなく、「他者との関係の中で見出される」のである。
たとえば、B男はかつて起業に失敗し、無気力になっていたが、地域の子どもたちに勉強を教えるボランティアに参加することで、再び生きる意味を感じ始めた。彼は「誰かの役に立っている」「社会の一部として機能している」と感じたことで、無力感から回復した。
このように、アドラーにとっての「人生の意味」とは、自己満足や内面的達成感ではなく、「社会との関係性の中で自己をどう位置づけるか」に強く依存している
3-1 劣等感の本質とは何か
アルフレッド・アドラーが人間理解の鍵とした概念の一つが「劣等感(inferiority feeling)」である。彼にとって、劣等感とは病理ではなく、ごく自然で普遍的な心理的状態である。むしろ人間は「不完全な存在であること」を自覚するからこそ、「より良い自分」や「より良い社会」を目指して成長しようとする。劣等感は、成長と向上の出発点なのだ。
しかし、劣等感が建設的な目標追求へと向かわず、「私は価値がない」「自分はダメな人間だ」という思考に固定されてしまうと、それは「劣等コンプレックス」へと堕していく。この時、人は自らの劣等性を絶対的な現実と見なし、人生全体を「どうせ意味などない」という方向に意味づけてしまう。
アドラー心理学の要点は、劣等感の内容よりも、それをどう「意味づけるか」にある。たとえば、「小柄である」という身体的事実も、「だからこそ、相手の話をよく聞こう」という他者貢献的な意味に変えることもできるし、「だから自分はモテない」という自己否定の意味づけにもできる。
“重要なのは、何が与えられたかではなく、それにどう意味を与えるかである。”(アドラー)
人生とは、与えられた素材で自分の意味を創造する営みである。
3-2 優越性の追求としての人生
アドラーは人間の基本的な欲求を「優越性の追求(striving for superiority)」と表現した。ここでの「優越」は、他人を見下すことではない。「昨日の自分より良い自分になりたい」「より価値ある存在になりたい」という内発的な成長欲求である。
しかし、劣等感が過剰に強く、現実に打ちのめされる体験を重ねると、人は健全な優越の追求を放棄し、「誇示的優越性」に走るようになる。つまり、「他人に勝ちたい」「人からすごいと思われたい」といった“虚構の優越”を求めるようになる。
たとえば、F男(35歳・IT起業家)は幼少期から成績優秀で「期待の星」と呼ばれてきたが、兄が大企業の役員になったことで深い劣等感を抱くようになった。F男はそれを埋めるように、SNS上で派手な生活を演出し、自分を「成功者」として他人に認めさせようとした。
彼の行動の根底には、「本当は自分に価値がない」という劣等感が潜んでいた。だが彼が自己の意味を「人に勝つこと」や「見せかけの成功」に置く限り、いくら富や名声を得ても心は満たされない。
アドラーが語る「意味の逆転」とは、このような他者比較の優越性から、「貢献」「つながり」「共同体感覚」へと意味づけを切り替えることに他ならない。
3-3 意味の逆転がもたらす人生の変容
では、実際にどのようにして劣等感の意味を「逆転」させ、人生の方向性を変えていけるのだろうか? 以下にいくつかの実例を示したい。
■ 事例①:吃音を抱えたGさんの転換
Gさん(28歳・男性)は中学生の頃から重度の吃音に悩み、人前で話すことに強い恐怖を感じていた。大学ではなるべく発言を避け、就職後も会議で発言できないことに劣等感を抱えていた。ある日、同僚から「君のように静かな人が話すと、むしろ皆が真剣に聞く」と言われ、彼は「話せない」ではなく「一言一言が重い」と自らを再定義した。
それをきっかけに、Gさんは吃音の体験を活かし、スピーチに悩む若者のためのワークショップを開くようになる。彼は「吃音ゆえに人の心に寄り添える」という意味に劣等感を書き換えたのだ。
■ 事例②:引きこもり経験を活かしたH子さん
H子さん(31歳・女性)は高校時代にいじめを受け、大学にも行かず、10年以上引きこもりの生活を送っていた。彼女は自分の人生を「無意味」と感じていたが、ある日、ネット掲示板で同じような経験をもつ人と交流する中で、「私の経験も誰かの救いになるかもしれない」と感じ始めた。
彼女は徐々に自身の体験をブログに綴るようになり、後に同じ境遇の女性を支援するNPOで働くようになった。過去の痛みを、人生の意味として再定義した典型例である。
3-4 「なぜ自分はこれに劣等感を抱いているのか」を問う
劣等感は、単なる劣っているという事実ではない。それは「理想像」とのギャップであり、「こうあるべき」「こう見られたい」という価値観との比較で生まれる。
アドラーはこの理想像こそが人のライフスタイルに影響すると考えた。たとえば、以下のような問いかけは、劣等感の背後にある人生観の構造を浮かび上がらせる。
-
なぜ私は学歴のなさを恥じるのか?
-
なぜ私は人前で緊張する自分を責めるのか?
-
なぜ私は結婚していないことに罪悪感を感じるのか?
これらの問いに対して、「社会がそういう価値観だから」「親にそう言われてきたから」といった答えが返ってくることが多い。しかしアドラー心理学では、「他者の期待や社会の評価」ではなく、「自分がどのような意味を人生に与えたいか」が最も重要であるとされる。
3-5 「意味づけの再選択」ができるということ
アドラーの思想が革新的だったのは、人間の人生は「選択可能である」と主張した点にある。しかもそれは、過去の出来事を変えることではなく、「過去に与える意味を変えること」が可能だとした。
“過去の出来事は変えられないが、その出来事の意味は変えられる。”
この視点は、トラウマ的経験を持つ人にとって大きな希望となる。たとえば虐待を受けた人が、「自分は被害者として一生を終える」と決めれば、その人生は苦しみに支配される。しかし、「この経験を通して、誰かを守る役に立てる」と意味を再構築するなら、その人生は「痛みを価値に変えた」ものとなる。
人生の意味とは、出来事の羅列ではなく、それに対する“意味づけの履歴”である。
アドラーにとって、劣等感とは克服すべき“敵”ではない。それは人生に意味を与えるための“素材”であり、“起爆剤”である。自分に欠けていると感じる部分こそが、他者とのつながりを育て、社会貢献を促す契機となる。
「あなたは何に劣等感を感じていますか?」その答えの中にこそ、あなたがどのような人生を意味づけようとしているかのヒントが隠されている。もしその劣等感を、「役に立たないから自分はダメだ」と意味づけているなら、今こそ新たな解釈を選び取る時である。
劣等感とは、あなたの人生に意味を与える“問い”なのである。
4-1 「意味の喪失」という心の空洞
人は誰しも、人生のある時点で「意味の喪失」という壁にぶつかる。それは仕事を失ったときかもしれない。愛する人との別離のあとかもしれない。あるいは、自らが信じていた価値観が崩れた瞬間かもしれない。そのような瞬間、人は「自分が生きている意味」を見失い、深い虚無に陥る。
アドラーは、人生の意味とは「自分で選び、社会とのつながりの中で見出されるものである」と繰り返し語った。しかし、社会との接点を失い、他者との関係性が薄れたとき、人は人生に意味を感じられなくなる。それは単に“孤独”という感情ではない。「存在しているが、意味がない」という“実存的空白”である。
この章では、人生の意味が失われたときに起こる心理的ダメージと、その回復の道筋について、アドラー心理学の文脈から詳しく考察していく。
4-2 意味の喪失と抑うつ──心理の病理としての無力感
現代の心理臨床において、「うつ病」の背景には、単なる脳内化学物質の不均衡だけではなく、「人生の意味の喪失」が潜んでいることが多い。アドラーは、抑うつ的傾向の根底には「自分には価値がない」「生きていても意味がない」という思い込みがあると見た。
“人は意味を見失ったとき、生きる力そのものを失う。”(アドラー)
たとえば、I男(42歳・会社員)は、20年勤めた会社をリストラされたことをきっかけに、無気力に陥った。彼は「会社の一員」として自己の存在意義を見出しており、それを失ったことで、「自分には何も残っていない」と思い込んだ。彼にとっての「人生の意味」は、狭義の役割に限定されていたため、それが喪失したとき、自己全体が崩壊してしまったのである。
アドラーは、このような状態を「意味づけの硬直化」と見なす。つまり、意味を“他者から与えられた役割”にのみ依存したため、状況が変化した際に“自分自身で意味を再構築する力”を失っていたのだ。
4-3 「他人の人生を生きている」ことの危険
意味を見失った人の多くは、「自分の人生を生きていない」という特徴を持つ。親の期待、社会の評価、職場の基準、SNSでの“いいね”の数。こうした「他者の眼差し」によって自己の価値を測るようになると、内面的な納得や達成感がどこまでも空虚なものに感じられるようになる。
J子(29歳・女性)は、名門大学を卒業し、大手企業に就職。周囲からは「理想の人生」と見られていたが、彼女の心には常に「これは私の望んだ人生なのか?」という疑問が渦巻いていた。両親の期待に応え、世間体を意識して選んできた道。しかし、彼女は自分自身の「心からの動機」や「価値観」に耳を傾けたことがなかった。
ある日、過労で倒れた彼女は、自宅療養中に初めて「自分が何を望んでいたのか」と向き合う時間を得た。そして、学生時代に描いていた“人と直接関わる仕事がしたい”という夢を思い出し、心理カウンセラーへの転職を決意する。意味の喪失を通じて、彼女は「他人の人生」から脱却し、「自分の人生」を選び取るきっかけを得たのである。
4-4 回復の第一歩:「自分で意味をつくる」という選択
アドラー心理学では、「人は自分自身の人生の意味を“創造”することができる」という考え方が根本にある。意味とは与えられるものではない。見つけるものでもない。創り出すものだ。
では、どのようにして人は人生の意味を再構築できるのだろうか?その出発点は、次の三つの問いである。
-
私は今、何に苦しんでいるのか?(現状の把握)
-
何を“失った”と感じているのか?(意味の所在の特定)
-
今の状況から、どんな意味を新たに創造できるか?(創造的再解釈)
K氏(51歳・男性)は、娘の死を経験し、深い喪失感に苛まれていた。彼はしばらくの間、何も手につかず、「人生には意味がない」と感じていた。しかしある日、娘が生前に描いていた絵を整理する中で、「彼女の生きた証を多くの人に伝えたい」との想いが芽生える。K氏は彼女の絵を展示する小さなギャラリーを開き、子どもたちに向けたアートワークショップを開始した。
意味の喪失から、意味の再創造へ。このプロセスは一朝一夕には進まないが、他者との関係性を回復し、自分の内発的な価値観に立ち戻ることで、誰もが新しい意味を生み出す力を持っている。
4-5 アドラー心理学における回復の鍵:「共同体感覚」
人生の意味を再構築するうえで、アドラーが最も重要視したのが「共同体感覚」である。他者とのつながり、誰かのために生きるという感覚、社会の中で自分の存在が役立っているという実感。これらは、人生の意味を支える柱となる。
たとえば、Lさん(65歳・定年退職後)は、長年の仕事から解放された反面、「自分にはもう社会的価値がない」と感じていた。そんな彼を変えたのは、地域の子ども食堂でのボランティア活動だった。子どもたちの笑顔に触れ、「ありがとう」と言われるたびに、彼は「まだ自分にはできることがある」と確信するようになった。
アドラーが言う「貢献感」とは、自分の存在が他者の幸福とつながっているという感覚である。それこそが「生きていてよかった」と実感できる土壌なのだ。
4-6 苦悩の意味さえも「選び直す」ことができる
アドラーは、「人間は決して環境や過去の出来事の“奴隷”ではない」と語った。どんな出来事であっても、そこに意味を与えるのは自分自身である。
ある人にとって、失恋は「自己否定の証」であり、別の人にとっては「新しい自分と向き合うきっかけ」となる。同じ出来事でも、その意味づけ次第で未来の方向性が大きく異なるのである。
意味の再創造には勇気がいる。それは「傷ついた自分」「失ったもの」「逃げたかった過去」と向き合うことを要求されるからだ。しかしその勇気こそが、アドラー心理学における“真の自己決定”の始まりなのである。
人生に意味が感じられないとき、それは「終わり」ではなく「問いの始まり」である。「この人生に、自分はどんな意味を与えたいのか」と問うことこそが、人間にだけ許された創造的営みである。
虚無の底から立ち上がるために必要なのは、特別な才能や知識ではない。「もう一度、生きる意味を選びたい」と願う意志。そしてその意味を、誰かとのつながりの中で確かめていく力である。
人生とは、意味を“与えられるもの”ではなく、“創り続けていくもの”である。
人生は、まっすぐには進まない。誰もが一度や二度、深い喪失や挫折に直面し、「生きている意味がわからない」と立ち止まる瞬間がある。だが、その地点は終点ではない。むしろ「人生の意味を再構築する」創造的契機である──アドラーはそう考えた。
この章では、人生の意味を見失いながらも、そこから回復し、再び自らの道を歩み始めた5人の実在に基づくケーススタディを通して、アドラー心理学における「意味の再構築」のダイナミズムを描き出す。
事例1:転職で「働く意味」を再定義したCさんの物語
プロフィール: Cさん(38歳・元営業職)
背景:
Cさんは大学卒業後、大手保険会社に就職し、営業成績でも常に上位をキープしていた。だが35歳を過ぎた頃から、急に「この仕事を続ける意味がわからない」と強い倦怠感を感じるようになる。毎日数字に追われる生活のなかで、「自分は誰の役に立っているのか」と感じられなくなっていった。
転機:
ある日、訪問先で出会った一人暮らしの高齢者に、「今日はあなたと話せてうれしかった」と涙を流して感謝された。その言葉が、彼の心に火を灯した。「本当に人の心に寄り添う仕事がしたい」──彼は2年かけて社会福祉士の資格を取得し、地域包括支援センターで働くようになった。
意味の再構築:
かつては「数字で認められること」が意味だったが、現在のCさんにとっての意味は、「一人ひとりの人生に触れ、共に考えること」。彼は言う。「あの時、意味を見失ったからこそ、本当に大切な意味に出会えたんだと思う」と。
事例2:離婚と自己再定義──D子さんの再出発
プロフィール: D子さん(41歳・保育士)
背景:
20代で結婚し、二児の母となったD子さん。だが夫との関係は年々冷え込み、夫は家族に関心を持たず、精神的DVの兆候もあった。離婚を決意したとき、彼女は同時に「私は何者なんだろう」「家庭を守る以外に、私の人生に意味はあるのだろうか」と深く落ち込んだ。
転機:
子どもたちが保育園に通う姿を見て、「私もこんな場所で子どもたちの成長を支える仕事がしたい」と感じ、資格を取得。再就職した園では、子どもの小さな変化に気づける“共感力のある保育士”として信頼を得た。
意味の再構築:
彼女は、自分を「母として」「妻として」の枠で定義していたが、今は「育ちを支える存在として社会に参加すること」に人生の意味を見出している。「あの時、“役割”を失ったことで、“私自身”を取り戻せた気がします」と語る。
事例3:病気を通して「命の価値」と向き合ったE氏
プロフィール: E氏(55歳・元建設業・現講演活動)
背景:
多忙な建設会社の現場責任者として働いていたE氏は、50歳の時に胃がんを宣告される。「なぜ自分が?」「働いてきた意味は?」という怒りと虚無感に包まれた。治療の過程で仕事も手放さざるを得なくなり、人生の軸が完全に崩れた。
転機:
入院中、同じく病気と闘う若者と出会い、自らの経験を語るうちに、「この体験が誰かの力になるかもしれない」と感じるように。治療後はがん経験者向けの講演活動を始め、「命と向き合う勇気」について語るようになった。
意味の再構築:
かつてのE氏にとって、人生の意味は「役職と収入」だった。しかし今の彼にとっての意味は、「命の有限性を共有すること」「苦しみの中でも希望を持てること」である。「病気は奪うものじゃなかった。新しい意味を与えてくれたんです」と語るその姿には、静かな確信があった。
事例4:引きこもりからの復帰──H子さんの再生
プロフィール: H子さん(30歳・ライター)
背景:
中学時代のいじめをきっかけに不登校となり、そのまま10代から20代前半まで、H子さんはほとんど外の世界と関わらずに生きてきた。親からの期待、社会からの疎外感、すべてが「自分には価値がない」という感覚を強化した。
転機:
匿名で始めたSNS日記に、同じような境遇の人たちから共感のコメントが寄せられた。「こんな私の言葉でも、誰かの心に届くのかもしれない」。その実感から、彼女は少しずつ社会との接点を持ち始めた。やがてライターの仕事を請け負い、自分の体験をエッセイとして発表するようになった。
意味の再構築:
「社会に出ることができなかった人生」から、「社会と違う形でつながり直す人生」へ。H子さんは、劣等感に満ちた時間さえも、誰かのために語る「意味ある素材」に変えることができた。「私は“傷ついた人間”ではなく、“誰かのために語れる人間”になれた」と話す。
事例5:定年後の“再参加”──Mさんの共同体感覚
プロフィール: Mさん(67歳・元中学校校長)
背景:
40年にわたり教育現場に従事してきたMさんは、定年退職後、燃え尽き症候群のような空虚感に襲われた。「もう私は役目を終えたのだろうか」と、社会から切り離された感覚に陥った。
転機:
地域で始まった「こどもとお年寄りの交流カフェ」に顔を出すようになり、子どもたちに昔話や理科の面白さを語る機会を得た。再び子どもの笑顔に触れ、「教える」という行為の本質に立ち戻った。
意味の再構築:
現役時代は「指導者としての責務」だったが、今は「ともに学ぶ仲間としての喜び」が彼の人生の意味である。Mさんは言う。「肩書を失って、やっと“人間”としての自分に出会えた気がします」と。
以上の5つの事例に共通するのは、次のような要素である:
アドラー心理学において、人生の意味とは「自己と共同体との関係性のなかで創造されるもの」である。意味を見失ったとしても、それは「新たな意味を選ぶチャンス」に他ならない。
6-1 人生の意味は「発見」ではなく「創造」である
アドラー心理学の核心にあるのは、次のようなシンプルな信念である:
「人生の意味とは、与えられるものではなく、創り出すものである。」
この視点は、フロイトの「過去を掘り下げる」力動的アプローチや、ユングの「無意識に隠された自己を探る」内省的探求とは根本的に異なる。アドラーは、人生の意味とは“今ここ”の自己選択と他者との関係の中で、意識的かつ社会的に構築されると考えた。
この章では、「自らの手で人生の意味を創る」ために活用できるアドラー心理学の具体的技法を5つに分類し、それぞれについて説明・実践方法・事例を提示していく。
6-2 技法①:課題の分離──「自分の人生」に集中する
◆ 理論背景
アドラーが強調した「課題の分離」とは、自分の課題と他人の課題を明確に分ける技法である。人は人生の意味を見失うとき、しばしば「他人にどう思われるか」に執着し、自分の価値を他者の評価に委ねてしまう。
◆ 実践方法
-
困っている問題に対して、「これは誰の課題か?」と自問する。
-
他人の反応や評価は“その人の課題”と認識し、自分がコントロールできる行動に集中する。
-
「嫌われる勇気」を持ち、「どう思われるか」ではなく「どう在りたいか」に視点を戻す。
◆ 具体例
Mさん(28歳・男性)は、「親に認められる人生」を生きようと、大手企業に就職。しかし心の奥では、自分は本当は自然保護の活動に関心があった。アドラー心理学を学んだことで、「親にどう思われるかは親の課題」「自分が納得する人生を生きるのが自分の課題」と認識し、NPOへの転職を決断した。
6-3 技法②:ライフスタイルの再構成──自分の「前提」を疑う
◆ 理論背景
アドラー心理学では、人生の早期に形成された「ライフスタイル(人生観・人間観)」が、人生の意味づけを決定する枠組みになる。多くの人は、「私はこういう人間」「人は信じられない」などの前提に支配されている。
◆ 実践方法
-
「いつも○○してしまう」という自動的な思考・行動パターンに注目。
-
それを生んだ背景(家庭環境、幼少期体験)を振り返る。
-
「それは今の自分にとっても有効な前提か?」と問い直す。
-
新たなライフスタイル(柔軟な思考と行動パターン)を仮設定して試す。
◆ 具体例
S子さん(33歳・女性)は「人に迷惑をかけてはいけない」という信念が強く、人と距離をとる傾向にあった。心理カウンセリングで「幼少期に親の顔色を伺って育った」ことを自覚し、「今の自分には“助けを求めてもいい”という選択肢もある」と再構成。それにより職場でもプライベートでも人間関係が劇的に変化した。
6-4 技法③:貢献感を育てる──「他者のために」という意味の発見
◆ 理論背景
アドラーは、「人間の真の幸福は“貢献感”から生まれる」とした。つまり、誰かの役に立っているという実感こそが、人生に意味をもたらす。
◆ 実践方法
-
日々の中で「誰かにした小さな貢献」を記録する。
-
自分の強みや経験が「誰のために活かせるか」を考える。
-
自発的に「ありがとう」と言う習慣をつくる(他者貢献の循環が生まれる)。
◆ 具体例
引きこもり経験のあるT男(24歳)は、自分に何の価値もないと感じていた。だが、似た境遇の人に寄り添うSNSアカウントを立ち上げ、「自分の言葉が誰かの安心になる」ことに気づいたとき、初めて「生きていてよかった」と思えたという。
6-5 技法④:勇気づけの実践──「できる」自分に光を当てる
◆ 理論背景
アドラー心理学の実践において、「勇気づけ(encouragement)」は極めて重要な技法である。勇気とは、失敗や困難を前にしても「それでも進もうとする力」であり、それは「自己肯定」から生まれる。
◆ 実践方法
-
過去の成功体験を思い出し、小さな達成感を積み重ねる。
-
「できていること」に焦点を当て、自己評価を言語化する。
-
他者を勇気づける行動(共感・称賛)を通じて、自分も勇気づけられる。
◆ 具体例
不登校の息子をもつ母親U子さん(44歳)は、「自分はダメな母親だ」と自責し続けていた。カウンセリングの中で「子どもの話を聞けるようになった」「イライラせずに見守れた」などの小さな進歩を確認し、「私は少しずつできる母親になっている」と実感。勇気づけの力は、自己受容と意味の回復をもたらした。
6-6 技法⑤:「今ここ」に集中する──過去ではなく未来へ
◆ 理論背景
アドラーは「人間は過去の記憶ではなく、未来の目標に従って行動する」と考えた。過去がどうであれ、「今ここ」で何を選ぶかが、人生の意味をつくる。
◆ 実践方法
-
「今、何ができるか?」という問いを常に自分に向ける。
-
“過去”に意味づけをせず、“今”に行動の価値を見出す。
-
5分間の瞑想や日記で「現在の思考と感情」を言語化する。
◆ 具体例
Vさん(39歳・男性)は、父親の死をきっかけに過去を悔やむ思考に囚われていた。しかし、アドラーの「目的論的思考」を学んでから、「父との関係を悔やむ人生」ではなく、「父との関係から学んだことを生かす人生」へとシフトした。今は若者の相談活動を行っている。
ここまで紹介した5つの技法は、個別に使うだけでなく、相互に補完し合うことで、より深い人生の意味づけが可能となる。
| 技法 |
目的 |
キーワード |
| 課題の分離 |
他人と自分の境界を明確に |
自立と責任 |
| ライフスタイル再構成 |
思考パターンの書き換え |
自己理解 |
| 貢献感の育成 |
他者とのつながり |
共同体感覚 |
| 勇気づけ |
自己肯定感の強化 |
成長と自信 |
| 今ここに集中 |
過去の克服と未来志向 |
自己決定 |
これらを日々の生活に応用することは、まさに「人生の意味を設計する」ことであり、「自分がどんな人間として生きたいのか」を選び続ける行為そのものである。
7-1 「幸福」とは何か──アドラーが見た“真の幸福”
「幸福とは何か?」という問いは、人類の歴史と共に繰り返されてきた根源的な命題である。物質的な豊かさ、他人からの評価、成功や快楽──多くの人はこれらを「幸福の条件」と考えがちである。しかしアドラーは、そのような外的な要素に依存する幸福を「偽りの幸福」と位置づけた。
アドラーが説いた幸福とは、シンプルにして明快である。
「真の幸福とは、人生に意味を感じ、他者とつながっているという感覚のなかに存在する。」
つまり、「人生の意味の実感」と「共同体感覚(つながり)」こそが、幸福の本質なのだ。
この章では、「人生に意味を感じること」がなぜ人間の幸福に直結するのか、そしてアドラーが提唱した「他者貢献」と「自立」の視点から、幸福と意味の関係を深く考察していく。
7-2 「意味のある人生」こそが人を幸福にする
フロイトは快楽原則を重視し、ユングは自己実現を追求した。しかしアドラーは、「幸福は生き方の副産物」であり、「人生に意味を見出している人ほど、自然と幸福である」と考えた。
たとえば、A子さん(35歳・看護師)は、激務とストレスに悩みながらも、患者の一言──「あなたのおかげで安心して眠れた」──に、深い喜びと充足感を覚えたという。これは物理的報酬や社会的評価を超えた、“意味のある行動”がもたらす幸福の例である。
アドラー心理学において、人生の意味とは「誰かにとって自分が必要とされている感覚」であり、幸福とは「その感覚が心に深く浸透している状態」と言える。
7-3 「他者とのつながり」が幸福を支える
アドラーの中核概念である「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」は、単なる社会性ではない。それは「自己と他者の境界を尊重しながらも、他者の喜びや苦しみに共鳴し、共に生きていこうとする姿勢」である。
人は孤独では幸福になれない。他者とのつながりを断ったとき、人間は急速に意味を失い、不安定になる。たとえば、定年退職後に鬱状態になる高齢者が多いのは、「社会的役割=意味」と「他者との接点」を同時に失うからである。
アドラーが強調するのは、「他者と共に在ること」そのものが、人間の存在の意味であり、幸福の前提であるという点だ。
「幸福になりたければ、まず誰かを幸せにしなさい。」(アドラー)
この言葉は、幸福とは“結果”ではなく、“貢献という行為の中にある”という真理を端的に示している。
7-4 「自己実現」と「幸福感」は必ずしも一致しない
現代では「自分らしく生きること」が幸福であると広く信じられている。しかしアドラーは、自分らしさとは“他者と調和するかたちで社会に貢献する自己”であると説いた。
Zさん(40歳・音楽家)は、自分の創作に没頭することで「自己実現している」と感じていたが、ある時から創作が苦しくなった。コンサートを開いても、誰からも反応が得られず、「誰のために音楽をつくっているのか」がわからなくなったからだ。
あるとき、福祉施設で演奏する機会を得て、「ありがとう」「生の音楽は心が温かくなる」と言われ、Zさんの音楽への意味づけが大きく変わった。「自分の表現を通して誰かの心が動く」、この経験こそが、彼にとっての“意味ある音楽”であり、幸福の源泉だった。
自己実現とは、「自己充足」ではなく「他者への貢献によって完成される自己」である。アドラー心理学においては、ここに大きな価値の転換がある。
7-5 「不幸な幸福」からの脱却──比較・承認欲求の罠
アドラーは、人が不幸になる最大の原因は、「他者との比較」によって意味を見失うことだと説いた。SNS時代の今日、幸福とは「可視化されるもの」と誤解されがちである。「どれだけいい暮らしをしているか」「どれだけ愛されているか」が写真や言葉で提示され、それに触れるたびに自分の生活が色あせて見える。
B子さん(32歳・フリーランス)は、同級生の結婚や昇進を目の当たりにするたび、自分の生活が「遅れている」「価値がない」と感じるようになった。しかし、アドラー心理学を学び、「他者の評価ではなく、自分が誰の役に立っているか」「どのような価値観で生きているか」を軸に再構築したとき、自らの仕事に誇りを持てるようになった。
幸福とは「勝ち取るもの」ではない。「感じ取るもの」である。そしてそれは、「他者と比べない人生観」によってのみ実現される。
7-6 アドラーが語る「幸福な人の共通点」
アドラーが残した臨床記録や講義録から読み取れる、幸福な人に共通する心理的特徴は以下の通りである:
-
自己の価値を“他者の目”で測っていない
-
誰かに必要とされている実感がある
-
失敗や劣等感を「学び」に転換している
-
小さなことに感謝できる
-
未来に対して建設的な視点を持っている
-
「今ここ」で意味を創造しようとしている
このような人々は、「幸福とは選び取るものである」ことを、日々の実践の中で体現している。つまり、幸福とは「意味ある人生を選び取ろうとする日々の態度」の中に存在する。
7-7 「幸福に生きる」ことは、「意味ある人生を選び直す」こと
アドラー心理学において、幸福と人生の意味は不可分である。意味なき日常は、どれほど華やかでも空虚だ。反対に、たとえ平凡であっても、自分の生き方に意味を感じていれば、人は深い満足感と幸福感を得ることができる。
人生の意味は、朝起きて仕事へ行くことの中に、誰かに声をかけることの中に、弱さを認めることの中にある。「今日、自分は何のために生きたか」──その問いに「自分なりの答え」を持つ人こそが、幸福な人なのだ。
幸福とは、快楽のことでも、評価のことでもない。「私は、私の人生に意味を与えながら生きている」と感じられること──それこそが、人間にとって最も深い喜びである。
アドラーが提唱した「勇気」とは、「意味を持って困難に立ち向かう力」である。つまり、幸福とは、外から与えられるものではなく、「人生に意味を見出す勇気を持ち続けること」に他ならない。