年収が高くても選ばれない?婚活男性が気づ……
結婚相談所クインテット恵(奈良県)
2025.07.02
ショパン・マリアージュ
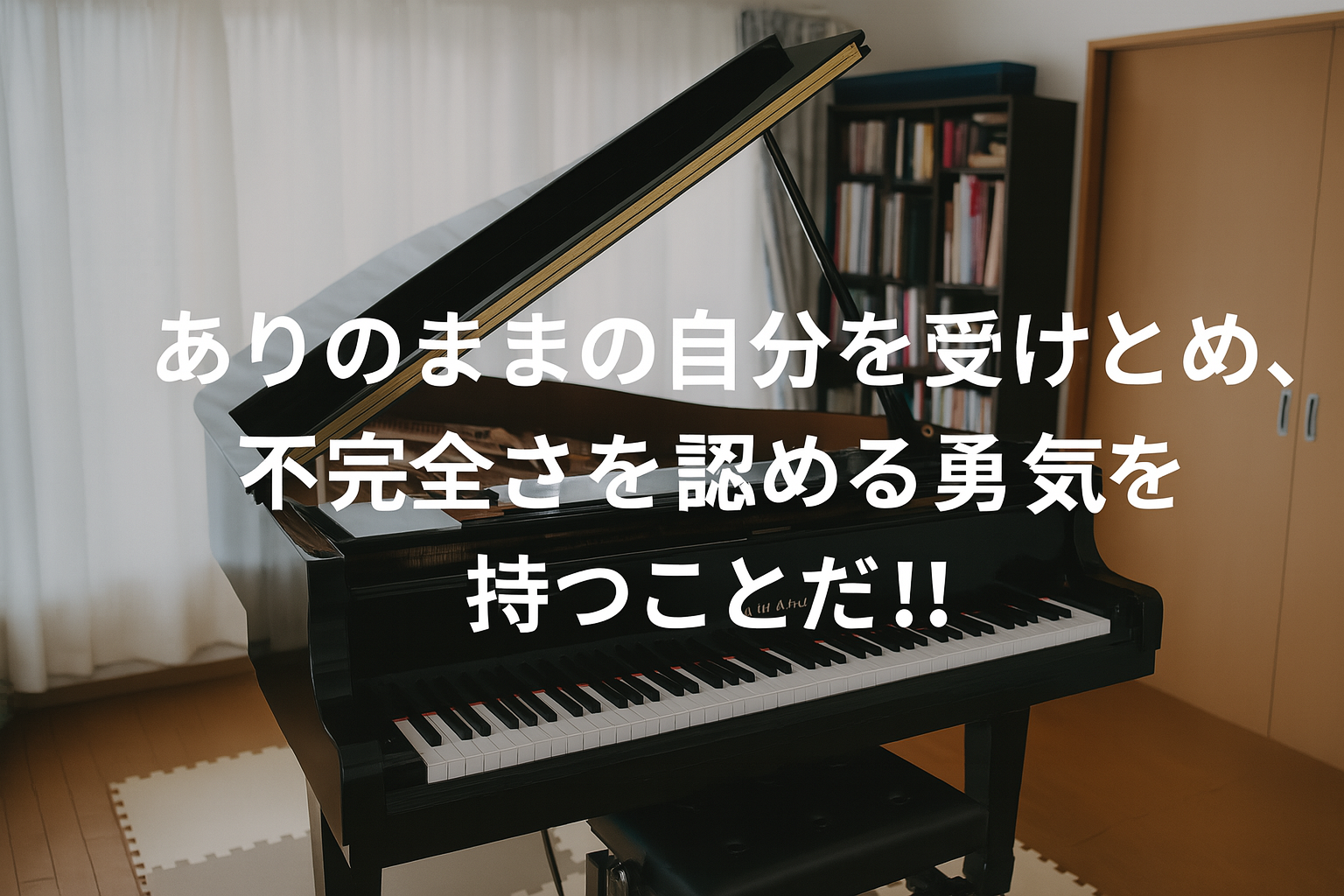
第1章:他人からの評価に左右される心の構造
1-1. 劣等と優越性――根源的な心理の構図
アドラー心理学では、人は生まれながらに「劣等感」を持っているとされます。身長や知能、容姿、才能など、何かしら他と比べて自分に感じる不足は、多くの場合において本人の成長の源となります。重要なのは、誰かとの比較で自己価値を見出すのではなく、より良い自分になるという“自己超越”へ向かう姿勢です。そして、他者との比較にとらわれると、「他人がどう評価するか」が人生の指針になりがちです。
1-2. 「評価」という名の鎖
事例①:大学生の里奈さん(仮名)
里奈さんは絵描き志望の大学生。当初、友人にも才能を認められ、賞や展示にも挑戦していましたが、ある日尊敬する教授に「もう少し独自性がほしい」と言われて以来、次第に自分の作風を他人の好みに合わせて調整するようになりました。
内面の葛藤:
「評価されたい」という欲求が、「自分の好きを突き詰める」創作より優先されるようになった。
結果として作品の質が低下。評価も得られず、苦しむ日々が続く。
自分自身が「他人の評価に依存している」事実にも気付かず、自己嫌悪が深まっていきます。
分析:
里奈さんのように他人の評価を重視しすぎると、「誰かに良く思われたい」が先立ってしまい、自分の価値観や感性が揺らいでしまいます。アドラー心理学では、自己決定性の喪失、すなわち「人生のレールを他人に任せている」状態として理解されます。
1-3. 所属の欲求と評価の錯覚
「周囲に受け入れられたい」「相互に信頼できる関係を構築したい」—こうした所属欲求は自然で正当です。しかし、もしそれが「あの人に嫌われたら」「評価が下がったら」への恐怖に変わってしまうと、他人の顔色ばかり気にしてしまう状態に陥ります。
事例②:会社員・健太郎さん(仮名)
入社2年目の健太郎さんは、上司や先輩に気に入られたいあまり、自分の意見を出すことを極度に怖がるようになっていました。「批判されたらどうしよう…」が先立つことで発言の機会を失い、特に自分の得意分野である分析や提案の質が評価されるチャンスも減っていました。
心理構造:
他人の眼差しを恐れる心が、自己表出性を封じてしまう。
所属と貢献をつなぎ直したい願いが、リスク回避へとすり替わる。
第2章:勇気づけとしての「ありのままの自己」受容
「ありのまま」を受け入れるという勇気
「そんな自分じゃだめだ」「もっとできる人間にならなくては」——誰もが一度は、そんな自己否定の声を心の中で聞いたことがあるでしょう。私たちはいつの間にか、「他人に評価される自分」でなければ価値がないと信じ込み、内側にある“本当の自分”を否定する癖がついてしまっています。
しかしアドラー心理学では、このような思考は「勇気の欠如」としてとらえられます。勇気とは、完璧ではない自分をも受け入れながら、今ここでできる貢献を模索しようとする姿勢です。自分の欠点も含めて「ありのまま」を認めることこそが、人が人生の主導権を取り戻し、幸福へと進む第一歩となるのです。
アドラーが繰り返し述べた「勇気づけ(Encouragement)」は、まさにこの“自己受容”への橋渡しとして機能します。
勇気づけの本質:評価ではなく共感と承認
勇気づけとは、「あなたには価値がある」「あなたには貢献する力がある」とメッセージを届けるコミュニケーションです。ここで重要なのは、評価とは違い「条件付きの承認」ではないということです。
例えば、仕事で失敗をした部下に対し、上司がこう言ったとします:
「よくやったね、結果は出なかったけど君の姿勢は素晴らしかった」
「どうしてこんなミスをしたんだ?もう少し考えて行動してくれ」
前者は勇気づけ、後者は勇気くじきです。結果ではなく、行動や努力を承認することで、相手が「自分にはまだできることがある」と感じるように促しているのです。
自分自身への勇気づけ
アドラー心理学では、他者への勇気づけだけでなく、「自分への勇気づけ」も重視されます。つまり、自分自身に対しても次のような姿勢を取ることです:
「今日の自分、少し落ち込んでいるけど、それも自分なんだ」
「完璧にこなせなくても、一歩前に進めただけでも価値がある」
これは、いわゆる“ポジティブ思考”とは異なります。無理に明るく考えるのではなく、「ありのままの感情・現実を認めながら、それでも歩もうとする意志」を支えるのが勇気づけなのです。
具体事例①:転職に悩む女性のケース
佐知子さん(仮名・32歳)は、大手企業で10年間勤務してきましたが、慢性的なストレスややりがいの喪失から転職を考えていました。しかし「今辞めたら失敗だと思われるのではないか」「親も心配するだろう」という思いが頭をよぎり、なかなか行動に踏み出せずにいました。
カウンセリングで彼女が語った言葉:
「私はずっと“できる人”でなきゃいけないと思ってきました。でも、本当はもう限界で…。けれど、弱音を吐くのは“できない自分”を認めるようで怖いんです」
ここでカウンセラーが行ったのが、「不完全さの受容」と「勇気づけ」です。
「“できない自分”を認めることは、逃げではなく、次に進むための一歩ですよ」
「あなたが苦しいと思えるのは、自分の感性に正直でいようとする証拠なんです」
彼女は「こんな自分でもいいのかもしれない」と少しずつ感じ始め、半年後、自分の価値観に合った仕事へ転職。完璧な道ではなく、「自分が納得できる道」を選びました。
具体事例②:発達障害のある少年と母親
小学校4年生の悠斗くん(仮名)は、注意欠陥傾向があり、クラスでの集団行動や課題の提出に苦労していました。母親は「どうして他の子のようにできないの?」と叱咤することが多く、親子関係がぎくしゃくしていました。
家庭訪問時、支援担当の心理士が母親に投げかけた言葉:
「悠斗くんは“みんなと違う”けれど、それが悪いということではありません。『うまくいかない自分』をまず母親が受け入れてくれたら、彼ももっと安心できると思います」
母親ははっとして涙を流し、「あの子の“できない部分”ばかり見て、“努力してる姿”を見ようとしていませんでした…」と語りました。
このように、子どもに対する勇気づけは、まず大人自身の自己受容から始まることが多いのです。
「わたし」で生きるという選択
「人からどう思われるか」でなく、「自分がどうありたいか」で生きること。その第一歩は、ありのままの自分と手を取り合うことにあります。アドラー心理学は、「不完全であることを恐れない勇気こそが、人生を前に進める力になる」と教えてくれます。
最後に、この章のまとめとしてアドラーの有名な言葉を紹介します:
「あなたは他人の期待を満たすために生きているのではない。あなた自身の人生を歩むために生きているのだ」
この章では、「勇気づけ」というキーワードを中心に、自己受容と他者関係のバランス、日常における事例を通して、アドラー心理学が示す生き方のヒントを深めました。
次章では、より実践的なテーマとして「不完全さを認める勇気」について詳述し、困難の乗り越えや再出発のプロセスを探っていきます
第3章:不完全さを認める勇気――実例とケーススタディ
完璧主義という幻想の檻
「もっとできたはずだ」「失敗は許されない」「理想の自分でなければ意味がない」――そんな思考に支配されている人は、まさに“完璧主義の檻”の中で生きていると言えるでしょう。アドラー心理学はこのような思考を「人生の課題からの回避」とみなします。
完璧でなければならないという信念の背景には、「失敗=価値の否定」「欠点=存在否定」といった極端な自己評価の構造があります。この章では、アドラー心理学がいかに「不完全さの受容」を勇気と見なし、人生の困難を乗り越える鍵とするか、具体的事例を交えて考察します。
1. 不完全さは「劣等感」ではなく「成長の入口」
アドラーによれば、劣等感は人間にとって本来的な、かつ創造的な感情です。なぜなら、人は「今のままでは不十分だ」と感じることで、成長へと動機づけられるからです。つまり、劣等感とは欠点ではなく「向上しようとする意志の源泉」なのです。
ところが、劣等感を過剰に恐れ、それを隠すために他者評価に依存すると、人は「挑戦しない」「逃げる」「完璧であろうとする」などの回避行動に走ります。これが、アドラーのいう“優越コンプレックス”や“人生の嘘”という現象です。
2. 事例①:挫折を越えた起業家の話
翔太さん(仮名・28歳)は、大学卒業後に起業した若手経営者です。初期はSNSやメディアで注目され、順風満帆のように見えました。しかし、2年目の事業拡大で資金繰りが悪化。仲間も離れ、負債を抱えて撤退することになりました。
「周囲から“すごい人”って言われる自分でいたかった。でも失敗してから、人と会うのも怖くて、何もかも終わった気がしたんです」
翔太さんは失敗=自分の価値の否定と捉えていました。しかしカウンセリングや自己対話を重ねる中で、「自分は失敗した“経験を持つ人間”にすぎない」と考えられるようになっていきます。
アドラー心理学では、失敗とは「価値の欠如」ではなく「行動の結果」であり、「勇気ある挑戦の証」として捉えます。翔太さんはその後、失敗経験をもとに企業向けの起業支援コンサルに転身。過去を武器にする人生へと再出発を果たしました。
3. 事例②:自分を許せなかった母親
理恵さん(仮名・40代)は、高校生の息子と関係がうまくいかず悩んでいました。特に思春期になって反抗的になった息子に対して、「なんで素直に育たなかったの?私の育て方が悪かったの?」と自分を責める日々が続いていました。
そんな中で彼女が読んだのが、アドラー心理学の『嫌われる勇気』でした。「子どもは親の所有物ではない」「親は完璧である必要はない」という考えに触れ、彼女ははじめて「母親として完璧じゃなくてもいい」と思えるようになったのです。
その気づき以降、理恵さんは息子に「ママもよくわからないけど、一緒に考えてみよう」と正直に話すようになり、関係が徐々に改善されていきました。
ここで大切なのは、「不完全な親」である自分を認めることが、親子関係に“人間対人間”の信頼をもたらしたという点です。
4. 自分を認めることで他者を認められる
アドラー心理学では、人間の根源的な課題は「他者との関係性」であり、最も重要な概念が「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」です。この感覚とは、「自分も共同体の一部として受け入れられている」「他人も信頼できる存在である」という安心感です。
しかし、この共同体感覚は、まず「自分が自分を受け入れること」から始まります。自分の不完全さを受け入れられなければ、他人の不完全さも許せず、批判や比較が優位になります。
自己受容 ⇨ 他者受容 ⇨ 共同体感覚の育成
この順序が崩れると、「評価の支配」「競争の罠」に陥り、関係が損なわれるのです。
5. 実践のための小さな問いかけ
以下のような問いかけは、日々の生活で「不完全さを受け入れる勇気」を育む助けになります。
「今日、自分の失敗をどう捉えただろう?」
「誰かと比べて落ち込んだとき、自分に何と声をかけただろう?」
「“ありのままの自分”に点数をつけるなら何点?なぜその点数?」
こうした問いを通して、“自分との関係”を見直すことができれば、それは立派な勇気の行為です。
結びに:欠けたまま、美しく生きる
陶器の修復技法に「金継ぎ(きんつぎ)」という文化があります。割れた器の継ぎ目に金を施すことで、むしろその“傷”が味わいとなり、唯一無二の美しさを放ちます。私たちの人生もまた、欠けや不完全さを“隠す”のではなく、“活かす”ことで、より深い輝きを持ち得るのです。
不完全な自分を抱きしめ、「それでもいい」と自分に言ってあげられる勇気。それこそが、アドラー心理学が教えてくれる最大の自由なのです。
第4章:所属の欲求と評価への依存
孤独の恐れが「評価依存」を生む
人は本質的に「つながり」を求める存在です。誰かに受け入れられたい、社会の一部として認められたい――そうした願いは、文化や国を越えて人間の根源的な欲求です。アドラー心理学では、これを「所属の欲求」と呼びます。
しかし、この所属の欲求が過度になると、「他人からどう思われているか」「評価されているかどうか」が自己存在の支えとなってしまいます。これは「所属の欲求」が「評価への依存」にすり替わってしまった状態です。
たとえば、次のような言動を見聞きしたことがあるでしょう。
「嫌われたくないから、自分の意見を言えない」
「あの人より劣っていると思われたくない」
「うまくいっている自分だけを見せていたい」
これらの背景には、「所属していなければ価値がない」「評価されなければ受け入れられない」という深い不安が潜んでいます。
アドラー心理学における「共同体感覚」
アドラーは「人は社会的存在である」と前提づけ、人間の精神的健康と幸福は「共同体感覚」にかかっていると説きました。これは次の3つの要素から構成されます:
自己受容:不完全な自分でも、そのまま受け入れる姿勢
他者信頼:他人もまた信じるに足る存在であるという感覚
貢献感:自分は社会に役立っているという実感
しかし、所属の欲求が評価依存に傾いていると、この共同体感覚はゆがみ、次のような状態になります:
「評価されること=所属する資格」と思い込む
他人の承認がなければ自分に価値がないと感じる
自分らしさよりも“他人ウケ”を優先する
これは、アドラーが「人生の嘘」と呼んだ状態に他なりません。
事例①:SNSと“つながり”のパラドックス
高校生の陽菜さん(仮名・17歳)は、SNSでのフォロワー数や「いいね」の数に一喜一憂する毎日を過ごしていました。投稿する写真も流行や他人の目線を意識したもので、本当は行きたくないカフェにも「映えるから」と言って無理に出かけることがありました。
「友達と同じようにしてないと“仲間外れ”にされる気がするんです。いつも自分が“正解”の行動をしているかどうか、不安で仕方ありません」
アドラー心理学では、こうした「正解探しの生き方」は自己決定性の放棄ととらえます。つまり、「人生のハンドルを他人に握らせている」状態です。
陽菜さんはカウンセリングで、「自分はどうしたいのか」を主語にして話す練習を始めました。「私は本当はどう感じているか」「どんな関係を築きたいか」と自問し始めるうちに、「つながるために自分を失う」のではなく、「自分を持ったまま誰かとつながる」ことの可能性を見出すようになりました。
事例②:職場での「いい人症候群」
新入社員の祐介さん(仮名・24歳)は、職場で誰に対しても笑顔を絶やさず、頼まれた仕事はすべて引き受ける性格でした。しかし、ある日突然過労で倒れてしまいます。医師の診断は「適応障害」でした。
「嫌なことでも“断ると嫌われる”って思ってしまって…。気がついたら、自分が何を感じているのかも分からなくなっていました」
このような「いい人症候群」も、評価依存型の所属欲求が招く典型です。祐介さんは、「他者の期待を裏切らないこと」が人間関係維持の唯一の方法だと思い込んでいました。
アドラー心理学では、「人は他者の期待を満たすために生きているのではない」と明言します。そして、「自分の課題」と「他者の課題」を分離し、それぞれの責任を明確にすることを重視します(=課題の分離)。
祐介さんは、「断ること=悪」ではなく、「自己を守ること=信頼関係を育てる前提」と考えるようになり、徐々に本音で関われる同僚との関係を築くようになりました。
所属は「評価」ではなく「つながり」で成り立つ
真の所属とは、「条件付きの承認」ではなく、「無条件の存在承認」に支えられています。つまり、「役に立っているから」や「能力が高いから」ではなく、「そこに“いる”ことそのもの」が歓迎されているという感覚です。
アドラー心理学が説く共同体感覚は、こうした“存在レベルでのつながり”の実感に基づいています。それは「競争のない世界」であり、「人間関係における平等」が前提です。
この感覚を育むには、自分自身にまず問いかける必要があります:
「この人間関係は、評価でつながっているだろうか?」
「私は誰かの期待に応えるために“演じて”いないだろうか?」
「“つながりたい”という気持ちが、“怖れ”や“無理”になっていないだろうか?」
まとめ:評価から解き放たれた所属の実現
所属とは、他人の承認を勝ち取って得るものではありません。むしろ、他人の評価に振り回されず、「私はここにいていい」と思える場所と関係性の中で育つものです。
アドラーはこう述べました:
「人間のあらゆる悩みは、対人関係の悩みである」
そしてその解決は、「他人との違いを否定せず、違いのままに存在を認め合える勇気」によって初めて可能になるのです。
第5章:評価に揺れずに行動するライフスタイルのデザイン
評価の軸から自由になるとはどういうことか
現代社会は、目に見えない「評価の物差し」があらゆる場に潜んでいます。SNSの“いいね”やフォロワー数、学歴や職歴、仕事の成果といった外的評価に、人は容易に翻弄されます。
「このままではいけない」と思いつつも、他者の期待や評価を裏切ることが“怖い”。そんな中で、アドラー心理学が提唱する「自己決定性に基づくライフスタイル」は、評価に左右されない“自分らしさ”を再設計する手がかりとなります。
アドラーにとって「自由」とは、評価されない自由ではなく、「評価されても、自分の価値を自分で決められる自由」でした。そして、そのような自由は、“自己決定に基づいたライフスタイル”の確立なしには実現できません。
「ライフスタイル」とは何か?
アドラー心理学における「ライフスタイル」とは、生まれてからおよそ10歳頃までに形成される「世界の見方」「自分の価値観」「人間関係のパターン」などの総称です。性格とは異なり、「変えられないもの」ではなく、「選び取ってきたもの」「これから選び直せるもの」として理解されます。
たとえば、以下のような思考・行動の傾向はすべてライフスタイルの表れです:
「失敗するくらいなら挑戦しない」
「期待に応えられなかったら価値がない」
「他人に嫌われるのは自分のせいだ」
これらは環境の中で獲得された“信念”であり、自分を守るために選ばれてきた“戦略”でもあります。だからこそ、「自分の人生を再設計する」という視点に立てば、この“信念”を書き換えることが可能です。
事例①:「人に合わせる」ことをやめた女性
優子さん(仮名・35歳)は、常に周囲の顔色をうかがって行動するタイプでした。「本音を言えば嫌われる」「誰かが傷つくくらいなら、自分が我慢すればいい」と考えてきたのです。彼女のライフスタイルは「自己犠牲によって所属を維持する」スタイルでした。
しかし、その生き方に限界を感じ始め、アドラー心理学を学び始めます。彼女が最初に行ったのは、自分の行動の“目的”を見直すことでした。
「私が笑顔でいるのは、本当に楽しいから?それとも、嫌われたくないから?」
その問いに直面したとき、彼女は初めて「自分が“いい人”を演じていた」ことに気づいたのです。
彼女は徐々に、自分の意見を伝える練習を始めました。最初は怖さもありましたが、「嫌われても、自分の価値は減らない」と思えるようになるにつれ、関係もむしろ深まっていきました。
アドラー心理学の「目的論」において、行動はすべて“未来の目的”のために選ばれていると考えます。つまり、人は「どう見られるか」ではなく、「どうありたいか」に意識を向けることで、自分の生き方をデザインし直せるのです。
事例②:失敗からライフスタイルを見直した経営者
隆弘さん(仮名・42歳)は、中小企業の社長です。若い頃は成果主義で社員を厳しく管理し、「成果こそ正義」という信念のもとに会社を成長させてきました。
しかし、ある日部下が自殺未遂を起こしたことで、大きなショックを受けます。原因の一端に「プレッシャーの強すぎる社風」があると知り、「自分のスタイルは正しかったのか」と深く悩むことになります。
アドラー心理学のカウンセリングを受ける中で、彼は「自分は父から“強い男になれ”と育てられてきた」「だから“弱さを許せない”スタイルを身につけた」と気づきます。そして、それが「成果至上主義」という経営スタイルに反映されていたのです。
その後、彼は「社員の強みを伸ばす文化」「失敗を許容する空気づくり」に経営スタイルを大きく転換しました。これは、「他者貢献を中心に据えたライフスタイル」への大きな変化だったと言えます。
「自己決定性」とは、自分に責任を持つ自由
アドラーは「人間は環境の産物ではなく、自分の意思によって生き方を選んでいる」と述べました。これが“自己決定性”の考え方です。
「親がこうだったから」「社会が厳しいから」「過去に傷ついたから」――これらは確かに事実かもしれません。しかし、それを“今の生き方”の理由にし続ける限り、私たちは“過去の奴隷”になってしまいます。
アドラー心理学では、こう問います:
「その生き方を、これからも選び続けますか?」
選び直すことができる。それが、人生のハンドルを再び自分の手に取り戻すということなのです。
実践のヒント:「ライフスタイル再設計」のステップ
気づく:「私はなぜこの行動を選んでいるのか?」と自問する
振り返る:その行動は、どんな目的(安心・承認・優位性)を満たしてきたのか?
選び直す:「私はこれから、どんな生き方を選びたいのか?」
実験する:小さな言動から「新しい自分」を実践してみる
このプロセスは、習慣や思考の再設計に通じる“心理的ライフデザイン”です。
結びに:自分の人生の主人公として生きる
「人の目が気になって仕方ない」「失敗したらどうしよう」――そんな恐れが浮かんだとき、アドラーならこう言うでしょう:
「あなたの人生は、他人のための舞台ではない。あなた自身が、あなたの舞台の主演を務めるべきなのだ」
評価の軸から自由になり、「どう思われるか」ではなく「どう在りたいか」を選び直すこと。それこそが、“ライフスタイルの再設計”であり、勇気を持って人生を生き直す第一歩なのです。
第6章:教育・職場・家庭における展開
日常にアドラー心理学を活かすということ
アドラー心理学は、単なる理論や思想ではなく、「生き方の哲学」であり「人との関係性を築く技術」でもあります。本章では、これまで述べてきた「他人の評価に左右されない」「ありのままの自己受容」「不完全さの勇気」「共同体感覚に基づいた行動」といった要素を、具体的に教育・職場・家庭という3つの主要な生活領域でどう展開していけるのかを考察します。
1. 教育の場における勇気づけと自己受容
1-1. 「褒める教育」から「勇気づけの教育」へ
従来の教育は、「できたら褒める」「できなければ叱る」という“行動主義”の枠組みが主流でした。しかし、アドラー心理学はこれを乗り越え、「結果でなく姿勢・努力・意図に注目する勇気づけの教育」を提唱します。
たとえば、テストで満点を取った子どもに「すごいね!」と褒めるだけでなく、「計画的に学習を続けた努力が伝わるよ」とフィードバックする。このように“結果でなく内面”に光を当てることで、子どもは「他者評価でなく自己決定によって行動する力」を育みます。
1-2. 失敗を許容する教室づくり
教師や親が「失敗してもいい」と言葉で伝えるだけでなく、実際に“失敗に寛容な場”を作ることが重要です。例えば、「今日は間違えてよかったこと」を話す時間を持ったり、「一番苦労した問題は何だった?」という問いを授業の終わりに投げかけることで、子どもたちは「不完全でも認められる」体験を積んでいきます。
2. 職場における評価依存からの脱却
2-1. 上司の勇気づけが職場文化を変える
組織において上司が「結果」ではなく「貢献」や「意図」に着目することで、部下のモチベーションは大きく変化します。
例えば、ある中間管理職が、「今回の企画、予算は通らなかったけれど、過去にないアイデアを出してくれた姿勢が本当にありがたかった」と伝えることで、部下は「挑戦すること自体が価値あること」と受け取り、次の行動につなげやすくなります。
このように、「上司の視点」が「部下の自己概念」を育てるという観点が、アドラー心理学では重要です。
2-2. 課題の分離による信頼関係の再構築
職場では、業務の失敗やコミュニケーションの摩擦から「誰の責任か」をめぐって関係がぎくしゃくしがちです。アドラー心理学の「課題の分離」を用いれば、責任の所在と感情の所有を切り分け、建設的な関係が築きやすくなります。
例:報告ミスをした部下に「なぜ報告しなかったんだ?」と責めるのではなく、「この報告はあなたの課題。だが、その結果をどう活かすかは私たちの課題」と伝えることで、信頼と責任の両立が可能になります。
3. 家庭における「条件なき所属感」
3-1. 子どもが「存在しているだけで愛される」体験
アドラー心理学において、子どもが最も必要とするのは「無条件の愛」、すなわち「存在しているだけで受け入れられている」という感覚です。これは、子どもの成績や振る舞いとは関係なく、「あなたがそこにいるだけで、私にとって大切な存在だ」と伝える姿勢から生まれます。
例:何かを失敗したときに「どうしてそんなことしたの!」ではなく、「大丈夫、あなたのことは何があっても大好きだからね」と最初に伝える。これが、自己受容の基盤となる“安心基地”を作ります。
3-2. 親自身の不完全さを示す勇気
親が「完璧であろう」とするあまり、子どもに対しても「理想の姿」を押しつけてしまうことがあります。しかし、親が「ママも今日うまくできなかったよ」「パパもミスしたけど、どうしたらよかったか考えてる」と話すことで、子どもは「不完全さは悪ではない」という価値観を内在化します。
家庭は「最初に自分らしくいられる場所」であるべきです。そこに“評価からの自由”がなければ、子どもは「家でも演じなければならない」という二重のストレスを抱えることになります。
教育・職場・家庭を貫く共通項:「勇気を与える関係性」
どの場面においても、アドラー心理学が一貫して重要視するのは「勇気を与える関係性」の構築です。つまり、相手が「今のままの自分でもいい」「不完全であっても社会に貢献できる」と感じられるように接すること。
この関係性は、評価や期待を超えた“信頼”と“尊重”によって生まれます。
結びに:小さな日常が、共同体感覚を育てる
教育・職場・家庭――これらはすべて、日々のささいなやり取りで成り立っています。そして、その一つひとつが、人に「自分は価値ある存在だ」と感じさせる機会でもあります。
評価されることではなく、「つながっている」「必要とされている」と感じること。それが人を支える本当の力であり、アドラー心理学のいう“共同体感覚”です。
「人は支えられることで強くなるのではない。自分が誰かを支えていると感じたときに、強くなる」
そのような共同体感覚が、家庭、学校、職場に広がっていくことが、私たちの未来に必要な“人間の在り方”なのです。
第7章:困難や感情の波との向き合い方
感情は「問題」ではなく「メッセージ」である
人間は感情の生き物です。喜び、怒り、不安、悲しみ、羞恥、罪悪感――こうした感情はときに激しく、予測不能に訪れ、私たちを揺さぶります。特に「不快な感情」は、人生の困難と結びつきやすく、「自分の心をどう扱えばよいか分からない」という戸惑いを生みます。
アドラー心理学では、感情は「行動の目的に従属する」と考えます。つまり、感情は“原因”ではなく“目的”を持っているという視点です。この視点を持つことで、私たちは感情に「流される」のではなく、「読み解き、活かす」ことが可能になります。
怒り:自分の正当性を守るための手段
怒りという感情は、多くの場合「自分の価値が否定された」「尊重されなかった」という主観的な“危機”に対する反応として現れます。しかしアドラーは「怒りは相手を支配する手段である」と述べています。
たとえば、親が子どもに対して「なんで言うこと聞かないの!」と怒鳴る場面。これは「親の思い通りにならない状況」によって、「自分の権威が損なわれた」と感じ、怒りという感情を選んでいるのです。つまり、怒りは「相手を自分の望む方向に動かす」ための戦略なのです。
この構造に気づけたとき、私たちは「怒らない親」「穏やかな自分」への第一歩を踏み出せます。怒りが湧いたときこそ、自分にこう問いかけてみましょう:
「私は今、何をコントロールしようとしているのか?」
この問いは、怒りを自己認識の契機とし、相手との新たな関係性づくりへとつながります。
不安・恐れ:行動の回避を正当化する感情
アドラー心理学では、「不安」もまた目的を持った感情だと考えます。たとえば、プレゼン前に不安を感じるとき、それは「失敗して評価が下がるのを恐れている」からかもしれません。しかし、実はその裏に「挑戦を避けることで自尊心を守りたい」という無意識の目的があることもあります。
この場合、不安は「行動しないことを正当化する道具」になっているのです。
アドラーは、こうした状態に対し、「不安を理由に行動を止めることは、自分の人生の主導権を放棄することだ」と述べました。では、不安を感じたときにどうすればよいのでしょうか?
鍵は、「小さな行動から始めること」です。
100点満点の行動ではなく、30点の試行をしてみる
結果ではなく、行動した“事実”を自分で承認する
できなかったことより、“やってみた”ことに注目する
こうして「動ける自分」の実感を積み重ねることで、不安という感情は次第に“行動の敵”ではなく、“自己理解の味方”へと変わっていきます。
劣等感・自己否定:人は比較から自由になれるか
劣等感は、アドラー心理学において中心的な感情のひとつです。それは「人より劣っている」「自分には価値がない」といった主観的な感覚ですが、これは本来“成長への原動力”として機能します。
問題は、「劣っている=価値がない」という思い込みです。たとえば、「学歴が低いから」「容姿に自信がないから」といった理由で、自分を否定し、他人と比べて落ち込むというサイクルに陥ることがあります。
しかし、アドラーはこう述べています:
「他人との比較ではなく、“昨日の自分”との比較だけが、あなたの人生を豊かにする」
つまり、自己価値の基準を“相対的”なものから“絶対的”なものへ移行させることが、劣等感との健全な向き合い方なのです。
劣等感が湧いたときには、こう問い直してみましょう:
「私は本当に“誰かに勝つこと”を望んでいるのか?」
「昨日よりも自分らしくいられた瞬間はあっただろうか?」
「私だけの“できていること”は、何かあったか?」
このような問いは、比較の呪縛から私たちを少しずつ解放してくれます。
感情と“仲直り”するためのステップ
アドラー心理学では、感情は“目的に従属する行動の一部”であると同時に、「変えられるもの」として捉えます。以下は感情との向き合い方の基本ステップです。
感情に気づく:「今、私は◯◯を感じている」と正確に言語化する
感情の“裏の目的”を探る:「この感情で、私は何を守ろうとしているのか?」
感情を責めない:「こんな感情を持ってはダメ」ではなく、「感じてもいい」と許す
小さな行動を選ぶ:「感情に反応する」のでなく、「価値に沿って選ぶ」
フィードバックを得る:実践を振り返り、「感情の波とどう付き合えたか」を検証する
このプロセスを繰り返すことで、感情は“敵”ではなく“案内人”となり、人生をより主体的に歩む力を私たちにもたらします。
結びに:感情に揺れても、人生は前に進む
困難や感情に揺さぶられるのは、人間としてごく自然なことです。むしろ、「感情が揺れる」ということ自体が、「今を誠実に生きている証」であり、自分の価値観や願いに触れている証拠とも言えるでしょう。
アドラー心理学は、「感情をコントロールする」よりも、「感情の意味を読み解き、選び直す力」を大切にします。感情を敵にするのではなく、パートナーに変えていくことで、私たちはどんな困難にも“心のハンドル”を手放さずに進むことができるのです。
第8章:不完全さの中で生きる勇気と共同体感覚の深化
「完全ではない私たち」がつながりの中で育つということ
人は誰しも、何かしらの不完全さを抱えています。失敗する自分、劣等感に揺れる心、他者との関係に傷つきながらも関わりを求める姿。そうした姿は決して「弱さ」の象徴ではなく、「生きる力のありのままの姿」です。
アドラー心理学は、その不完全さを否定せず、むしろ「不完全であることこそが、人間らしく、成長し続けるための前提」であるとします。そしてその視点は、人生の核心にある「共同体感覚」へとつながっていきます。
共同体感覚とは何か?
アドラーが晩年まで説いた「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」とは、単なる“仲良くする感覚”ではありません。それは、自分が他者とつながっており、他者もまた信頼に足る存在であり、そこに自分なりの貢献ができるという実感です。
この感覚を持つことで、人は「競争」や「承認欲求」から自由になり、「自分のままで社会に居場所がある」と信じることができます。
共同体感覚は、以下の3つの支柱によって構成されます:
自己受容:不完全な自分をそのまま認める
他者信頼:他人を敵ではなく、共に生きる仲間として捉える
他者貢献:自分の存在が誰かのためになっていると実感する
不完全である勇気が「つながりの回路」を開く
共同体感覚を深めるには、「弱さを見せる勇気」が不可欠です。完璧な人間でいようとすると、他者とのあいだに“壁”が生まれます。しかし、自分の不完全さを認め、それを開示することで、逆に深いつながりが生まれるのです。
たとえば、以下のような場面:
教師が「先生も間違えることがあるんだ」と語る
親が「ママも迷うことがある」と子どもに伝える
上司が「うまくいかないこともあるよ」と部下を励ます
こうした言葉には、「不完全さを否定しない空気」「完璧でなくていいという安心感」があり、それが人間関係の土壌となります。
事例:介護の現場で変わった人間関係
佐和子さん(仮名・50代)は、認知症の母を介護しながらフルタイムで働いていました。毎日の介護と仕事の両立に追われ、完璧にこなそうとするほど自分を追い詰めていました。
ある日、母に対して感情を爆発させてしまったことをきっかけに、「私はダメな娘だ」と思い込むようになります。しかし、介護者支援グループで「私も同じようなことがあった」と語る仲間と出会い、「失敗しても、感情的になっても、それでも愛している気持ちは変わらない」という言葉に触れます。
彼女は徐々に、「完璧にこなすこと」よりも「共に過ごすことの質」に意識を向けるようになり、自分の不完全さを責めるよりも、母との関係に愛情を注ぐ選択をするようになったのです。
このように、「不完全さを抱えたまま共に生きる関係性」は、共同体感覚の実体験そのものと言えるでしょう。
「役に立つ」よりも「共にある」ことの価値
現代社会では、「役に立つ人間」であることが求められがちです。しかし、アドラー心理学においては「貢献」は、スキルや結果に基づくものだけではありません。むしろ、「その人がそこに“いる”こと」自体が貢献となり得ると考えます。
たとえば:
落ち込んでいる友人の隣に“黙って座る”こと
職場で特別な成果はなくても“空気を和ませている”こと
家族と一緒に“今日もご飯を食べる”こと
これらの行動は、目立たないけれども、確実に他者の心を支えている貢献です。
生きるとは、「未完成な自分で共同体に参加し続けること」
人生は常に“途中”です。昨日よりは少し前進したかもしれない。でも今日は後退したように感じるかもしれない。アドラーはそんな日々に対して、「人は最善を尽くすことで価値を持つ」と語ります。
「人間の価値は、完成された姿ではなく、“どう生きようとしているか”にある」
共同体感覚とは、完成された“理想の自分”になったときに得られるものではなく、「今の自分で、誰かと関わり、誰かに手を差し出す」ことで育まれるものです。
結びに:勇気はいつも、“不完全さ”の隣にある
ここまでの章を通して見てきたように、アドラー心理学が語る生き方は、「他人の評価に依存しない」「ありのままの自分を受け入れる」「不完全でも歩み続ける勇気」に貫かれています。
そしてその道は、「他者とのつながり」「共同体への貢献」という、普遍的な人間の願いへとつながっています。
「誰かのために完璧な自分でいよう」とするのではなく、
「不完全なままでも、誰かとつながり、支え合える自分でいよう」
そう思えることこそが、アドラー心理学の核心であり、これからの時代を生きる私たちにとって最も大切な哲学なのです。

ショパン・マリアージュは貴方が求める条件や相手に対する期待を明確化し、その基準に基づいたマッチングを行います。これにより、結婚生活の基盤となる相性の良い関係性を築くためのスタートを支援します。また、結婚に関するサポートや教育を通じて健全なパートナーシップを築くためのスキルや知識を提供します。
あなたに合った結婚相談所が
見つかります!
 オススメが知りたい人向け!
オススメが知りたい人向け!お気軽に連盟スタッフにご相談ください。
あなたに合った結婚相談所をご紹介いたします。
 自分で調べたい人向け!
自分で調べたい人向け!活動がしやすい環境がとても大切です。また担当者との相性も重要なポイント。ぜひあなたに合った結婚相談所を見つけてください。
